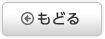意見書
教育基本法の「全部改正」案についての緊急意見書
第二東京弁護士会
第1 はじめに
1.教育基本法の法的性格
政府は、本年4月28日、現行の教育基本法の「全部を改正する」法案(以下、「「全部改正」案」という)を国会に提出し、現臨時国会において審議が開始されている。
1947(昭和22)年3月31日に公布・施行された現行教育基本法は、前文と全11条から成るシンプルな法であるが、次の性格を有する。
第1に、その前文に「憲法の理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである」とあるように、憲法価値を教育により実現しようとしたものであり、憲法と不可分一体をなす<準憲法的>な性格を持つ法律である。第2に、憲法26条の「教育を受ける権利」を実現するために営まれる教育の基本原理を定めたものであり、<教育憲法>としての性格を持つ法律である。
旭川学力テスト事件最高裁大法廷判決(1976年5月21日)も、「教育基本法は、憲法において教育のあり方の基本を定めることに代えて、わが国の教育及び教育制度全体に通じる基本理念と基本原理を宣明することを目的として制定されたものであって、戦後のわが国の政治、社会、文化の各分野における諸改革中最も重要な問題の一つとされていた教育の根本的改革を目途として制定された諸立法の中で中心的地位を占める法律であり、このことは、同法の前文の文言及び各規定の内容に徴しても、明らかである」と明示しているところである。
このような法的性格を持つものとして成立した教育基本法は、一方で「教育の機会均等」を定めた第3条や、「男女共学」をうたった第5条などに見られるように、憲法下の新しい教育の<あるべき筋>を打ち出したものであり、他方で学校における政治的活動を禁じた第8条2項や、公立学校における宗教的活動を禁じた第9条2項などが示すように、教育の<あってはならない筋>を明示するものでもある。
このように、教育基本法の各条項は、いずれも「教育を受ける権利」を保障し実現する責務を負う者に向けられた規範であり、公教育について責任を負い「権力」を行使する者を名宛人とするものであって、彼らの教育へのかかわり方に枠をはめ、その権力行使のありかたを拘束することに法の基本的役割があり、子どもや親・市民を規範的に拘束しようとするものではない。
2.「全部改正」案と教育基本法の変質
しかし、政府の提案した「全部改正」案は、第2条において教育の目標を詳細に規定し、子どもが教育において目標とすべき徳目を20項目以上にわたって掲げている。
また、第6条(学校教育)の第2項において「教育を受ける者が、学校生活を営むうえで必要な規律を重んずる」ことを求めている。
さらに、第10条(家庭教育)において、父母に「生活のために必要な習慣を身に付けさせる」「自立心を育成」「心身の調和のとれた発達をはかる」ことを求めたうえで、第13条で「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする」と規定している。
これらの規定に顕著に見られるように、「全部改正」案は、<権力拘束規範>であった教育基本法の本質を大きく転換し、<国民への命令規範>をも加えようとするものであり、法の基本性格を変質させるものである。
第2 教育基本法「全部改正」の立法事実は存在しない
1.政府の「全部改正」案提出の理由
(1) 「全部改正」案提出の理由として、政府は、「我が国の教育をめぐる諸情勢の変化に鑑み、時代の要請に応える我が国の教育の基本を確立するため」とだけ述べており、それ以上に、全部改正の必要性を根拠づける具体的な事実、すなわち、立法事実についての明確な説明はなされていない。
(2) この点、「全部改正」案に関する文部科学省の説明資料では、「教育をとりまく環境は大きく変わり、子どものモラルの低下、学ぶ意欲の低下、家庭や地域の教育力の低下していること」などが教育基本法の「全部改正」の必要性として挙げられている。また、同説明資料に添付されている中教審答申(平成15年3月20日)では、「青少年が・・・・規範意識や道徳心、自律心を低下させている。いじめ、不登校、中途退学、学級崩壊などの深刻な問題が依然として存在しており、青少年による凶悪犯罪の増加も懸念されている」と指摘されている。国会でも、政府の言う「様々な課題」が何であるかについての太田昭宏議員の質問に対し、小泉首相(当時)は、教育の現状認識として、「近年においては、道徳心や自立心の低下が指摘され、いじめ、不登校さらには家庭や地域の教育力の低下など、様々な課題が生じて」いるとの答弁をしている。
しかしながら、教育基本法の「全部改正」によって、上記の「様々な課題」、つまり、いじめ問題や青少年による凶悪犯罪の増加の問題を解決できるという政府の認識は、これらの問題が発生する背景を理解しておらず、根本的に誤っている。以下、この点について、特に「いじめ問題」と「少年犯罪」に絞って検証することにする。
2.いじめ問題
(1)上記のように、政府は、現行教育基本法の下で生じている深刻な問題の一つとして、いじめ問題を挙げ、その原因が子どもたちの道徳心・自立心の低下であるかのような認識を示している。
しかし、いじめの原因・背景にあるものは、そのように単純なものではなく、子どもたちをとりまく環境の悪化などに起因しつつ、具体的ケースごとに多様である。これらの問題に目を向け解決せずして、子どもたちに対して道徳心や自立心の向上だけを求めても、いじめ問題を解決することはできない。
(2)当会では、1990年以来、子どもの問題に関する常設の相談窓口として「子どもの悩みごと相談」を実施しているが、そこに寄せられる相談の中でも、いじめに関する相談の割合は高く、同相談開設後10年間の全電話・面接相談件数2952件中、いじめは597件と約2割にものぼっている。その後もこの傾向は続き、昨年は、いじめに関する相談が全電話相談206件中46件とやはり約2割を占めている。
そして、当会では、いじめが、子どもの人権を侵害する極めて深刻且つ重大な問題であり、見過ごすことができない問題であるという共通の認識にもとづいて、上記相談窓口の相談担当者は相談に臨み、ケースによっては、助言のみに止まることなく、いじめを受けた子どもやその保護者と直接会って事情聴取等を行い、子ども自身の意思や希望を最大限尊重しながら、学校や加害者との交渉、いじめ解消のための環境調整への協力、法的手続等の救済活動を行なうなどして、いじめ問題に取り組んできた多くの実績がある。その実績・経験を通じても、具体的なケースごとに、いじめの原因・背景は様々であることが裏づけられる。
このように、いじめ問題の原因・背景には多様な要素が存在するものであり、政府が目論んでいる教育基本法の「全部改正」によって、いじめ問題の解決につながるものではないことは明らかである。
3.少年犯罪
(1)上記のとおり、「全部改正」案の説明資料中にある中教審答申では、青少年による凶悪犯罪の増加への懸念を指摘している。また、これまでの流れを振り返ると、教育基本法の「全部改正」の動きの背景には、世間の耳目をひく少年犯罪の発生があるように思われる。現行教育基本法の影響により、子どもたちの権利や自由意識が強調される一方で規範意識が低下し、少年犯罪へと繋がっているという見方があるからである。しかしながら、以下に述べるようにそのような図式は存在しない。
(2)日弁連は2001年に開催された第44回人権擁護大会において「少年犯罪の背景・要因と教育改革を考える」というテーマで報告を行っているが、まさに上記観点を含めて昨今の少年犯罪について相当数のデータ(重大事件14件並びに非行少年、保護者、弁護士及び一般高校生を対象にした調査票の有効回収数1987票)を基に具体的な調査を行い、少年犯罪の背景・要因について考察を加えている。
これによれば、少年犯罪全般、特に少年重大事件において、非行少年自身の被虐待体験事例の多さが目立つこと、虐待を含む家族関係や交友関係上の問題、少年自身の精神疾患、学校内での学業成績重視の傾向やいじめなど、その問題性が深刻であり、背景事情が複雑であることなどが報告されている。
他方で報告は、非行少年以外の一般高校生を含んだ調査結果から、逸脱傾向のある生徒の方が正義感が強いなど、少年の規範意識については「規範意識が低いから非行を犯す」という図式がそのまま通るわけではないことを指摘している。
これらの調査結果からわかることは、少年犯罪の背景・要因としては、当然、複雑な事情が絡み合っているが、少なくとも、子どもたちの権利や自由意識の強調が、少年犯罪に結びつきやすいという命題は成立しないということである。
むしろ、上記調査結果によれば、今日の子どもの問題行動は、幼児時代からの虐待や、学校でのいじめ、体罰などで虐げられ、人間の尊厳を傷つけられ、ときには生命侵害に及ぶ人権侵害を受け、受験戦争の中で将来に対する不安を抱かされるというストレスに曝され、それぞれの人格を尊重し、それぞれの個性に応じて学び、成長する機会を奪われている子どもたちの悲鳴であり、子どもの権利が保障されていない状況を示すものである、と言える。
(3)こうした状況に対し、「全部改正」案が何らかの効果ある対策を示しているものではない。前記のような子どもたちの陥っている状況・環境を改善する方策を示すことなく、子どもたちの権利や自由意識を問題にするだけでは、少年犯罪問題を解決できるものではない。しかも、「全部改正」案は第10条において、「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有する」として家庭の責任のみを強調しているが、かかる改正は、上記日弁連の報告でも述べられているように「家庭のしつけ」の強迫観念による育児ノイローゼなどからの親による虐待、教育競争下での親の過干渉により、子どもたちが生命の危機に曝され、発達の歪みを招いている実態を無視するものであり、子どもたちの状況の悪化を助長するおそれさえある。子どもたちの状況を改善するために求められているものは、親に対する適切な支援であり、家庭の責任のみを強調することは逆効果の危険があるのである。
(4)当会では、少年当番弁護士制度や当番付添人制度を実施し、また、重大・困難事案について個別の事件を受任・サポートするほか、法改正に対する提言や少年事件の処理に関するマニュアルの策定などを行ってきた。また、一般会員が参加できるケース研究会を通じ、参考となるべき具体的事件処理を担当弁護士に報告してもらい、議論を重ねてきた。
このような当会の活動実績からも、上記の指摘は裏づけられるものである。
(5)以上のとおり、「全面改正」の背景の一つと目される少年犯罪について、実態に照らして考察を加えても、少年犯罪減少のために教育基本法を改正しなければならないという立法事実は全く認められない。逆に、「全部改正」案は子どもの人権保障という教育目的を軽視する点で子どもの問題行動や少年犯罪に結びつく可能性を有しており、弊害が大きいといわざるを得ない。
4.小括
上記のように、いじめ問題、少年犯罪といった子どもに関する二つの大きな問題の原因・背景を検討すること等によって、政府の「全部改正」案には、それを必要とする立法事実がないこと、それのみならず、「全部改正」案によって、子どもの人権が侵害されるなどの弊害が生じ、かえっていじめや少年犯罪の増加につながりかねない危険があることが指摘できる。
教育基本法は、憲法、子どもの権利条約とともに、子どもの権利保障を担う基本法として重大な役割をもっている。現行教育基本法の理念を生かし、子どもの権利保障を確立した教育を行い、現行法の理念を子どもたちの現状に積極的に及ぼすことこそが、いじめその他の子どもの問題行動や少年犯罪を抑制することにつながるというべきである。
第3 教育行政の変質-第10条の解体と第16条・第17条への組み換えの意味
1.教育行政に関する改正法案の概要
「全部改正」案第16条(教育行政)は、現行法第10条第1項の「教育は、不当な支配に服することなく」という文言は残したものの、「国民全体に対し直接に責任を負って」との文言は削除し、代わって「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべき」と規定している。また、現行法第10条第2項「教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行わなければならない。」を全文削除し、「教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない」と新しく規定(第16条第1項後段)し、国に対しては、「教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し実施」する義務を課している(第16条第2項)。そのうえで、第17条(教育振興基本計画)を新設して、政府には「教育の振興に関する施策についての」「基本的な計画」を定める権限を付与し、自治体に対しては「地域の実情に応じ」た教育振興計画を定めるよう「努める」義務を課している。
2.教育行政の役割の変質
しかし、現行法第10条の教育の直接責任と教育行政の条件整備義務の原則は、戦前の教育に対する深い反省に基づいて定められたものであり、教育がときの国家権力の政治的な意思に左右されずに、自主的・自律的に行われることを保障するうえで重要な役割を果たしてきた。前記旭川学力テスト事件最高裁大法廷判決も、教育が「本来人間の内面的価値に関する文化的な営み」であり、「教育内容に対する国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請される」として、国家の教育内容への介入に対して慎重に歯止めを課したうえ、現行法第10条については、「教育行政の目標を教育の目的の遂行に必要な諸条件の整備確立に置き・・・教育の自主性尊重の見地から、これに対する『不当な支配』となることのないようにすべき旨の限定を付したところにその意味があり、したがって、教育に対する行政権力の不当、不要の介入は排除されるべきである」として、教育行政も「不当な支配」の主体となりうるとしている。従って、この2つの原則を削除したうえで、教育が「法律の定めるところにより行われるべき」とすることは、「不当な支配に服することなく」という文言を残したとしても、現行法第10条の立法趣旨を根本から否定することになる。
すなわち、教育は「不当な支配に服することなく」「法律の定めるところにより行われるべき」とすることは、法律に根拠がある限り、教育行政による教育内容への過度な介入も適法化されて、「不当な支配」に該当しないことになるおそれがあるとともに、「不当な支配」が権力によるものに限られないことを意味することにもなる。そのため、本来の意味とは逆に、本来教育に反映されるべき教師や保護者、地域の人々の意見などが組織的に集約された場合など、「不当な支配」として排除されてしまうようなおそれが生じる。その結果、残された「不当な支配に服することなく」という文言は、法規範としては全く逆の意味を持ってしまうことになるのである。
3.組み換えられた「全部改正」案の問題点
このように、現行法第10条第2項の規定を削除したうえ、国に教育に関する施策の策定権限を付与するのは、教育行政の役割を「条件整備」を超えて教育内容の決定にまで拡大させ、教育の自主性・自律性を奪うことを正面から認めることを意味する。
また、第17条第1項は、政府に対して教育振興基本計画の策定と国会への報告、公表を義務づけているが、これは、第16条第1項の規定と相俟って、国会が教育内容の決定に深くかかわり介入してくることを正面から認めることになる。
さらに、自治体の教育振興計画の策定も、その策定主体が教育行政機関である教育委員会ではなく、自治体当局とされているため、首長部局による政治主導の計画策定となるおそれがある。
以上のように、現行法第10条を解体し、第16条及び第17条に組み換えるのは、国会や政府といった時の政治権力が、教育内容を統制して教育現場の自主性・自律性を剥奪することにつながる法的整備であるというよりほかない。これによって、教育基本法は、教育の自主性保障法から教育の権力統制正当化法へと、その基本精神を180度転換させられることになる。
第4.思想・良心の自由が侵害される危険性
1.「全部改正」案は、現行法第2条(教育の方針)を削除し、代わりに第2条(教育の目標)を定めている。そこでは、個人の意志・意欲や内心に関わる事柄を含む数多くの事項(徳目)を5項目に分けて幅広く取り上げ、これを「国家が望むもの」=教育の目標として定めている。
2.ここで取り上げられた「徳目」は、本来多様性を持つ多義的な概念であり、一義的に決定できるようなものではない。しかしながら、これらが達成すべき「教育の目標」として教育基本法に規定されるならば、教育の場においては、公的に一定の価値選択がなされオーソライズされた具体的な内容を持つものとして一義的に決定され、その決定された一方的な観念が子どもたちに植え付けられることになりかねない。そして、これが「教育の目標」とされるのであるから、目標への達成度が成績の評価の対象となることは避けられないことである。
3.とりわけ、第5号では、「伝統と文化を尊重し」、「我が国と郷土を愛する」「態度を養う」ことを掲げている。しかし、国を愛する態度を養うことを、達成すべき「教育の目標」として教育基本法に規定するならば、教育の場において、公的に一定の価値選択がなされ具体的な内容を持つものとして一義的に決定された一つの考え方が子どもたちに一方的に教育されることになりかねない。愛国心を含む内心に関わる事柄を、「教育の目標」として改正案に定めることは、結果として憲法19条を中心とする「内心の自由」に抵触するおそれがある。また「伝統・文化の尊重」も、何を「伝統」とするかあいまいなままいわゆる「愛国心」と結びつけられるおそれがあり、「愛国心」を直接にうたわないことで問題が回避されるものではない。
4.以上のように、愛国心を含む内心に関わる事柄を、「教育の目標」として「全部改正」案に定めることは、憲法19条を中心とする「内心の自由」に抵触するおそれがあるといわなければならない。
第5 結論
以上のとおり、政府により上程された現行教育基本法の「全部改正」案は、子どもたちを巡る諸問題の解決に結びつかず、逆に、子どもたちの管理を強め、子どもの内心も規制して子どもの権利を空洞化する危険性を有するものであるので、当会は法案に反対であり、直ちに廃案にすることを求めるものである。