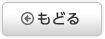少年法の適用年齢の引下げに反対する会長声明
2015年(平成27年)6月11日
第二東京弁護士会会長 三 宅 弘
15(声)第4号
公職選挙法の選挙年齢の改正に伴い、自由民主党は、少年法の適用対象年齢等の引下げに関し、「成年年齢に関する特命委員会」を設置し、検討を始めた。
しかし、法律の適用年齢を考えるにあたっては、それぞれの法律の立法趣旨に照らし、個別の法ごとに立法趣旨を慎重かつ具体的に検討すべきであり、1つの年齢で画するという発想は、単純にすぎ、制度として未熟である。
人間の能力は、体格や体力の成長や発達に比例して一律に成熟するものではない。
現行少年法の適用年齢は、20歳までの非行が、未だ心身の発達が十分でなく、環境その他外部的条件の影響を受けやすいため起こるものであり、刑罰よりも保護処分による方が適切である場合が極めて多いことを理由として設定された。
その後、我が国では、18歳で経済的に自立している者の数は激減している一方、精神的・社会的に未熟な若年者が増加していると指摘されており、我が国の政策においても、手厚い成長支援の対象は、広げられる方向にあるから、少年の「成人」年齢を引き下げる理由はない。
また、少年法は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた重大事件に関し、原則として裁判員裁判を経て刑事罰を科すと規定している(少年法20条2項)。さらに、これらの少年に適用される刑についても、2014年の少年法改正によって重罰化がされたばかりである。
したがって、少年法が18歳以上の少年を過剰に保護しているとの批判はあたらない。
他方、2013年における行為時18歳以上の少年の一般保護事件の件数は、2003年に比べて51%も減っている(ちなみに、この間の世代人口の減少率は16%にとどまる。)。
事件数の面からも、現在、少年法改正が必要であるとの状況にはない。
むしろ、少年法の「成人」年齢の引下げは、再非行防止の観点で重大事件でない大多数の事件に与える悪影響が著しい。
現行の少年法は、少年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識、特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用した調査を前提とし(少年法9条)、それを踏まえた適切な処遇によって再犯防止を図ってきた。
少年法は、検察官の起訴猶予を認めず、全件を家庭裁判所へ送致することとしている。成人では比較的軽微とされ、実刑にならない事件であっても、少年であれば少年院送致となる場合があり、成人と比して厳しい場合も少なくない。他方、2013年の成人事件の公判請求率は7.3%、第一審での実刑率はそのうちの39%であるから、少年法の「成人」年齢を引き下げると、その多くが、起訴猶予や罰金、執行猶予となり、犯罪の背景・要因となった資質や環境上の問題点に関する調査・分析と立ち直りのための手当がされないままに手続が終わることになる。これでは、更生と立ち直りにはつながらず、犯罪抑止の観点からは、改正論者の主張するところと反対の結果をもたらすことになろう。
州ごとに法制の異なるアメリカ合衆国における実証的研究でも、刑事裁判所に送致された少年の予後は、少年裁判所での審判を受けた少年よりも悪いとされている。
可塑性のある年齢においては、少年法に基づく手続によって、しっかりとした調査と矯正のための教育を実施した方が、将来、社会の真っ当な構成員に育つことが期待できる。社会全体の利益や費用負担の観点からも、少年法の「成人」年齢は維持されるべきであると考えられる。
以上のとおりであるから、当弁護士会は、少年法の適用年齢の引下げに強く反対する。