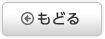公害紛争処理制度の見直しについての提言
提言の目的
昨秋から今春にかけて、政府の公害等調整委員会(以下「公調委」という。)において「公害紛争処理制度に関する懇談会」(以下「公調委懇談会」という。)が開催された。公調委懇談会では、現行制度の運用や改善の方向性等について幅広く議論され、その半年間の討議結果が報告書として公表されたところである。
具体的な制度改正が今後始まることが予想される。利用者の目線からその内容や方向性に関する重要点を以下挙げ、人権擁護および環境保全の充実を図るべく提言する。
提言の趣旨
提言1
公害紛争処理法(以下「法」又は「本法」という。)の対象範囲を広げるべきである。具体的には、公調委、都道府県公害審査会、都道府県及び市区町村の公害苦情相談が取り扱う対象範囲を、現行の「公害」から環境に係る被害またはそのおそれ全般へと拡げるべきである。
本法の対象とする「環境に係る被害またはそのおそれ」には、次のものを含めるべきである。
(1) 公害
(注)現行法どおり、環境基本法2条3項の「公害」の定義と同じ。
(2) 公害類似の被害。すなわち公害以外の、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる環境の保全上の支障によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む)に関して生ずる被害
(注)「公害」の定義から、相当の範囲の要件および典型7公害の要件を外した被害のうち、公害以外のもの。
(3) (1)、(2)以外の被害またはそのおそれのうち、人間の健康で文化的な生活に対する環境上の被害またはそのおそれ、または生態系の破壊またはそのおそれ
(注)環境基本法3条を参考にした、対象範囲の拡張。
提言2
前項に伴い、法令や機関の名称を変更すべきである。具体的には以下のとおり。
「公害紛争処理法」 → 「環境紛争解決法」
「公害等調整委員会設置法」→ 「環境紛争等調整委員会設置法」
「公害等調整委員会」→ 「環境紛争等調整委員会」
「都道府県公害審査会」→ 「都道府県環境紛争審査会」
提言の理由
第1 提言1について
1 公害類似の被害へ対象を拡張
(1) 現行の法2条の「公害」の定義は、環境基本法2条3項の公害の定義をそのまま準用している。そのため、「相当範囲にわたる」という相当の範囲の要件と、大気汚染や水質汚濁といったいわゆる典型7公害の事象に限るという対象類型の要件が存在する。しかしながら、以下述べるとおり現状の運用や紛争解決要求との間で齟齬が生じているため、法の対象範囲を公害だけに留めることは狭きに失し、これらは見直されるべきである。
(2) まず、「公害」の相当の範囲の要件には、次の問題点がある。
① かつては産業型公害への対処が喫緊の課題であったが、社会の変容(たとえば、生活様式の多様化、地域コミュニティーの弱体化等)の結果、環境に関する都市型・生活型の紛争、近隣紛争が増加し、それらを第三者機関で解決するニーズが高まっている。
② 公調委の現実の運用では既に、相隣関係と言うべき紛争の一部も対象として扱っている(たとえば、マンション内の上下階の騒音)。
③ 1967年(昭和42年)に環境基本法の前身である公害対策基本法が制定され、それを踏襲して本法が1970年(昭和45年)に制定された当時、公害の定義に相当の範囲を要件としたのは、社会性・公共性のあるものを対象とすることで公法的な介入を正当化するためであった。しかしその後の環境問題の広がりを受け、公害対策基本法を廃止して環境基本法が制定され、同法では健全で恵み豊かな環境が人間の健康で文化的な生活に欠くことができないものであることにかんがみて環境の保全が行われるべき旨の基本理念が定められ(環境基本法3条)、より広い視野の環境保全法制が出発した。したがって今日では、相隣関係レベルの環境問題も含め、広く一般的に環境の保全は公法的に対応すべき課題となっていると解される。公調委懇談会においても、制度の射程に疑義を生じさせないためにも公害紛争処理法2条を改正し、環境基本法2条3項にある「相当範囲にわたる」という部分は適用しないとするような対応が法治主義の観点から望ましい、とする意見が存した。
(3) また、本法の対象範囲を媒体ごとに分類した典型7公害に絞ることも、次のとおり、もはや合理性が失われた。
① 現行の「公害」がこれらに限られているのは、法制定時の社会問題であったことや既に規制法が整備されていたからにすぎない。法制定の時点においても、「典型七公害以外の日照等に係る紛争をも紛争処理の対象範囲とするよう速やかに検討すること。」という衆参両院の各委員会による附帯決議が付されていた。その懸念どおり、今では全国の苦情相談件数の統計上、全体の約3分の1がそれ以外の苦情である。
② 1974年(昭和49年)法律第55号民事調停法及び家事審判法の一部を改正する法律(同年10月1日施行)により加えられた民事調停法第33条の3においては、「公害又は日照、通風等の生活上の利益の侵害により生ずる被害に係る紛争に関する調停事件」について特別の管轄を認めており(公害等調停事件)、典型7公害以外の被害についても公害と同列の取扱いをしている例が、既に存在する。
③ 通風、電磁波、光(ひかり)害等、社会の変化に伴い環境に係る新たな紛争類型は絶えず出現しうる。そのような変化に柔軟に対応できる仕組みが望ましい。
新しい環境に係る紛争の中には、人への健康影響について科学的知見の蓄積の少ない分野もある。民事訴訟において、因果関係や加害者の過失を立証することが難しいこのような紛争を本法に基づく制度の対象とすれば、公調委の調査能力の活用や調停条項を工夫して定めること等により、予防原則の観点に立って柔軟な解決策を模索できるといえる。
2 環境に係る被害全般へ対象を拡張
(1) 上述のように「公害」の定義からその要件の一部を削除した被害についても本法の対象に加えることにより、対象範囲の一定の拡大は図れるが、なお、人の健康や生活環境への直接の影響が生じにくい事案については、直ちに対象になるとは言い難い。たとえば、景観破壊、有害性のない残土の放置や区画形質の変更等による自然破壊は、環境が損なわれる事態ではあるが、本法が「公害」およびその類似の事案だけを対象に限ったままでは、取扱いに疑義が生じる。そこで、以下のような環境に係る被害およびそのおそれについても、本法の対象とすべきである。
(2) 対象範囲は、環境に係る被害またはそのおそれのうち、「人間の健康で文化的な生活を害する環境上のおそれがあるもの、または生態系を破壊するおそれがあるもの」という要件で区別することが考えられる。その理由は次のとおりである。
① 紛争の核心が自然破壊等である場合、現行制度ではその司法救済手段が未整備で、充実が求められている。
② 環境基本法3条は、健全な環境が人間の健康で文化的な生活に欠くことができないものであること、及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っている、人類の存続基盤である環境が損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、環境保全を適切に行うよう定めている。
この規定からすれば、公害以外の環境に係る紛争のうち、健康で文化的な生活を害するおそれがあるもの、または生態系を破壊するおそれがあるものについては、本法の対象とすることが環境基本法の要請に沿うものと言える。
③ 公調委は、本法に基づき当事者間の権利義務を審議する司法機関に類似した側面と、公益に資する活動を行う行政機関としての側面との、2つの面を有している。自然環境や生態系の保全は、個々の関係者の私益に留まらず将来世代にもわたる公益であることに照らすと、公益を保護する後者の側面について制度強化することは理に適っている。
たとえば、公調委の原因裁定の手続は、公益侵害が問題となる事案との親和性が高い。同手続は、被害と加害行為との因果関係のみを判断する仕組みであり、個人の権利義務の判断にまで立ち入る必要がないためである。必ずしも「公害紛争処理制度においては権利義務を確定しなければならない」、と考えるべき論理必然性はないといえる。
(3) なお、このような環境に係る被害またはそのおそれにまで紛争解決の対象を拡げた場合、生態系の保全等の公益保護の様相が強い事案においては「誰に申請の権利があるのか」という申請人の適格の問題に直面する。このような事案を解決するためには、民事上の紛争当事者(法26条1項)のみならず、環境保護について専門的かつ長期的な視点を有する団体にも申請を認めることが合理的である。
一定の条件で環境保護団体にいわゆる団体訴権を導入することは国際的潮流であり、日本弁護士連合会も2012年(平成24年)に「環境及び文化財保護のための団体による訴訟等に関する法律案」を公表し、違法な開発行為等に対し一定の団体に差止権等を付与する特則を定めるべきであると主張した。近畿弁護士会連合会は、公害紛争処理法の改正として同様に提言している。日本でも既に消費者保護の分野では、適格消費者団体による消費者団体訴訟が2006年(平成18年)に導入され、広く市民の権利擁護に活用されている。
本法に基づく紛争解決を目指す際に、保護対象に対する特別の利害を持つ個人や団体が存在する事案については、それらの者に紛争解決の申請適格が認められ得る。しかし、より集団的・社会的利益の保護が求められる事案においては個々の利益侵害を観念し難い場合が考えられる。その手当として、一定の環境保護団体に調停等の申請権限を付与する特別の手続を設けることが必要となろう。
第2 提言2について
1 名称変更がもたらし得る利用促進効果
(1) 2013年(平成25年)の全国の公害苦情受付件数は8万件弱にも及んだが、公害等調整委員会及び各都道府県の公害審査会(以下「公調委等」という。)の利用は低調であり、その理由の一つに、名称から受ける印象の問題があると考えられる。
利用者の視点に立った場合、今日、環境に係る被害を「公害」と認識する市民は少数派で、「環境問題」や「環境上のトラブル」等との名称で捉えることが一般的であろう。そのため、法の用語も「公害紛争」に代えて「環境紛争」に置き換えた方が身近な手続であると認識され、利用促進効果が期待できる。
かつてピアノ騒音殺人事件が世間を震撼させたが(1978年(昭和53年)にピアノ騒音が理由で集合住宅内の母子3名が殺害された事件)、最近でも騒音を原因とする殺人事件が頻発するなど(例えば昨年9月1日から10日の間には、騒音を原因とする殺人ないし殺人未遂事件が3件も報道されている。)、紛争解決手段が利用されずに悲惨な結末に至る事例が未だに絶えない。もし当事者が、使いやすい環境紛争解決手段があることを知っていたら、この種の事件は防止できたかもしれず、認知度の低さは市民にとっての悲劇といえる。
また現行の「処理」という名称には、行政機関が"お上として"行う固い事務処理のイメージが付きまとうが、「解決」であれば、柔軟な調整機関という印象が鮮明になるため、市民が自己の問題解決に利用できるとの認識につながり、利用促進効果が期待できる。
(2) また、名称変更がなされれば、各種媒体に「環境紛争解決法」「環境紛争調整委員会」の名が載り、その周知効果による利用促進も期待できるだろう。
2 名称と実情等との乖離
第1で述べたとおり、現在の本法の「公害」の定義は、今日の環境上の諸問題を取り扱う枠組みとしては狭きに失し、既に柔軟な運用がなされている。そのような実情がある上に、本法の対象を、環境に係る被害やそのおそれ全般に拡張する以上、法令や機関の名称は、当然、それら実情及び内容にふさわしいものに変更されるのが自然である。
3 利用増加による新たな環境保全規範醸成への期待
法規範を発展させるためには、成文法を改正する手法の外に、判例の蓄積を増やすという手法がある。本名称変更の提案は、形式的な変更に過ぎないように見えるがその実、後者の効果をも期するものである。
すなわち、市民生活に身近な名称へと法令名や機関名を変更することにより、利用件数が増え多数の判断が公調委等でなされると予想される。その成果として、環境保全のための新たな規範の生成が加速されることが期待できる。
第3 おわりに
国際的な文脈から捉えた場合、公調委等の機能やこれまでの慣行に照らすと、本組織は、広義の意味での「環境裁判所」に相当する機関である。環境保全のための公的機関の中心として、取り扱い範囲を現代の諸問題にも対応できるよう拡大して、調停や裁定手続等の機能を強化し、その実効性を向上させることにより、今日の環境問題をより幅広く効果的に解決できるよう、改善していくことが望まれる。