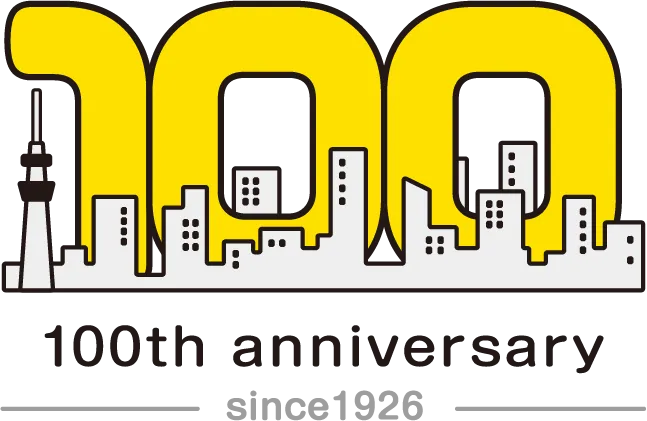成年後見制度の見直しについて
1 見直しの背景にある社会状況 現行の成年後見制度(以下「現行制度」という。)は、2000年度に始まりましたが、我が国の令和4年10月1日現在の65歳以上の人口が3624万人(総人口に占める割合が29.0%)に達し、しかも、同年末時点の認知症の高齢者が約600万人と推計され、本来、成年後見制度利用の需要が高い筈であるのに、成年後見制度の利用者は、同年度末時点で約245,200人にとどまっており(最高裁判所事件統計)、利用が低調といわざるを得ない社会状況があります。
2 見直しに向けての内外機関の動き このような社会状況から、内閣は、同年3月、対象期間を同年度ないし令和8年度とする「第二期成年後見制度利用促進基本計画」(国は、障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活の継続や本人の地域社会への参加等のノーマライゼーションの理念を十分考慮した上で、専門家会議における指摘も踏まえて、成年後見人の更新制導入等の現行制度の見直しに向けた検討を行うというもの)を閣議決定しました。
また、障がい者の権利に関する条約の第1回対日審査に関する障がい者権利委員会は、同年10月7日、「意思決定を代行する制度を廃止する観点から、すべての障害者が、法律の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正すること」という総括所見を出しました。
そこで、法務省民事局は、令和6年1月、「成年後見制度の見直しに向けた検討」の中で、現行制度に対する指摘としては、㈠ 主に、(1) この制度の利用動機の課題、例えば遺産分割手続の当事者の判断能力不足の補充が、同手続の終了により解消されても、被後見人本人の判断能力が回復しない限り同制度の利用を止めることができないこと、(2) 成年後見人に被後見人本人の行為について包括的な取消権、代理権があり、本人の自己決定が必要以上に制限される場合があること、(3) 被後見人本人の状況に応じた成年後見人等の交代が実現しないために、被後見人がそのニーズに合った保護を受けられないことがあること及び(4) 任意後見契約の本人の判断能力が低下した後も適切な時機に任意後見監督人の選任申立てができないことの見直し、㈡ その他に、(1) 法定後見制度の利便性の観点から類型の一本化を含む見直し及び(2) 利用者及び受任者の双方から、各家庭裁判所が個別に定めていて明確な基準がなく、利用者側からは経済的負担の重さにつき、受任者側からは事務負担の重さとの均衡につき、それぞれ不満があるとされており、成年後見人等の報酬の在り方を検討する必要があると整理しました。
3 法制審議会に対する諮問 そして、法務大臣は、同年2月15日、法務省民事局の上記2の整理を承けて、法制審議会に対し、諮問第126号により、「成年後見制度の見直しの要綱を示されたい。」との諮問をしました。
4 法制審議会の検討手順 以上の経緯から、法制審議会は、令和8年度までに、以下の各テーマについて議論して改正要綱案をまとめた上で、民法などの関連法規の改正を可能とすることを目指しています。
㈠ 主要テーマ (1) 現行制度における開始、終了等に関するルールのあり方を見直し、一定の期間制や、具体的な利用の必要性を考慮して開始し、必要性がなくなれば終了する仕組みとすること、(2) 同制度における取消権、代理人に関するルールの在り方を見直し、本人の同意を要件とする仕組みや、本人にとって必要な範囲に限定して付与する仕組みとすること、(3) 同制度における成年後見人等の交代に関するルールの在り方を見直し、本人の状況に合わせて成年後見人等の交代を可能とするなど適切な保護を受けることができる仕組みとすること及び(4) 任意後見制度における適切な時機の監督人選任を確保するための、任意後見受任者に任意後見監督人選任の申立てを義務付ける仕組みや申立権者の範囲を見直すこと
㈡ その他のテーマ (1) 現行制度の3類型の利便性の観点からの一本化を含む見直し及び(2) 成年後見人等についての明確な報酬基準の策定
5 当コラムでは、法制審議会の改正要綱案作成の動向について、節目毎にフォローしますので、ご注目下さい。