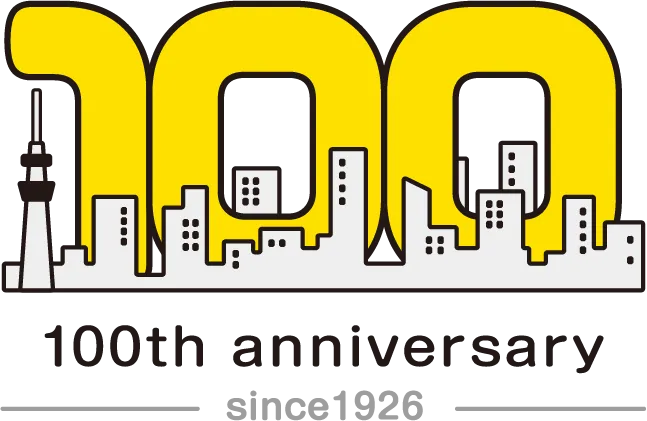特定商取引法及び特定商品預託法における書面交付義務の拙速な電子化に反対し、電子商取引における消費者被害に対する実効性ある規制を求める会長声明
2021年(令和3年)3月3日
第二東京弁護士会会長 岡田 理樹
20(声)第10号
1 政府は、特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)及び特定商品等の預託等取引契約に関する法律(以下「預託法」という。)に定められた書面交付義務について、消費者が承諾した場合に電磁的方法による書面交付(以下「電子化」という。)を可能とする内容の法改正を進めようとしている。
しかし、オンライン契約と対面契約とを区別せず、「デジタル社会の推進、オンライン取引の推進」の名の下に、特商法や預託法で交付を義務づけられている書面を安易に電子化することは、これまで書面交付が果たしてきた消費者保護機能に重大な悪影響を与えることが強く懸念されることから、当会は、この法改正を拙速に進めることに反対する。
2 そもそも特商法や預託法によって交付を義務づけられる書面は、消費者自身が、取引を勧誘された後に、交付された書面から契約内容を確認してその契約を維持するか解消するかを冷静に判断できるようにするためのものであるとともに、家族やケースワーカー等の消費者の周囲にいる者が不審な取引に気付く機会を与えるという、消費者保護上重要な機能を有しているものである。また、電磁的方法により交付された書面は、ワンクリックで消去されてしまうという特性があり、記録という意味でも書面交付に劣る。
かかる書面交付が消費者保護に果たしてきたさまざまな機能を電磁的方法で十分に果たせるかどうかについては慎重な検討が必要である。
3 また、特商法や預託法が規制対象としている取引では、不意打ち的な勧誘や利益ばかりを強調した勧誘等により消費者の契約締結の意思形成過程自体が歪められることが多いのだから、電子化の要件を消費者の承諾にかからせることは無意味である。一般のネット取引などの場合でさえ、高齢者や若年者を含む多くの者が契約内容を十分確認することなく同意欄にチェックをし、思ってもいない契約に至る被害が多発しているのは顕著な事実である。特商法や預託法が対象とする、より消費者被害が生じやすい取引について、消費者の同意により書面による交付を免れさせるのは、これまで積み重ねられてきた消費者保護を後退させるものであり、有害ですらある。
4 さらに、今回の法改正では、特商法の7つの取引類型のうち通信販売を除く6つの取引類型と、預託法に基づく特定商品等の預託等取引につき一括して電子化を進めようとしているが、オンライン契約と対面契約とを区別することもせず、各取引類型による被害の実情や危険性が何ら踏まえられていない。
電子化を導入すべき必要性の点でも、例えば、訪問販売を中心とする対面販売等、その場で直接書面を交付することに支障はなく、電子化を認めるべき必要性自体が乏しい取引類型もある。それにもかかわらず一括して電子化を進めることに合理性は見出せない。
特商法や預託法で規制対象とされている取引には様々な類型があり、オンライン契約から対面契約までさまざまであって、その類型ごとの被害の実情や危険性に応じた規制がなされてきた。このような類型ごとの実情、必要性や危険性が何ら検討されないまま、「デジタル社会の推進、オンライン取引の推進」という名の下に、十分な検討なく法改正が強行されてしまえば、過去に社会問題となった消費者被害を繰り返す結果を招きかねず、かえってデジタル社会の推進に逆行することにもなりかねない。
5 以上のとおり、特商法及び預託法における書面交付義務の電子化は、消費者保護に重大な悪影響を与えることが懸念されるものである。したがって、これまで積み重ねられてきた消費者被害事例などに鑑み、まずは書面の電子化の必要性とそれによる消費者被害発生の危険性を取引類型毎に慎重に検討し、消費者被害について書面交付と同程度の実効性のある規制を導入することを検討すべきである。そのような検討なく拙速に電子化を進めることには、当会は、強く反対する。
特定商取引法及び特定商品預託法における書面交付義務の拙速な電子化に反対し、電子商取引における消費者被害に対する実効性ある規制を求める会長声明(PDF)