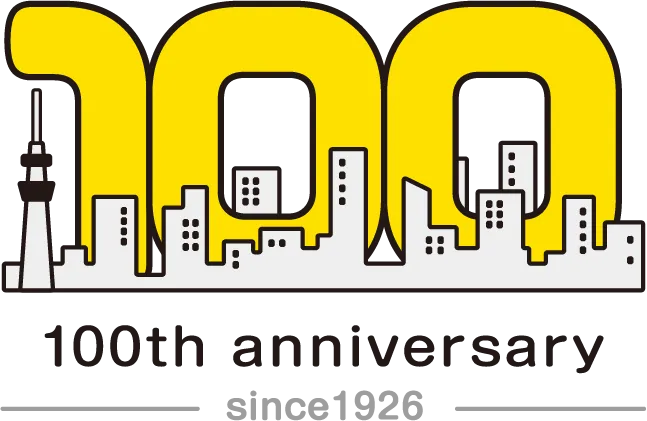女性のための生活、仕事、子育て、なんでも相談会相談データ集計及び分析結果に基づく政策提言
2021年 ( 令和3年)9月
第二東京弁護士会
はじめに
当会は、日本国内における新型コロナウイルス感染症(COVID-19。以下「コロナ感染症」という。)の感染拡大を受けて、2020年(令和2年)3月3日に災害対策本部を設置し、同月10日に「新型コロナウイルスの影響を受ける皆様の支援に関する会長声明」を発出するとともに、コロナ感染症に関連する悩みに広く対応するために、現在に至るまで電話相談及びオンラインによる面談相談(いずれも無料)を実施し、また、災害時ADRを運用している。
しかし、今なおコロナ感染症のまん延が続いており、収束の見通しは立っていない。これに伴う経済活動の停滞は、特に女性、子ども及び外国人といった経済的な弱者に厳しい生活を強いる結果となっている。このような方の中には、弁護士に相談をすること自体に考えが至らない方も多い。とりわけ女性は、相談ニーズが高いものの、家庭の状況等の制約のために相談を躊躇するなどの事情から弁護士へのアクセスが困難な方が多いことなどが指摘されている。
そこで、女性等が相談をしやすい場所を弁護士が積極的に提供していく必要があると考え、当会は、相談が必要な方々に"届く"相談活動を展開することを目的として、本年4月にアウトリーチ相談PTを立ち上げた。また相談困難者に対するサポートや生活相談を先進的に行っている民間団体と連携協力をしていくことにした。
そして、「女性による女性のための相談会実行委員会」(以下「実行委員会」という。)の共催と東京都の後援を得て、対象者を女性に限定した「女性のための生活、仕事、子育て、なんでも相談会」(以下「本女性相談会」という。)を企画し、本年7月10日(土曜日)及び11日(日曜日)に実施した。
その結果は、「相談データ集計及び分析結果」(以下「分析結果」という。)にまとめたとおりである。
当会は、以上のデータ集計及び分析結果を踏まえ、以下のとおり、政策提言を行うものである。
政策提言
1 女性の困窮状態に対する大規模な全国調査の実施
国及び地方自治体は、コロナ禍における女性の貧困やDV等の現状を把握し て政策に反映させるため、大規模な調査を早急に実施すべきである。
2 複合的な悩みに対応できる相談体制の構築と支援
国及び東京都は、法律相談に限らず、複合的な悩みに対応できる相談体制の構築を早急に検討し、実施すべきである。
3 権利としての生活保護法の適切な実施に向けた施策
生活保護の受給要件を充足しているにもかかわらず、申請を躊躇せざるを得ない人が多数存在する現状が改めて明らかになった。国は、生存権を実効あらしめるための生活保護制度の運用実態を改めるとともに、憲法の権利である生存権保障に対する誤った考え方に対する適正な広報周知を徹底するとともに、生活保護法を改正して、法律の名称の「生活保護法」から「生活保障法」への変更、権利性の明確化、水際作戦を不可能にする制度的保障として法律で申請権侵害を禁止すること、生活保護(生活保障)給付の全国及び地域別の捕捉率の定期的な調査・向上の義務付けなどを図るべきである。また、依然として扶養照会が生活保護申請の障害となっていることから、扶養照会自体を原則行わないこととする旨の運用を行うべきである。
4 生活困窮者に対する各種支援制度の延長と周知
生活困窮者の生活支援のための制度である緊急小口資金等特例貸付期間の延長、住宅確保給付金支給の特例の延長、雇用調整助成金の特例措置については、コロナ禍が収束するまで延長するとともに、広報活動を通じてその制度の周知を図るべきである。
5 住まいの実態調査
東京都は、都内のシェアハウス等生活困窮者の住まいの実態調査を早急に行い、生活困窮に陥っている女性に対して、支援体制を早急に構築すべきである。
6 DVやモラハラ、虐待、性暴力被害への支援体制の構築
国及び地方自治体は、DV、モラハラ、虐待などコロナ禍において浮き彫りとなった家庭関係における女性の悩みに応えるべく、専門相談体制の構築、充実、専門相談員の育成、専門相談機関への支援など総合的な対策を早急に行うべきである。
7 食糧支援の充実
国は、政府備蓄米を子ども食堂や各相談会、民間団体等への無償交付を拡充するとともに、更新期が到来した災害備蓄食品の提供を早急に行うべきである。
提言の理由
1 女性の困窮状態に対する大規模な全国調査の実施について
本女性相談会には、わずか2日間の間に合計123件の相談者が参加した。東京都のみならず、神奈川県、埼玉県、千葉県など関東近県から参加した方も相当数に上った。相談者の年齢層は、30代(18%)、40代(31%)、50代(24%)が中心であったが、60代以上の高年齢層や20代以下の若年層も一定程度参加がみられた。職業別では、正社員、非正規社員の他、主婦、無職など多岐にわたっていた。このように、コロナ禍において幅広い層の女性がさまざまな困難を抱えて相談を切実に必要としている実態が明らかになった。
こうしたニーズに今後応えていくためには、現状の把握が必要である。今回の企画で明らかになった相談ニーズは一端に過ぎない。3月に相談会を実施した実行委員会は、2021年6月4日に「女性に対する政策に関する要望」(以下「要望」という。)を発表し、その第1項において、女性の貧困等の状況を把握するために大規模な全国調査の実施を要求している。
内閣府の「コロナ下の女性への影響と課題に関する研究会報告書」では、労働力調査の個票分析に基づいた報告がなされるなどしているものの、女性の貧困状態を具体的に把握する目的での調査まで実施されているとは言い難い現状にある。各地で実施されている相談会などの情報の集約や生の声を集めるなどして、リアルな調査を実施する必要がある。
そこで、当会は、上記の本女性相談会の分析結果を踏まえ、国及び地方自治体に対して、コロナ禍における女性の貧困状態とニーズを正確に把握するために、全国規模の大規模な調査を実施するよう要望する。
2 複合的な悩みに対応できる相談体制の構築と支援
本女性相談会の特徴として、あえて「法律相談」ではなく、「何でも相談」と銘打ち、実行委員会との共催としたことで、通常の法律相談の枠に入らない段階の相談(例えば、紛争の相手方が必ずしも存在しない本人の生活環境に関する悩み、相手方がいる場合でも紛争には至っていない状況での悩み、法的手段の選択のみでは解決には至らないと思われる悩みなど)が多数寄せられた。これらは、相談内容の分類において、必ずしも明確な切り分けができない「その他」の相談が最も多かったことに表れている(76件)。
また、それとともに、生活に関する悩み、仕事や求職に関する悩み、子育てや健康に関する悩みなど、一人の相談者に多くの問題・課題が集積している実態が明らかとなった。こうした複合的な悩みを抱えている女性は、様々な困難に直面しているため、誰に相談し、どのように解決していいかわからないと訴えることが多く、また、一人で悩みを抱え、誰にも相談できないでいる人も多かった。
そして、相談に応じる側においても相談分野を限定することなく、相談者の悩みを受け止める姿勢を示すことで、相談者が一定の満足を得たり、解決への糸口を見出しうることを実感した。本女性相談会では、相談者に感想を書いていただき、それを壁に貼って閲覧できるようにした。通称「レノンウォール」というものである。そこには、「勇気を出してきました。まわりにいえない話を誰かに聞いてもらえてよかったです。」「一人で悩んでいたので話ができて良かったです。」「ずっと自分がおかしいのかもしれないと思い続け、相談することを躊躇していました。相談してみると、『それはひどい』「それは犯罪です」とおっしゃってくださって安心しました。」「人に相談しにくいことが相談できてよかったです。」「自分がつらい状態なんだと改めて知ることができました。無理せず相談しようと思います。」などの感想が寄せられた。
なお、特定の相談分野について付言すると、本女性相談会では、例えば、労働問題に関する相談が一定数よせられた。その具体的な相談内容としては、本人の置かれた就労環境における就労条件の不遇や、嫌がらせ、パワハラなどの人間関係の悩みが生じているものであり、それ故に充実感ややりがいが得られないというものが挙げられる。派遣切りを含め解雇の被害を受ける場合でも、法的に争うことを望まず、むしろ、収入や生活の安定を求めて新たな職探しをするものの、再就職が叶わないという相談者も複数いた。労働問題については、各地方自治体や弁護士会、民間団体、労働組合など、多くの機関による専門性の高い相談窓口が設けられている。しかし、本女性相談会に来場した女性の多くは、前述のような相談窓口は敷居が高いと感じていたということであった。
また、親族・家庭問題という分野についても、離婚調停・訴訟、養育費調停や調停内容に基づく強制執行など、法的紛争性の高い相談が一定数存在したが、他方で、離婚を決断するまでには至らない状況での夫の無理解や、子育て方針の違い等の婚姻生活上の悩みがあったり、夫婦関係以外でも、同居する親もしくは子との間でのいじめ被害の悩みがあったりするなどした。これらは、弁護士が法律相談として対応するだけでは解決の方向性を示すことが難しい相談があった。
以上のとおり、相談内容は一つのテーマにとどまらず、複合的なケースであることが多く、気軽にワンストップで対応できる相談体制が重要であることがわかる。本女性相談会は、臨床心理士や看護師という専門職の他、女性相談の経験豊富な相談員を擁する実行委員会と弁護士がペアを組んで相談に応じるという体制をとったこともあり、複合的な問題を抱えた相談者が必要としている相談に一定程度応えることができたと考えている。
そこで、当会は、国及び地方公共団体に対して、複合的な事案に対応するための具体的な相談窓口を弁護士会、関係機関・民間団体と協力して設置するとともに、広報・周知の徹底、専門相談員の育成・確保・配置、財政支出を行うよう要請する。
3 権利としての生活保護法の適切な実施に向けた施策
生活保護制度は、憲法25条で保障された生存権の具体化である。しかし、現実には、福祉事務所によるいわゆる「水際作戦」は、依然として行われており、申請書を渡さない、「相談ですね」と言って申請をさせないといった運用があることは、実行委員会の報告からも確認されている。3月の「女性による女性のための相談会」においても、同様のケースが多数あったと報告されており、本女性相談会においても、所持金、収入がなく、生活保護を受給することが可能であるにもかかわらず、保護の申請を決断できない相談者が相当数来場された。
厚生労働省は「生活保護は権利です。」とホームページやツイッターで周知に努めているものの、まだまだ国民の間では、生活保護受給に対する心理的ハードルが高い。最近では、芸能人のYouTubeにおけるホームレスや生活保護受給者を否定する言動が広く社会から批判される事態となった。
そこで、国や地方公共団体は、本女性相談会に参加されたような生活に困っている方が躊躇なく、生活保護を申請できるための法改正及び運用を早急に検討すべきである。
4 生活困窮者に対する各種支援制度の延長と周知
本女性相談会の相談の中では、やはり生活に関する相談が27.6%と最も多く、収入の減少に伴う生活苦や住まいについても切実な相談が寄せられた。労働問題では、解雇、休業手当の相談も相当数あり、失業、障害等さまざまな理由で生活に困窮している女性が多数存在することが明らかとなった。そして、それらについては、コロナ禍に伴う就労環境の悪化を背景とするものが多かった。
この点を踏まえ、「利用したことのある公的支援制度」を質問したところ、生活保護が18人、特定定額給付金が17人で最も回答が多かったが、緊急小口資金、住戸確保給付金、総合支援資金等を利用したと回答した方は極めて少なかった。「分析結果」の「特徴的相談事例」のイ、ウのように制度自体を知りたいという相談がかなり見られたように、制度の周知が十分になされておらず、制度が生かされていない。
解雇や雇止め等によって失職したという相談者やハラスメント等による職場環境の悪化から退職を余儀なくされた相談者も相当数いたが、休業手当を受給したことがあるという回答はなく、また、失業給付を受給したことがあると答えた相談者はわずかに3名であった。
日本では、失業者に対する失業給付の受給者の割合が低いことが指摘されてきたが、その実情を裏付ける形となっている。
以上のことから、コロナ禍においてその影響を強く受けている女性の生活困窮者を支援する各種制度について、コロナ禍が収束するまでの間、各制度の延長を図るとともに、各制度の徹底した周知をすべきである。
5 住まいの実態調査
本女性相談会の広報宣伝の過程で、新宿、上野、秋葉原、錦糸町などのシェアハウスを訪問し、チラシの配布を行った。シェアハウスは、「女性専用」「格安できれいな部屋」などというネット広告などで集客している。しかしながら、実際に訪問してみると、住居が非常に分かりにくい場所にあったり、郵便受けがなかったり、あるいは1つしかなかったり、外から見えないように目張りをしてあるなど劣悪な住環境に多くの女性が住んでいることがうかがわれた。恐らくはワクチン接種券など重要な書類も届いていない可能性が高い。
こうしたシェアハウスについては、行政の指導・監督が必要であるところ、まずは東京都の責任において実態調査を行い、必要な支援を行う措置を早急に講じる必要がある。
6 DVやモラハラ、虐待、性暴力被害への支援体制の構築
本女性相談会では、「親族・家族関係」に分類した相談が25.2%にのぼり、「その他」に分類したものにも相当数、親族、家族関係の悩みが含まれており、女性の悩みの多くを占めている。「特徴的相談事例」ウ、エのようにコロナ禍において家庭環境が悪化し、それを機にDVやモラハラ、虐待の事例が増加しているといえる。
本女性相談会では、関係機関への相談を促すなどの助言等を行い、また弁護士が継続的に相談に応じることとしたが、家族関係の悩みは相談がしにくい実情にあり、女性が相談しやすい仕組みを積極的に取らないと相談にまで至らないことが多い。
国や都は、こうした女性が多数いることを踏まえ、女性が相談しやすい体制を構築する必要がある。そのためには、提言2で述べた間口の広い「なんでも相談」窓口を設けるとともに、女性やDV相談の特性を踏まえた専門性のある相談員を育成して配置すること、実績のある専門相談機関を支援し連携すること等によって総合的な対策を早急に行うべきである。
7 食糧支援の充実
本女性相談会では、マルシェを設置し、米、野菜、生理用品等の生活用品の配布を行い、相談者の多くに喜ばれた。レノンウォールにも、「特に生活用品が沢山いただいて非常にありがたいです。」「お野菜もいただきありがとうございました。」「お米と食料たすかります。」など感謝の言葉が寄せられた。実際、空腹を感じている相談者も少なからずいた。
コロナ禍の中で、本格的な支援制度につながるまでの間の緊急支援の一つとして、食料品や生活用品の配布は重要であり、国はこうした民間団体に対して政府備蓄米や災害備蓄品などを積極的に提供するとともに継続的に支援する仕組み作りを行っていくべきである。
女性のための生活、仕事、子育て、なんでも相談会相談データ集計及び分析結果に基づく政策提言(PDF)
女性のための生活、仕事、子育て、なんでも相談会相談データ集計及び分析結果(PDF)