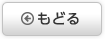民法の成年年齢引下げにあたり、消費者被害防止のための措置を改めて求める会長声明
2022年(令和4年)4月1日
第二東京弁護士会 会長 菅沼友子
22(声)第1号
本日、「民法の一部を改正する法律」(平成30年法律第59号。以下「本法律」という)が施行された。本法律は、1896年に民法が制定されて以来120年以上にわたって20歳とされてきた成年年齢を18歳に引き下げるという、国民の生活に大きな影響を与える歴史的なものである。
民法の成年年齢引下げについては、既に施行されている選挙年齢の引下げとは制度の趣旨が異なり、より多くの問題があること、特に、18歳、19歳の若年者が未成年者取消権(民法5条2項)を喪失することによる消費者被害の拡大への懸念が指摘されてきた。未成年者取消権は、未成年者が違法又は不当な契約を締結するリスクを回避する「防波堤」であり、かつ、未成年者を勧誘しようとする悪質事業者に対する「抑止力」としての機能を有しているところ、成年年齢の引下げによって18歳、19歳の若年者はその保護を受けられなくなるのである。
そのため、本法律の成立にあたって採択された附帯決議(参議院法務委員会)では、①本法律成立後2年以内に、いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権の創設など、若年者の消費者被害の防止・救済のために必要な法整備を行うこと、②高等学校・大学等での実践的な消費者教育の実施、③18歳、19歳の若年者に理解されやすい形での周知徹底、など十項目にわたり必要な措置を講ずることを政府に求めた。当会も、会長声明(18(声)第7号、21(声)第6号)において、上記附帯決議に記載された各措置の確実な実現を求め、それが出来ない場合には施行延期の検討を求めてきた。
しかしながら、本法律の成立から3年10ヶ月という準備期間があったにも関わらず、つけ込み型不当勧誘取消権は未だ創設されず(本年2月1日に消費者庁が発表した消費者契約法改正骨子案にもこの点は明記されなかった)、若年者の消費者被害の防止・救済のための効果的な法整備もなされていない。消費者教育についても、若年者一人ひとりが未成年者取消権を喪失することのリスクを十分に理解するに至っているとは言い難い状況にある。このままでは懸念された若年者の消費者被害拡大が現実のものとなりかねない。
「新成人たちよ、未来をつくれ。」
これは新成人に向けた政府広報のメッセージである。新成人が未来に向けて活躍するためにも、附帯決議で求められた措置の実施が不可欠である。
当会は、政府に対し、上記附帯決議に記載されたような若年者の消費者被害の防止・救済のために必要な法整備等の措置を早急に実現することを改めて求める。