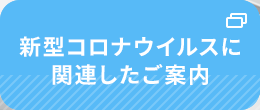民法(債権法)改正の最重要ポイント(前編)
前編 全3回

1、はじめに
平成21年9月から5年間余りにわたって法制審議会民法部会の幹事を務めていた関係で、改正民法の立法過程に深く関与しておりました。本日は、民法改正の中でも実務上非常に関心が高いと思われる点をピックアップして、お話しさせていただきます。
民法(債権法)の改正は非常に多岐にわたっておりますが、重要なところは真っ先にご理解いただく必要があるだろうということで、6つの項目を取り上げました。ただ、本日お話ができない部分でも理解しておかなければならない改正点が相当程度ございます。この講義を1つのきっかけにして、それぞれ先生方において施行までには遅くとも理解をしていただく必要がありますし、何よりも条文を読んでいただきたいと思います。
条文だけを読んでいくと、なかなかスッと頭に入らない部分ももちろんあるかと思いますが、逆に条文を読まずに趣旨だけを理解しても、理解が不十分になるのではないかと思います。やはり原点である条文に当たって、その条文の文言が何を言わんとしているのかということを直接感じ取っていただければと思います。本日は時間の許す範囲内で、少し条文の表現にも目を配りながらお話をさせていただきたいと思っております。
1、消滅時効
1、原則的な時効期間と起算点
(1)主観的起算点の導入(改正法166条1項)
「権利を行使することができることを知った時」から5年(1号)、又は「権利を行使することができる時」から10年(2号)
(2) 短期消滅時効(1年~ 3年、5年)の廃止
(3) 商事時効(5年)の廃止
消滅時効期間につきましては、従来「権利を行使することができる時」から10年という現行法の規律がありますが、改正法ではその規律と、「権利を行使することができることを知った時」から5年という起算点と期間を併存させて、そのどちらか早い方の到達時に時効が成立するという規律に改めました。
消滅時効期間を最終的にどのような規律にするかについては、そもそも時効制度をどう促えるかというところからの議論がありましたが、本日はその経緯を説明する時間がございません。従来のような起算点、すなわち「権利を行使することができる時」というものを客観的起算点と呼び、「権利を行使することができることを知った時」というのを主観的起算点と呼んでおりますが、この主観的起算点から5年という期間が加わったことが新しい点になります。
この主観的起算点というものは、現行法にも724条に不法行為債権の消滅時効について、「損害及び加害者を知った時」という主観的起算点が既に用いられておりました。今後は、債権一般について主観的起算点から5年という時効期間が1つの基準になります。
では、その主観的起算点から5年という時効期間と、客観的起算点から10年という時効期間がどのような関係になるのかということなのですが、通常の契約上の債権を想定しますと、契約を締結する段階でその契約に基づいて発生する債権の弁済期が来ることによって請求ができるということを、契約当事者は当然知っていることになりますので、通常の契約上の債権を想定すれば、この客観的起算点と主観的起算点は一致するだろうと考えられます。その結果、そこから5年という期間で時効が完成しますので、従来、一般の民事債権であれば10年という時効期間だったものが5年に短縮することになろうかと思います。
もっともご案内のとおり、商事債権については商法の規定によって5年という時効期間が定められておりましたので、ビジネス上発生する債権を想定すれば、変わらないことになります。
そのようなこともあって、商事債権の5年という商法の規定は削除されて、商事債権か否かを問わずに民法の規律が適用されるわけです。ただ主観的起算点は、「権利を行使することができることを知った」から5年ですから、多くの場合は客観的起算点と一致すると申し上げましたが、常に一致するわけではなくて、場合によっては起算点が遅くなる場合があります。
そうすると、その意味では今の商事時効として規定されている5年の時効期間よりも、6 年、7年と延びていく可能性はあります。例えばどのような場合かというと、現行法でいう瑕疵担保責任のようなものです。この瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権というのは、契約を結んだ時点で、瑕疵があれば損害賠償請求ということは認識しますが、最初から瑕疵があるということを認識しているわけではないので、瑕疵がある目的物の引渡後初めて権利を行使し得ることを知るわけです。実際に、瑕疵、不具合があることを知った時点が主観的起算点になるという意味で、契約成立時より主観的起算点が後ろにずれるということになります。
そのようなことをご理解いただいて、他方で今申し上げた商事債権の5年という制度がなくなるということと、現行民法の1年、2年、3 年、5年という職業分類的な債権の短期消滅時効の規定が、ばっさりとなくなるということです。
以上を原則的な時効期間と起算点としたのですが、そのことによってだいぶシンプルに時効制度は整理されました。シンプルにするということも1つの目的として改正されたわけですが、しかし、どうしても特則をいくつか設けるべき場面があるということで、次に述べるような特則の規定も設けられております。
2、時効期間と起算点等の特則
(1)定期金債権(改正法168条1項)
(支分権たる)「各債権を行使することができることを知った時」から10年、又は(支分権たる)「各債権を行使することができる時」から20年
その1つ目は、定期金債権といわれるもので、これは実務上、余りお目に掛からないと思いますが、定期金債権についてはその支分権である「各債権を行使することができることを知った時」から10年、又は「各債権を行使することができる時」から20年という形で、ここは通常の債権が5年、10年という期間のところを10年、20年と延ばしておりますが、支分権を基準にしてそのような期間が経過すると、元になっている基本的な権利そのものが時効消滅するということであります。
(2)不法行為による損害賠償請求権
(改正法724条)
不法行為から20年の経過による権利の消滅についても、「時効によって消滅する」
⇒ 時効障害事由、信義則違反・権利濫用の主張の可能性
○ 施行時において不法行為の時から20 年を経過していない債権について適用(改正法附則35条1項)
より重要なのは、(2)の不法行為による損害賠償請求権の時効期間です。現行法にもある特則ですが、不法行為の時から20年、あるいは先ほど指摘した「損害及び加害者を知った時」から3年という規律が今でもあります。では何が変わったのかというと、不法行為の時から20年という期間は、大審院以来の判例で除斥期間であると解釈されておりました。
条文を見る限り、20年経過したときも同様とするということで、むしろ素直な文言からは、これも時効期間のように読める文言にはなっておりますが、解釈上は、これは除斥期間であると解釈されておりました。それをやはり時効期間とすべきだということで、期間の20年というのは変わらないのですが、その性質が除斥期間ではなく時効期間であることが明記されました。そのことによって、この後説明する時効障害事由の適用があるとか、あるいは信義則違反や権利濫用の抗弁の対象になり得るという点が具体的な違いとして表れるだろうと思います。
その経過措置の関係で注記をしておきました。経過措置一般に関して言えば、新しい法律が施行される2020年4月1日以降に発生した債権については新しい法律が適用されるというのが原則なのですが、いくつか例外的にもう少し前倒しで適用されるような規律があります。
ここもその意味では例外的な経過措置になっておりますが、「不法行為の時から20年」というこの規律については、施行時にまだ20年経過していなければ、債権の成立自体は施行日以前から成立している債権についても適用されるということになっております。
もともと不法行為から20年という非常に長い時効期間を定めているのは、被害者救済的な観点からですが、そういった趣旨に鑑みて、新しい法律が施行日以降に発生したものだけに適用されると、その効果が実際に生かされるのが先になってしまうということで、既存の債権にも適用されるというように前倒ししております。
(3) 生命・身体の侵害に対する損害賠償請求権
(改正法724条の2・167条)
損害及び加害者を知った時から5年(不法行為債権)
権利を行使することができる時から20年(契約債権)
⇒ 債務不履行・不法行為ともに、主観的起算点から5年・客観的起算点から20年と一致
○ 施行時において損害及び加害者を知っていた時から3年を経過していない債権について適用(改正法附則35 条2項)
生命・身体の侵害に対する損害賠償請求権に対する時効期間の特則というのは、全く新しい制度です。生命・身体の侵害に対する損害賠償請求権には、不法行為構成で不法行為に基づく損害賠償請求権と、何らかの契約に基づく契約上の債権とが考えられます。例えば労災や医療過誤のようなものを想定すればよろしいかと思いますが、不法行為で構成することもできるし、契約上の債務不履行、安全配慮義務違反などという構成もできるということです。
どちらであってもこれは同じ社会事象として発生するものですので、同様の規律を設けた方がいいということもあって、不法行為債権に関して言えば、「損害及び加害者を知った時」から、通常は3年であるところを5年に延ばすという特則を設けておりますし、他方、契約上の債権については権利を行使することができる時という客観的起算点から、10年のところを20年と、それぞれ時効期間を延ばしております。
その結果、不法行為構成であれ契約責任構成であれ、主観的起算点から5年、客観的起算点から20年という通常債権よりも長い時効期間になっております。これは生命・身体というような保護法益の重要性に着目して、被害者救済の観点から期間を延ばしているということですが、法律構成のいかんにかかわらず同じ期間になるということです。
ここでも経過措置として特則を設けておりまして、損害及び加害者を知ってから、施行の時点でまだ3年たっていないものについては、施行前に発生している債権であっても適用されるということになっております。
3、時効障害事由の再編
時効の中断・停止→更新・完成猶予に置き換えた上で、両者の関係を整理
→権利行使事由=完成猶予(「裁判上の催告」の考え方を反映)
権利確証事由=更新
従来、時効の中断や停止と言っていた時効障害事由についてもある程度合理的に整理をして、時効の進行を止めるべきときには止めようという発想で、見直しがなされております。まず言葉の問題として、「中断」あるいは「停止」と言っていたものを、「中断」の方は時効の「更新」という言葉に改めましたし、「停止」の方は時効の「完成猶予」と表現を改めました。これは言葉の問題として、効果を分かりやすく表現するために「更新」や「完成猶予」などと置き換えたわけですが、単に言葉を換えただけではなくて、何が更新事由になるのか、何が完成猶予事由になるのかというところも整理いたしました。
考え方としては、権利者がいわゆる権利の上に眠っておらずに、権利行使をしたと見られるような事象があると、そこでまず時効の完成猶予という効果を与えようということです。更に、確かに権利が存在すると認められるような事象が生じた場合には、そこで時効の更新という効果を認めて、新たな時効期間をスタートさせようという整理です。
(1) 裁判上の請求等(改正法147条1項・2項) 裁判上の請求・支払督促・起訴前の和解・調停・倒産手続参加
⇒ 終了の時から6か月間の完成猶予
確定判決・確定判決と同一の効力を有する権利の確定
⇒ 更新
現行法は、最も典型的な時効中断事由である裁判上の請求などについて、訴えを提起すると、いきなり時効中断という効果を認めておりました。しかし途中で訴えが取り下げられたりすると、さかのぼってその効果がないかのような規定になっております。もっとも、解釈上は裁判を起こしている間は催告の効果があると考え、裁判上の催告という言い方をして催告の効果を認めて、その間は中断し続けるというような解釈になっておりました。しかし、改正法は、まず訴えの提起の段階で完成猶予という、取りあえず完成させないという効果を与えて、その後勝訴して権利があるということになると、その段階で時効の更新、従来でいう中断ですが、更新の効果を認めて時効期間を再スタートさせるという整理をしております。
判決と同様の効力を有するものも同じですが、取りあえず裁判上の請求等をした段階では、そのような事由が終了してから6か月間は完成しないという完成猶予の効果を与えると規律が改まっております。
(2)強制執行等(改正法148条1項・2項)
強制執行・担保権実行・形式競売・財産開示
⇒ 終了の時から6か月間の完成猶予権利の満足に至らないとき→更新
強制執行も裁判上の請求と似たような整理です。ここでいう強制執行というのは、いわゆる狭義の強制執行だけではなくて、担保権実行や形式競売や財産開示の手続を含みますが、これらについても一定の権利行使がなされているという意味では、訴訟と同じで、これらの手続を採られた段階でその手続が終了してから6か月間は完成を猶予するという効果をまず与えておきます。執行によって権利が満足してしまえば権利そのものが消滅しますが、執行によって回収しきれず満足しきれない場合には、執行が終わった段階で今度は更新という非常に強い効果が生じるということです。
(3)仮差押え等(改正法149条)
仮差押え・仮処分
⇒ 終了の時から6か月間の完成猶予
仮差押え、仮処分、これは現行法では中断事由とされておりましたが、そこまでの強い効果を認めるのは合理性がないということで、完成猶予事由にいわば格下げといいますか、効果が弱くなっております。
(4)承認(改正法152条1項・2項)
承認(相手方の権利の処分につき行為能力や権限は不要)
⇒ 更新
承認は現行法同様、更新という強い効果が認められております。
(5)催告(改正法150条1項・2項)
催告
⇒ 6か月間の完成猶予
※催告による完成猶予中の催告⇒効力なし
催告も現行法と同じ効果で、取りあえず6か月間、完成を猶予するということです。ご存じのとおり催告は6か月間の猶予ですから、暫定的に時効の完成を延ばす効果はありますが、その6か月以内に訴訟提起等のより強力な中断措置を取らなければ時効が完成してしまうと今まで理解していたわけですが、そこは今後も同じです。ただ、催告を繰り返してもだめですよというのが、現行法の争いのない解釈でした。新法では明文で催告による完成猶予中に更に催告をしても、更に6か月延びることはないという現行法の解釈を明文で明記しております。
(6)天災等による時効完成猶予
(改正法161条)
天災等の事変による裁判上の請求・強制執行不可
⇒ 障害の消滅時から3か月間の完成猶予
天災等による時効完成猶予というのは、従来、現行法でも時効の停止事由となっておりましたが、その停止される期間が2週間という非常に短い期間です。2週間だけ完成が止まっても、その間にすぐに対応することは難しい場合が、大地震等を考えればあるだろうということで、完成猶予の期間を3か月に延ばしました。
立法の過程では、ほかの事由が終了してから6か月ですので、ここも6か月でいいのではないかという議論もあったのですが、現行法の2週間からいきなり6か月というのは、12倍になりますので、そこまでするのはどうかということで、3か月となっております。
(7) 協議による時効完成猶予
(改正法151条1項・2項・3項・4項)
協議を行う旨の書面(電磁的記録)による合意
⇒ ①合意から1年、②合意において定めた協議期間の経過、③書面による協議の続行拒絶通知から6か月、のいずれかまで完成猶予
※協議による完成猶予中の再合意=本来の時効完成時から通算5年以内は可
※催告による完成猶予中の協議の合意・協議の合意による完成猶予中の催告は不可
※催告と協議の合意以外の完成猶予事由の競合・繰り返しについては解釈問題
協議による完成猶予というのは、全く新しい制度です。これは債権者、債務者間で債権の存否や額などについて争いがあって交渉しているときに、時効期間の満了が迫ってくると、時効が完成してしまっては債権者としては仮に権利があっても請求できなくなるということで、専ら時効中断のために訴訟を起こすかという問題が実務上あったわけです。しかし、それは余り合理的ではないだろうということで、債権者、債務者間で協議をしている間は時効の完成を猶予するという新たに設けられた事由です。
協議を行うということを合意すればいいのですが、そのことを口頭で合意しただけですと、合意があったか、なかったかが不明確になるので、書面若しくは電磁的記録で合意するということが前提になります。債権の存否や額などについて協議をするという合意をすると、そこから1年間、あるいはその合意の中に一定の期間協議をするという協議期間を定めた場合には、その定められた協議期間、若しくは書面でもって今後は協議を続行しないという拒絶の通知をした場合には、その通知から6か月間、この3つのいずれか最も早く満了する期間までは完成を猶予するという制度です。
協議を行う旨の合意書面なのですが、そこに何を書いたらその書面に当たるのかということについては、条文には何も書いてありません。まさに協議を行うということしか書いてありません。ですから、何をどう書面に書けばこの規定に当てはまるのかというのは今後の実務次第というところもあろうかと思います。
端的に時効の完成を猶予するとか、時効を完成させないなどと書けば非常に分かりやすいのですが、必ずしもそう書かなければいけないということにはなっていません。一定期間協議をしましょうという趣旨があればいいと解されております。
少し留意しなければいけないのは、例えば1年間協議しましょうといって、猶予の合意をして協議してみた。しかしまだ合意に至らないので、もう少し協議をしようとお互い考えているというときには、再度その協議をするという合意をすれば、またその期間、時効の完成が猶予されるという効果が認められております。
先ほど催告は二度も三度も繰り返しできないという現行法の解釈が明文化されたという話をしましたが、協議による完成猶予については再度猶予するということでも有効と考えられています。ただ、全くエンドレスかというと、それもよろしくないだろうということで、本来の時効完成時から通算して5年以内という期間の制限はあります。ですから最長5年までは完成猶予を合意することができるということです。
ただ催告による6か月間の猶予とこの協議による完成猶予の合意を組み合わせて延ばしていくことは認められないことになっています。つまり催告期間中に完成猶予の合意をするとか、あるいは完成猶予の合意中に債権者が債務者に対して催告するというようなことをしたとしても、その2つの組合せで延びるかというとそうではないということになります。
ですから取りあえず催告で6か月延ばしておいて、更にその6か月の間にこの協議を行う合意をして、更に延ばすことはできないということはご留意いただきたいと思います。
完成猶予事由はほかにもいくつか、今説明したようにあるわけですが、これらを組み合わせたときにどうなるかということについてはどこにも明文規定がありませんので、そこは解釈に委ねられております。
4、時効の援用権者(改正法145条)
「保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者」を含む。
時効の援用権者のところについて若干の手当てがなされています。ここは争いのない解釈を明文化しただけですが、保証人、あるいは物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者が援用できるということです。この「正当な利益を有する者」の例示として、保証人、物上保証人、第三取得者を明文で掲げたということです。更に「その他」が付いていますから、これらに限らないで、それに準ずるような者も「正当な利益を有する者」とみなされれば、時効の援用権が認められるというように明記しました。ほかにどういうものがあるかは、余り想定しにくいですが、一応「その他」の余地もあると思います。
現行法上、解釈を行うに当たって、時効を援用する直接的な利益があるということをメルクマールしていたと思います。改正法は「正当な利益を有する者」という表現がとられていますが、今の判例の解釈を変える趣旨ではありませんので、今まで援用できた人ができなくなるということは想定していないということです。
(次号へつづく)