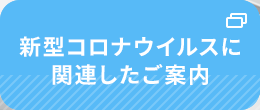会長あいさつ
 梅雨も明け、今年も暑い夏がやってきました。幼少期から東京住まいですが、その頃は最も暑い日でも32℃程度で、北関東で35℃などと聞くと信じ難いと思っていました。今は東京でも36℃程となり、国内でも40℃近くになる地域が出てきています。このような傾向は世界中で見られ、この半世紀弱の間に、気候が人体に与える悪影響は顕著となり、致命的なものとなってきました。異常気象と呼ばれていた現象も毎年のものとなり、もはや一時的な問題ではないことを実感します。気候危機を示す表現も、「地球温暖化」から「地球灼熱化」に変わりつつあります。
梅雨も明け、今年も暑い夏がやってきました。幼少期から東京住まいですが、その頃は最も暑い日でも32℃程度で、北関東で35℃などと聞くと信じ難いと思っていました。今は東京でも36℃程となり、国内でも40℃近くになる地域が出てきています。このような傾向は世界中で見られ、この半世紀弱の間に、気候が人体に与える悪影響は顕著となり、致命的なものとなってきました。異常気象と呼ばれていた現象も毎年のものとなり、もはや一時的な問題ではないことを実感します。気候危機を示す表現も、「地球温暖化」から「地球灼熱化」に変わりつつあります。
気候危機の要因は複合的かつ世界的であり、私たち日本の弁護士がこれに対してできることは限られているのかもしれません。しかしそれでも、日本弁護士連合会では、2021年の人権擁護大会において「気候危機を回避して持続可能な社会の実現を目指す宣言」を採択するなど、気候危機の問題について繰り返し意見発信し、国に対して具体的な対策を求めるとともに、自らも課題解決のために最大限努力することを宣言してきました。近年では、世界の司法関係者の間で、気候危機が生命の危険をもたらすことなどから、これを人権侵害であると捉え、喫緊の課題であることを社会にアピールする動きも強まっています。弁護士ですので違法な手段によることはありませんが、後になって手遅れであったと絶望することのないよう、引き続き社会に訴えていくことが使命であろうと思います。
これをお読みになっている皆様、老若男女を問わず、特に猛暑日には外出を控え、エアコンを使い、定期的な水分補給を意識しましょう。そして、ご高齢のご両親や幼いお子様が命を失うことのないよう、身近な人への声掛けやご配慮も是非お願いいたします。
2024年(令和6年)8月
第二東京弁護士会会長 日下部 真治