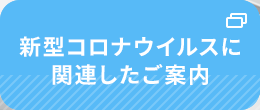民法(債権法)改正の最重要ポイント(後編)
後編 全3回

5、履行不能・債務不履行に基づく損害賠
1、履行不能(改正法412条の2、413条の2)
(1)履行不能の概念等
債務の履行が「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」不能であるとき
⇒ 履行請求できない。
契約成立時に履行不能であったとき(原始的不能)
⇒ 損害賠償請求を妨げない。(=当然に無効ではない)
(2)履行遅滞中/受領遅滞中の履行不能
債務者の履行遅滞中の当事者双方の帰責事由によらぬ履行不能
⇒ 債務者の帰責事由による履行不能とみなす。
債権者の受領遅滞中の当事者双方の帰責事由によらぬ履行不能
⇒ 債権者の帰責事由による履行不能とみなす。
履行不能、債務不履行に基づく損害賠償について、ご説明します。まず、履行不能という概念自体は従来からあるわけですが、条文として「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」不能を判断するということが明示されています。この「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らす」というフレーズは、新しい民法の中で、あちこちで出てきます。非常に重要なキーワードの1つと言えるかと思いますが、履行不能の概念のところでも用いられています。
より大事なことはその次に書いてあります、「契約の成立時に履行不能であったとき」いわゆる原始的不能と呼ばれる場合ですが、その場合であっても損害賠償を妨げないという規定が置かれました。履行の提供が物理的に不能というのが一番典型ですが、解釈において、社会通念上不能であれば、物理的に不能でなくても不能だというふうに幅を持って考えられてきました。いずれにしても、そういう社会的な意味での不能も含めて、契約締結時に既に不能状態になっている場合には、それを原始的不能と言って、その場合には契約が無効であるというのが一般的な考え方だったわけです。
しかし、この点は不能になる時点が契約締結の1日前か1日後かのタッチの差で、契約の有効、無効が変わってしまうのはおかしいのではないかと批判をされていたところです。そこで、改正法では、いわゆる原始的不能であっても当然には契約は無効にはならないということが明記されました。
それは412条2項の条文の字面だけを見ると、損害賠償の請求をすることを妨げないというような表現ですが、従来、原始的不能の契約は無効だったものを改正法では有効であることを前提に損害賠償請求できると規定しています。もっとも、当然に無効ではないということは、常に有効ということでもないので、そこはご留意いただきたいと思います。
それから(2)の履行遅滞中、あるいは受領遅滞中の履行不能についても、明文の規定が設けられています。413条の2、1項では、履行遅滞中の当事者双方の帰責事由によらない履行不能については、債務者の帰責事由による履行不能とみなす、逆に2項では、債権者の方で受領遅滞中のときの当事者双方の帰責事由によらない履行不能は、債権者の帰責事由による履行不能とみなすと規定されています。これは従前からの解釈で、ほとんど異論はないところを明文化しています。
2、損害賠償義務とその免責事由(改正法415条1項)
(1)原則
不履行があれば、原則として賠償義務あり。(「帰責事由」を積極要件としない)
(2)例外
「帰責事由」がないときは免責される。
←「契約その他の当該債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らし」判断
=「契約の性質、契約をした目的、契約締結に至る経緯その他の事情に基づき、取引通念を考慮して定まる当該契約の趣旨」に照らして判断
次に損害賠償ですが、現行法に比べて少し規定が変わっています。現行法では帰責事由について、債務不履行の損害賠償の要件と解釈されています。現行法の条文を見ると、履行不能の場合だけ帰責事由が要件とされていたようにも読めますが、解釈論上は履行不能か履行遅滞かを問わず、いわゆる債務不履行責任を問う場合には帰責事由が積極要件と解釈されていました。しかし、今後は帰責性のないことが免責事由、免責要件ということになります。ここでも、何をもって帰責事由ありと言うのかについて、「契約その他の当該債務の発生原因及び取引上の社会的通念に照らして」判断するということが明記されています。
これで何が変わるかというと、余り今までの実務が変わることはないと考えられています。というのは、解釈論としては帰責事由が損害賠償をするための積極要件という位置付けにはなっていましたが、実務的に、損害賠償請求訴訟で原告が被告の帰責事由をいちいち立証することを求められてこなかったからです。原告としては、被告がこういう債務を負っていたにもかかわらずその債務を履行しなかったと言えば十分であったと言えます。したがって、実務的には帰責事由がないことが被告の抗弁という形で判断をされていると言えますので、そういう意味ではそれを素直に条文にも反映させたにすぎないと思います。それから何が帰責事由かということについて、判例等では故意、過失、あるいは信義則上、それと同視しうる事由というようなことが説明されていましたが、研究者からは、故意や過失という問題とは違うのではないかと指摘をされていたところです。
結局、何が帰責事由になるかということは一般的抽象的に定まるものではなく、個々の契約ごとに決まってくるわけです。この契約において、こういうことをしてはいけない、しなければいけないという判断がされます。
「契約その他の当該債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」判断するということを今までもやっていたのでしょうが、何が帰責事由かということを考えるときには、当該契約に着目しないと帰責事由に当たるとも、当たらないとも判断がつかないことを素直に条文上で表現したということです。
判断のメルクマールを条文でどう書き表すかという点は、当初は、「契約の性質、契約をした目的、契約締結に至る経緯、その他の事情に基づき、社会通念を考慮して定まる当該契約の趣旨に照らして判断する」と分かりやすい表現になっていました。
中間試案のあたりでは、キーワードとして「契約の趣旨」という言葉を用いて契約の性質以下の表現を記載しておけば、改正法のほかの条文上に「契約の趣旨」が記載されていた場合には、同様の意味であると理解されるので非常に分かりやすいとされていました。しかし、内閣法制局から、「契約の趣旨」では、法律の文言としてはふさわしくないという判断がなされたため、最終的には、何度も述べるように「契約その他の当該債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らし」という、抽象的な表現になってしまいました。ただ、解釈としては「契約の趣旨」に照らして検討することになると思います。
3、履行に代わる損害賠償の要件(改正法415条2項)
①債務の履行不能
②債務の履行拒絶
③契約解除又は債務不履行による解除権の発生
次に履行に代わる損害賠償の要件ですが、これは講学上は填補賠償と言うこともあります。この履行に代わる損害賠償の要件が明文化されました。一番典型的なのは履行不能の場合です。契約で定めた債務が履行不能になってしまった場合に、本来の債務はもう履行できないわけですが、その履行に代えて損害賠償請求を認めようという場合です。ここで言う履行不能の概念は1履行不能で述べたとおりです。
更に填補賠償の要件としては、履行不能に限らず、履行拒絶の場合も填補賠償が認められると定められています。この履行拒絶というのは、一切履行する意思がないことを明確に債務者が表示をしている場合と言われています。履行自体が不能であれば履行不能の方に当たるわけですが、履行は可能であるが、肝心の債務者が一切履行する気がないと明確に表示をしている場合、実質的には履行不能と同視しうるような状況だろうということで、判例でも履行不能に準ずる場合として損害賠償を認めている例があります。
しかし、どこまでの拒絶をすれば、明確な履行拒絶に当たるのかというのは、なかなか当てはめることが難しいという気がします。
債務者が履行を拒絶するといっても、どこまで拒めば、それに該当するのか。合理的な理由があって、こういうことが解消されない限りは履行できませんというときに、あなたは履行を拒絶しましたねということで、填補賠償を請求しますということになってしまうのかというと、それは違うと思います。そういう意味では、これがどのくらい適用されやすい条文になるのかというのは、実務的に非常に注目すべきところだと思っています。
それから契約解除がなされた場合か、あるいは解除権が発生した場合も、填補賠償はできるかということです。契約が解除された場合は比較的分かりやすいですが、解除の意思表示がなされなくても法律上解除権が発生すれば、填補賠償は行うことができるということになっています。
4、損害賠償の範囲(改正法416条)
「通常生ずべき損害」と「当事者が予見すべき特別事情に基づく損害」
←損害賠償の範囲を規範的に判断
※「予見時期」(契約時か、不履行時か)、「予見すべき当事者」(両当事者か債務者か)は解釈問題
次に損害賠償の範囲ですが、現行法からは余り大きな変化はなく、通常生ずべき損害と、当事者が予見すべき特別事情に基づく損害が損害賠償の範囲だという規律です。現行法の「予見することができたとき」から、改正法では「予見すべき」と少しだけ言葉が変わっています。これは予見可能というときに、ここは規範的な概念で、実際に予見したかしないか、できたかできなかったかということよりも、予見すべきであったかどうかということがポイントになるという考え方に基づいて、「すべき」という表現に改められています。ただ考え方は現行法上の解釈と変わったわけではありません。
したがって、因果関係をめぐる解釈論については通説的な理解として非常に浸透している相当因果関係説に従った議論がそのまま続くのだろうと思います。なお、予見可能かどうかの予見時期が、契約締結時なのか、債務の不履行時なのかということをめぐる議論や、あるいは予見すべき当事者というのが両当事者なのか、債務者なのかということが議論されていましたが、これについては結論を出さずに、引き続き解釈に委ねるということになっています。
6、契約の解除・危険負担
1、催告解除の要件(改正法541条)
相当期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないとき解除可。
ただし、期間経過時の不履行が「その契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」は不可。
←「軽微である」≠「契約目的を達成できる」
※債務者の帰責性は、解除の要件としない。
←債権者を契約の拘束力から解放する制度として位置付ける。
※債権者に帰責事由がある場合には、解除を認めない(改正法543条)
次に契約の解除、それから危険負担です。契約の解除については、一番変わったところは債務者の帰責性を解除の要件としないというところですが、催告解除と無催告解除という、2つのパターンがあるという、この構造自体は変わっていません。つまり、考え方としては原則として相当の期間を定めて、履行の催告をして、その期間内に履行がなされないときに初めて解除ができるという、現行法の規律が維持されています。
維持されているということをあえて申し上げましたが、議論の過程では催告は不要ではないかという見解も当初かなり強く主張されていました。確かに弁済期が決まっているわけですから、催告をせずとも、履行期を徒過すれば解除という効果を認めてもいいのではないかという考え方や、重要な債務について履行があれば催告をせずとも解除を認めてもいいのではないかという考え方も分からなくもないです。しかし長年、催告をして、なお履行がないときに解除するという仕組みで実務は動いてきたので、それを変えるべきではないということで、原則は催告をした上で、なお履行がないときに初めて解除できるという仕組みになっています。
ただ、催告期間の経過時の不履行が、その「契約及び取引上の社会通念に照らして」軽微であるときには解除できないというただし書が付いています。この考え方も既に解釈上、判例等で認められているものです。メインの債務ではなく、付随的な債務などの不履行があったときに、それをもって契約全体を解除することはできないという判断をしている判例はたくさんあります。そういう考え方を明文化しています。明文化するに当たり、表現としては「軽微であるとき」という言葉が使われていますし、この軽微性の判断についても、「契約及び取引上の社会通念に照らして」という判断のメルクマールが付けられています。
重要なところは、解除の要件から帰責性が外れたということです。従来、解除という制度について、債務不履行に対する制裁的な効果と考えられていました。しかし、解除権というのは必ずしもそういうものではなく、帰責性があろうがなかろうが、もはや債務の履行が期待できないような状態になったときに、その契約から当事者を解放させる制度であるということが改正法で重要視されたからです。しかしながら、債権者の帰責性がある場合、 解除を認める必要はないので、そこは認めないということも合わせて明示されています。
2、無催告解除の要件(改正法542条)
①債務の全部の履行不能
②債務の全部の履行拒絶(拒絶する意思を明確に表示したとき)
③債務の一部不能又は一部拒絶の場合で契約目的達成不可
④定期行為
⑤その他催告しても契約目的を達成する履行の見込みのないことが明らかなとき
それから、無催告解除の要件も明文で定められました。先ほど述べたように催告解除の原則が維持されたものの、催告することに意味がないような場合、典型的には債務が全部履行不能な場合には無催告解除を認めるということになりました。
無催告解除④に挙げた定期行為、一定の時期までにやらないと意味がないような場合にも無催告解除ができます。それ以外にも②、③、⑤がありますが、②は先ほどの損害賠償の要件で指摘したとおりです。拒絶する意思を明確に表示したというのが前提になっていますが、この履行拒絶の場合にも無催告解除を認めています。
それから③の債務の一部の不能、又は一部の履行拒絶の場合でも、履行された部分だけでは契約の目的を達成できないような場合、契約全部を解除できるということになっています。
ここまでは何となくそれなりに分かりますが、問題は⑤です。その他催告しても契約目的を達成する履行の見込みのないことが明らかであるときという、包括条項といいますか、バスケット条項が定められています。もちろん解釈としては①〜④に準ずるような場合ということにはなるでしょうが、この適用範囲がどのぐらいの広がりを持っているのかということによって、まさに解除がどの程度認められるのかということが決まってきます。ここも非常に今後の実務が注目されるところです。
3、危険負担の債権者主義の特則の削除
「特定物に関する物権の設定・移転を双務契約の目的とした場合=債権者負担」との規定
(現行法534条)を削除
解除の要件から債務者の帰責事由がなくなったことを受けて、危険負担の制度にも影響が出ています。危険負担の制度は現行法の534 条以下にありますが、特定物に関する物権の設定、移転を双務契約の目的とした場合には、534条で債権者主義が採られていました。しかし、これは合理性がないということで、適用場面はかなり狭められて用いられてきたので、この評判の悪かった534条は削除されました。
4、危険負担の効果(改正法536条)
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったとき→反対給付の履行拒絶可
※反対債務を消滅させるには、解除を要する。
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったとき
→反対給付の履行拒絶不可
ただし、債務者は、債務を免れたことによって得た利益を債権者に償還が必要。
一方、536条の債務者主義の規定のところが残りますが、解除について債務者の帰責性を外したことによって、解除ができる場面と、危険負担の場面が重なるということになります。つまり、従来の規定の適用範囲というのは、債務者に帰責性がある場合には解除で規律をし、債務者に帰責性がない場合には危険負担で規律をするというすみ分けがなされていました。しかし、解除の方の要件が変わってしまって、帰責性を問わずに解除できるということになると、危険負担という制度はなくてもいいのではないかという議論もありましたが、最終的には残りました。
残った上で変わったことは、効果のところです。今までは反対給付が当然に消滅すると考えられていました。今後は消滅ではなくて、反対給付の履行を拒絶できるという履行拒絶条項に変わりました。反対債務を完全に消滅させるためには、解除の意思表示をして、解除の効果として債務は消滅するわけですが、危険負担の効果としては履行を拒むことができるということにとどまることになります。
一方、債権者の責に帰すべき事由によって履行することができなかったときは、履行拒絶ができません。また、債務者の方は債務を免れることによって得た利益がある場合には、それを債権者に償還しなければならないという規律も明文化しています。
7、売買の担保責任
1、要件(「契約責任」として再構成)(改正法562条、563条、564条、565条)
「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」、又は、
「移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合」
の債務不履行責任
売買の担保責任について説明します。現行法でも561条以下に、他人物売買以下のところにずらっと条文が並んでいます。ここもかなり大きく整理されました。
もともと570条の瑕疵担保責任については、いわゆる法定責任説という考え方と、契約責任説と呼ばれる考え方の古典的な議論の対立があり、かつての通説は法定責任説という考え方でした。近年の有力な考え方は契約責任説ということで、民法改正に当たっては、契約責任説を前提に規律を再構成するということについて、余り異論は出ませんでした。つまり債務不履行責任として売主の担保責任を整理し、瑕疵という言葉も使わずに「契約内容に適合しない」という、契約内容不適合と表現も改めています。
まず売主は買主に対して種類、品質、数量が契約の定めに適合するものを引き渡さなければならないという義務、あるいは、契約の内容に適合した権利を移転しなければならない義務を基本的な義務として負っているという前提の下において、しかるにその契約内容に適合しない目的物を引き渡したり、権利を移転したという場合には、担保責任を負うという整理をしています。
2、効果(救済手段の具現化・明文化)(改正法562条、563条、564条、565条)
① 損害賠償請求(ただし、「契約・・・及び取引上の社会通念」に照らした帰責事由がないときは不可)
②解除(催告解除及び無催告解除)
③ 追完請求(不適合が買主の責めに帰すべき場合は除く)
※売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完可)
④代金減額請求(催告減額及び無催告減額)
※対価的均衡を図る趣旨に基づく請求であり、債務者の帰責性を要件としない。
※一部解除の実質を有し、解除の要件と整合的規律
大事なことは、担保責任について、どういう効果を与えるかということです。債務不履行責任ですから、債権総論的に言えば、損害賠償責任や、あるいは解除権行使というものが当然に導かれてくるわけです。それは損害賠償請求であれば415条以下、解除権についても541条以下を見れば書いてあります。
売買の規定のところに出てくるのは、基本的にはそれ以外の効果ということになります。562条ではまず追完請求権というものが規定されています。つまり、不完全なものを提供した売主の義務として完全なものにそれを追完する義務を負うということです。ここで大事なことは、追完請求というのはいろいろな追完の仕方がありうることを想定しているという概念です。
それはどういう不適合があるのかに対応し、本来の履行されるべき状態と、実際になされた不完全な履行の状態と比較して、その差をどうやって埋めるかという話です。例えば納めた品物に何か故障したような部分があったら、そこを直してくれということを求めることによって不具合が解消し、不完全なものが完全になるという場合もあるでしょうし、そこの部品を取り換えてくれと言って、その部品の交換をすることで満たされる場合もあるでしょう。あるいは全く新品の、別のものを持ってきてくれという場合もあるかもしれません。
どういう追完の仕方をさせるかという点は、一次的には買主の方がこうしてくれと言えることになっていますが、大事なことはそれに対して売主の方で別の追完の方法を選択できるという仕組みになっていることで、最終的な決定権は売主の側にあるという点に注意が必要です。
それからもう1つの効果といいますか、救済措置としては、代金減額請求権があります。代金減額請求権というのは請負の規定として存在しましたが、これを一般的な担保責任の1 つの効果として明文で定めています。これが563条のところです。
代金減額請求権というのは、要するに不具合がある不完全な部分に対応して、その部分の程度に応じて代金の減額を請求できるということで、いわば履行されていない部分の履行義務を解除する、一部解除したのと同じような状況をつくり出すものなので、解除の要件と同じような規律になっています。つまり、先ほど催告解除と無催告解除についてご説明しましたが、ここでも催告減額と無催告減額という要件が必要とされています。
注意すべき点は債務不履行と違って、帰責性を要件とはしていないことです。つまり、売主、買主の債務の対価的な均衡を保つという観点から、片方の債務が不完全なものであれば、もう片方の債務も不完全なものとそろえた限度で認めましょうということですから、債務者の帰責性は問題にしません。
ただ難しいだろうなと思うのは、いくら減額できるかということです。例えば不完全なものが、数量が足りないというのであれば非常に分かりやすいです。100個納めてくれと言ったのに90個しかなかったら、10%代金を減額してくださいと言えば済むわけです。しかし、少し質の悪いものが入っていた、あるいは質が悪いというわけではないが、自分の指定した色と違う色のものが納められたというようなときに、それを不具合の程度に応じて減額するというのは、なかなか難しいです。それから、もともとが時価より高値に代金を設定した場合、あるいは時価より低めに設定した場合など、いろいろあると思います。そのときにどのくらい減じたらいいのか。この辺も今後の実務次第かなと思います。
この2つの規定の効果のほかに、先ほど述べた損害賠償・解除について、それらの請求を妨げないという確認的な表現で規定がされています。したがって、担保責任の効果としては、4つの効果がある(①〜④)わけですが、規定の置かれている形というのは単純に4つ並んでいるということではなくて、解除と損害賠償は確認的に564条で妨げないことが規定されているということを、条文を読む際にご留意いただきたいと思います。
3、競売の場合の例外(改正法568条)
買受人は、「数量及び権利に関する不適合」につき、解除(催告解除・無催告解除)又は代金減額請求できる(損害賠償・追完請求は不可)。
「競売の目的物の種類又は品質に関する不適合」については、一切責任追及不可
次に、競売の場合の例外です。現行法でも競売の場合の例外の条文があります。ただし、現行法は狭い意味での強制競売の場合を規定していますが、改正法では、強制競売に限らず、もう少し広げる意味で執行法上の競売の場合の例外規定が定められています。具体的には、買受人は数量及び権利に関する不適合があったときに、解除又は減額請求ができるという規定です。そして、反対解釈として、解除と減額請求はできるということは、逆に言えば損害賠償や追完請求はできないということを意味しています。
それから、数量及び権利に関する不適合についてというのは、裏を返すと、目的物の種類、品質に関する不適合については、この規定は適用がない。その結果、一切責任追及できないということを意味しています。
4、期間制限(改正法566条)
目的物の種類又は品質に関する不適合の場合、「不適合を知った時」から1年以内の通知が必要(=数量及び権利に関する不適合については、通知不要)
ただし、売主が引渡し時にその不適合を知り又は重過失で知らなかったときを除く
更に、期間制限の規定があります。目的物の種類又は品質に関する不適合の場合には、不適合を知ったときから1年以内に通知をしなければならないということになっています。まず、この適用があるのは、今述べたように、種類、品質に関する不適合の場合だけであり、数量や権利に関する不適合については、この規律は適用がないです。したがって、通知はいらないということです。ただし売主が引渡し時にその不適合を知り、又は重過失で知らなかったときを除くとありますが、原則としては種類、品質に関する不適合に関しては、知ってから1年以内に通知しないと、権利の行使はできなくなるということになります。
今でも似たような条文があり、その事実を知ってから1年以内に請求しなさいというのがありますが、改正法では、ここは単に不適合があるということを通知すればいいということです。現行法の規定は、判例の解釈によると、瑕疵に基づく損害賠償請求については、具体的な損害を特定しなければいけないということになっているので、かなりしっかりとした請求をしなければならないと解釈されています。しかし、改正法では、1年以内に通知を行ってから、その後、実際の損害賠償請求自体は消滅時効にかからない範囲であれば、ゆっくりと請求しても構わないということです。
5、有償契約への準用(改正法559条)
売買以外の有償契約に売買の規定を準用(現行法どおり)
※請負人の担保責任への準用に留意
最後の有償契約への準用ですが、これは実は非常に重要条文であり、現行法上の条文がそのまま残るということになりますが、そのことによって、まさに他の有償契約においては同じような規定がいらなくなりました。実際に最も影響が出るのは請負の規定です。現行法では請負のところには請負人の担保責任の規定がずらっと並んでいますが、準用規定で足りるために、請負人の担保責任の規定はばっさりとなくなりました。ごくわずかに請負特有の特則だけが残ったということになります。
民法の規定はかなり条文が増えましたが、請負に関して言えば、条文が減ったということになっています。改正法では、請負人の担保責任を考える際、請負の規定を見ても例外的な場合しか書いていなくて、他の規定がないのかというと、559条で準用される売買の規定を見れば書いてあるということになりますし、損害賠償や解除の方は415条や541条を見ないとストレートに出てこないという、パンデクテン方式を貫いたような形になっています。
以上、改正法の重要な点に絞ってご説明させていただきました。