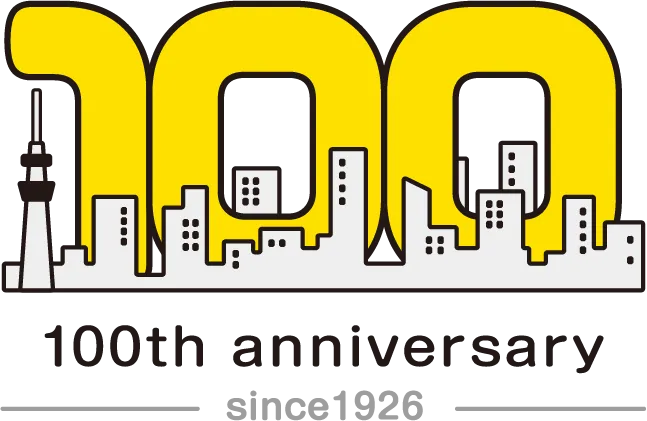山椿
渡邊 敏(36期)
●Satoshi Watanabe
エクスターン考
母校の法科大学院のエクスターンは、司法修習生より実務指導が困難である。一般に地裁事件で、特に知財事件は、企業の担当者等多数が傍聴する慣例になっているので、法科大学院生の傍聴は容易である。通常の地裁事件もあまり苦労しない。逆に家事事件は傍聴が殆ど困難である。プライバシーの名の元に傍聴を拒否される。簡裁事件も代理人受任事件は傍聴可能であるが、司法委員として関与した事件の特に和解手続は、裁判官の裁量で拒否されることが多い。調停委員も同様である。司法委員として関与したある事件で、マンション駐車場の管理会社の怠慢で、駐車場に外車が駐車スペースを前方にかなりはみ出して駐車していた。この駐車場では、はみ出し駐車は駐車場賃貸借契約で禁止されていたので、原告は管理会社に対し外車を駐車させないように要求したが、外車の持主に管理会社から連絡が伝達される前に、原告本人の妻が駐車場で外車を避けて出庫しようとした際に隣の車(外車の向かい側)に接触して損害を与えた(以下第1事故)。その後管理会社は外車の持主に連絡がつき外車の移動を要請したが、外車の持主に無視され、その後第1事故と同様の第2事故が起きた。この事件で、原告である事故車の持主は隣の車に対する接触事故で損害を賠償した( 第1、第2事故共)。原告は管理会社の責任を問うべく簡裁に訴えを提起したが、法科大学院生は傍聴ができなかったので、記録を一部書き留めて検討してもらった。二人の法科大学院生は合議の結果、管理会社が駐車場の管理を怠ったので、特に第2事故で管理会社から原告に対する債務不履行責任が発生し、損害賠償責任が発生するが、事故車の持主の妻の運転技術の未熟も加味して、管理会社は過失相殺の抗弁を主張できるという結論であった。裁判官は、交通事故実務で駐停車車両の背後から追突した車両は、基本的に追突車の過失が100対0であるという結論であった。後で調べたところでは、駐停車車両が駐車禁止場所で停車していた場合は、10%過失相殺されるため、駐停車車両に全く責任が発生しないわけではないことが分かった。エクスターン期間が1週間なので、法科大学院生は最終結果を知らずに研修を終えた。結局裁判官が原告に不利な事件の判例を探し出してきたので、第二事件の損害について25%過失相殺することを当方から提案し、管理会社が折れて和解解決となった。このような実際の事件は優れた教材であり、傍聴についても法曹界で幅広いコンセンサスを形成すべきである。この事件も法科大学院生が傍聴していたら、管理会社のかたくなな態度、原告代理人の請求がかなり無理筋であること、裁判官の考え方等参考になる点があったと思う。
話変わって法律相談の傍聴 では概ね拒否事案は無い。むしろ相談者は弁護士だけではなく法科大学院生の見解も聞きたいといった傾向が見られる。一般人には、弁護士も法科大学院生も、法律の専門家と見えており、色々な見解が聞けてメリットがあると考えているようである。今日も夕闇が迫り、法科大学院生と四谷の杜を好んで徘徊する弁護士(?)がいた。
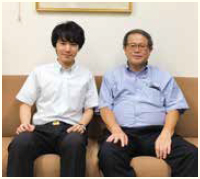
法科大学院生と筆者