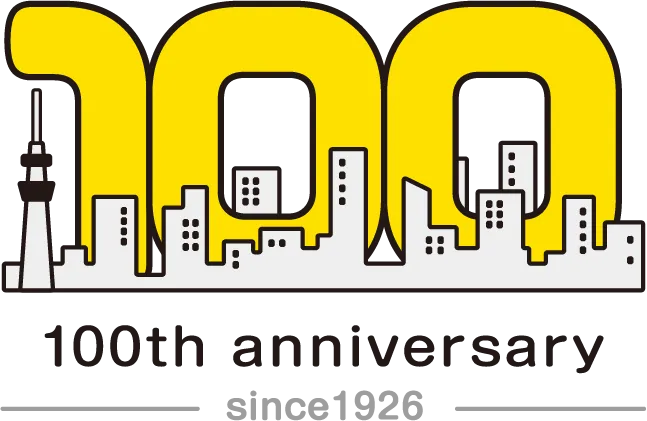花水木
私が弁護士7年目に至るまでに体験した、最も印象的な事件をもとに、弁護士の役目について考え直してみました。
今から遡ること約4年前、平成27年の出来事でした。国選事件の待機日であったことから、法テラスより連絡を受けて警察署まで赴き、被疑者と接見しました。被疑事実は自動車の窃盗ということで、否認事件ではあったものの、特別難しい案件でも、珍しい案件でもありませんでした。ところが、事件が進むにつれて発覚したのが、警視庁によるGPSを利用した捜査でした。当初、警視庁及び検察官は、GPSの利用の事実を断固否定していました。弁護側の調査で発覚するに至ったわけですが、検察官はそれでも利用したことの正当性を訴え続けて、事件は最高裁判所まで続きました。その間、被告人は一貫して否認し続けていましたが、結果として有罪判決が維持されて終結しました。これが、当該事件の流れです。
さて、今一度事件の結果を振り返ってみると、本件は、捜査機関がGPSを利用しなければ有罪にすることができなかった事案でした。確かに、犯罪防止や刑事訴追のために、捜査や証拠収集に積極的であること(GPSの利用の必要性)は理解できます。また、当時、この件がYahoo! ニュースに取り上げられたときも、GPS利用の適法性への言及よりも「犯人(当時、まだ被告人の立場ではありましたが)をかばう弁護士の気持ちが分からない」という、弁護人への批判的な意見も多く散見されましたが、これらのコメントをされた人達の気持ちも理解できます。しかしながら、犯罪を防止する、犯人を捕まえる、有罪にするためには、何をしてもよいのでしょうか。この事件を通して改めて考えさせられたのは、憲法31条以降の条文や刑事訴訟法の存在意義や制定経緯です。かつて、国家権力の暴走により起こった悲劇を繰り返さないために設けられたこれらの憲法や法律に忠実であるべきということです。このような考えから、GPSを利用した捜査手法の適法性を徹底的に争いました。弁護士でなければできない戦いであったと思いますし、弁護士冥利に尽きるものでした。
残虐な事件や悪質な事件に対する処罰感情の強さから世間的なものの見方は至極当然かもしれません。容易に情報にアクセスでき、また、メッセージを発信することができるようになったことで、声高に権利を主張したり、一人の人間によって世間を動かしたりできるようになり、情勢は大きく変動しています。その結果、こうした一人の発信や世論がきっかけとなって国家権力による暴走(あるいは、多数派による少数派への迫害など)がいつ起きてもおかしくはありません。そのような事態を早い段階で問題提起し、そして、抑止、歯止めをかけるのが、我々弁護士の役目ではないかと改めて考えさせられました。職業柄、相手方や世間から批判されます。しかし、それでも、国家や多数派による言動が法律に反しない正しいものであるのか、そして、結論の妥当性を見据えて、弁護士は細かく吟味し、常に目を光らせ続けなければなりません。

渡邉 祐太(65期)
●Yuta Watanabe