東京三会合同研修会 「成年後見実務の運用と諸問題」(後編)
後編 全2回
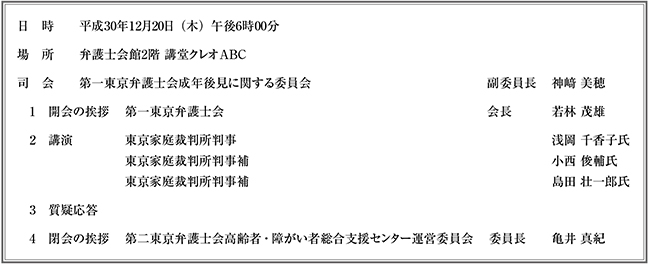
その他裁判所への質問
1 終了した事件記録の保管期間
終了した事件について、後見センターではどのような資料(審判書、財産目録及び裏付け資料等)を何年間保管しているか。また、後見人の方でも記録を保管しておいてもらいたいという期間の目安があったら教えていただきたい。
記録(財産目録や裏付け資料等を含む。)については、裁判所の管理が終了した後5年間保管している。後見開始・後見人選任等の審判書については、認容の審判書であれば管理終了後30年間保管しているが、却下した審判書はその他の記録と同様に5年間の保管となる。後見人等の記録の保管期間については、特に裁判所から要望すべきことはない。
2 郵便物等の回送嘱託に関する
郵便物等の配達の嘱託(回送嘱託)の申立てをするにあたり、留意すべき事項を教えていただきたい。
(1)回送嘱託の申立てについては、その必要性(民法860条の2第1項)の有無が問題となる事例が多い。この点に関する後見センターの考え方は、昨年まで後見センターに在籍されていた日景裁判官が『実践 成年後見 No.71』で説明されているところであるが、改めて回送嘱託の必要性に関する考え方を説明する(以下、件数の多い1年以内の初回申立てを念頭に説明する。)。
(2)郵便物等の回送嘱託は、成年被後見人が適切に財産管理を行うための方策として平成28年民法改正で新設されたものである。その制度趣旨は、成年被後見人が郵便物等を自ら適切に管理することが困難であるため、郵便物等の存在や内容を成年後見人が正確に把握することができない場合において、適切な財産管理に支障をきたすおそれがあることを考慮したものと解されるが、法は、これによって成年被後見人の通信の秘密が制約されることに鑑みて、裁判所が後見事務の遂行のために必要があると認めた場合にのみ回送嘱託ができるものとしたほか(1項)、嘱託期間についての制限を設け(2項)、嘱託の取消しや変更についての定めを置くなどして(3項)、本人の通信の秘密に配慮している。このような法の趣旨に鑑みると、回送嘱託の必要性が認められる場合とは、本人の通信の秘密を制約しないような方法によっては本人宛て郵便物等の存在及び内容を把握することができず、そのことによって後見事務の遂行に支障が生ずるような場合をいうものと解される。
(3)ところが、実際の申立てでは、後見人自ら又は親族や施設等の協力を得て本人宛て郵便物等の存在及び内容を把握する方法 (本人の通信の秘密を制約しない方法)の可否を具体的に検討した形跡がみられないものが散見される。裁判所からその旨指摘を受けた後見人が調査・検討し、かかる方法がとれない旨の補充を行った結果、認容審判に至ったものもあるが、取下げに至ったものも相当数に及んでいる(平成28年10月から平成29年9月までの自庁統計では、既済件数190件のうち、認容140件、取下げ50件となっている。)。
ア この点を具体的に説明すると、例えば、自宅に独居している本人が自ら郵便物等を管理できない(紛失するなどして後見人が存在及び内容を把握できない)場合や、自宅に独居していた本人が施設等に入所し、自宅が空き家になっている場合であっても、後見人又は信頼のおける親族が本人の身上監護ないし財産管理のために定期的に本人宅を訪れることが予定されているのであれば、その際に本人宅に配達されていた本人宛て郵便物等を確保する(親族の場合には、定期的に後見人に交付ないし郵送してもらう。)ことで、後見人として郵便物等の存在及び内容を把握することができることもあると思われる。したがって、この場合には、後見人が定期的に本人宅を訪問できず、親族においても、遠隔地に居住しているとか、高齢であるとか、疎遠である等の理由で協力を得られない等の事情を確認していただき、申立ての際に説明していただきたい。
イ また、後見センターでは、住民票の異動がされていなくても、郵便局において本人宛ての郵便物等を本人の入所する施設等に転送する手続を執ることができるものと理解しており、本人が施設等にいる場合ですぐに移転する予定がないときは、転送サービスの利用によってその施設等に転送された本人宛て郵便物等を施設等が受領・管理し、これらをとりまとめて定期的に後見人に交付ないし郵送するなどの協力を得る方法も考えられる。このような協力の有無は施設等によって相当異なるようであるので、この場合には、本人が入所している施設等が本人宛て郵便物等の受領ないし管理に協力してくれないという事情(管理はしてくれるが郵送はしてもらえないという場合には、例えばその施設が遠隔地にあり後見人が定期的に訪れることが困難である等の事情を併せて説明していただく必要がある。) があるか否かを個別に確認していただいた上で、その事情を申立ての際に説明していただきたい。
ウ なお、後見人からは、以上のような協力が得られるとしても、それによって郵便物等の交付ないし郵送をしてもらえる頻度が少ない(月に1回など)という事情が述べられることがある。しかしながら、直ちに後見人が対応しなければならない郵便物等が来る蓋然性があり、事前に宛先を後見人に変更する等の手続もとれないというのであればともかく、通常は、月に1回程度郵便物等の交付・郵送を受けられるのであれば、後見事務の遂行に支障が生じるとは考え難いというべきであり、上記のような事情は、本人の通信の秘密を制約する根拠としては弱いと考えている。
3 火葬費用を支払うための預金払戻許可
火葬のための預金払戻許可につき、親族がまず立替えしていた場合には、「本人の債務とはならないから許可しない」と聞いた。しかし、そもそも火葬の費用が本人の債務となることは生前契約がない限りはないのではないか。親族等が立替えているか否かで区別があるのか。
預貯金の払戻し許可に当たって問題となることが多いのは、「相続財産の保存に必要な行為」(民法873条の2第3号)に該当するか否かという点である。
元後見人によって行われる「死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結」は、その性質上、必ずしも相続財産の保存行為とは言い切れない面があるとして、適用上の疑義を避けるために同号で明示されたものであると解説されているところ、元後見人が同号の許可を受けて火葬、納骨等に関する契約を締結した場合には、その費用は保存行為によって生じた費用と言えるので、相続財産に属する債務になると考えられる。そして、元後見人が火葬等の許可を得て火葬を実行したということは、相続人が存在しないとか、相続人が関わりを拒んでいるなど適切な協力が得られない事案であることが通常である。このような場合に元後見人がその費用の支払を相続人に委ねると、債権者がその支払を受けるまでに相当な手間と費用を要することも考えられ、むしろ、元後見人において支払うことが相続財産の維持に役立つと思われるため、元後見人がその支払のために本人名義の預貯金の払戻しを行うことは、「相続財産の保存に必要な行為」と判断されることが多いと考えられる。
これに対して、本人の親族が火葬、納骨等に関する契約を締結して、その費用を立替え払いした場合、その費用が「相続財産に属する債務」になると考えたとしても、本人の親族という関係性に鑑みれば、その精算のための払戻しが「相続財産の保存に必要な行為」といえるか否かについては異なる考慮が必要になると思われる。例えば、立替え払いをした親族が本人の相続人である場合には、引継ぎ後に処理してもらえば足りるはずであるし、本人の相続人ではない場合であっても、その関係性を考慮すれば、報酬払戻しの方法によらずとも、預貯金を引き継いだ相続人から支払うことが期待できる場合もあるものと思われる。相続財産は飽くまで相続人が管理処分すべきものであり、相続債務の弁済も相続人がすべきものであるから、申立ての際には、元後見人において預貯金の払戻しを行う必要性があるか否かについて十分に検討していただきたい。
なお、実務上、葬儀費用の支払のための預貯金払戻しの許可申立てがされることもあるが、葬儀に関する契約の締結は裁判所による許否の判断の対象とされておらず、その費用も当然に相続財産から支出すべきものとは解されない(親族等が行う場合、喪主において負担すべきとされることが多いと思われる。)。したがって、火葬の場合とは異なる考慮が必要となることに留意されたい。
その他裁判所への要望
1 任意後見契約の代理権の範囲
任意後見人を手続代理人として遺産分割調停の申立てをしたところ、任意後見契約の代理権目録の記載に不足があるとして、最近、遺産分割調停の申立てが(従前と異なり)受理されない。遺産分割のためだけに法定後見を申立てなければならなくなるので、従前どおり受理していただくことはできないか。
任意後見契約に関する法律の10条1項において、任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」に限り法定後見を開始できると定められている。文献などによれば、この法定後見を開始できる場合、すなわち「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」の典型例として、任意後見契約で定い限り、成年後見制度があまり利用されていない。成年後見制度の利用者数自体は増えているが、認知症高齢者の数に比べると非常に利用者が少ないといわれている。また、前編冒頭の統計説明のとおり、統計上は後見の類型が圧倒的に多く、補助や保佐の類型が少ない。つまり、後見の状態になって初めて裁判所に申立てが来るという状況で、よほど大きな支障がない限り利用されない傾向がある。
2点目として、親族よりも第三者専門職が選 任されることが多くなっているが、そうしたケースの中には意思決定支援や身上保護等の福祉的な視点に乏しい運用がなされているものもある。これについては異論も多かろうとは思うが、そのような指摘がされている。
3点目として、後見等開始後に本人、親族又は後見人を支援する体制が十分に整備されておらず、監督機関たる家庭裁判所が福祉的な観点から必要な助言を行うことは困難であるという指摘もされている。この福祉的な観点からの助言については、家庭裁判所は監督機関であるので不正行為や裁量逸脱のおそれがある場合には対応するが、後見人の裁量の範囲内のことについて、後見人に対して指示をすることは基本的にない。後見人の側からすると、家裁に相談しても裁量判断にゆだねると言われてそれ以上の答えはもらえないため、らちが明かないと感じることも多いだろう。
さらにその施策の目標として、利用者がメリットを実感できる制度運用への改善ということを掲げている。その一つとして、本人の生活状況を踏まえて、本人の利益保護のために最も適切な後見人を選任することが挙げられており、ここで後見人等選任の在り方が議論になっている。
2 後見人等選任の在り方はどうあるべきか
最高裁が公表している統計上の数字では、現在、専門職の選任割合が全国平均で約7割を超えている状況である。過去を振り返ると、いずれも最高裁が公表している数字であるが、全国平均で、今の後見制度が始まった平成12 年度は親族後見人の選任割合が9割以上であった。今から約10年前の平成19年度でも親族後見人の選任割合は7割を超えていた。平成24年になって、初めて親族後見人の選任割合が5割を切るようになり、平成29年では全国で親族後見人の選任割合が26%にまで下がっている。制度が始まった当初に比べると、現在は専門職と親族の選任割合が逆転している状況である。
専門職の選任が多くなっているということは、裁判所としても専門職が必要だと考えている、すなわち専門職を必要とするような案件が非常に多い、ということではあるが、数字だけを見ると、これから制度を利用しようと考えている国民の側から見た場合に、誰が選任されるか分からない、知らない人が後見人に選任されるかもしれない、それであれば制度を利用したくない、という声があるのも否定できないところである。実際に、親族による申立て後に裁判所から専門職選任の可能性を説明すると、それならやめたい、取り下げたいと強硬に抵抗されることがある。しかし、裁判所としては、専門職選任の可能性があるという理由だけでは取下げを許可できないと考えている。このような事情が制度利用促進の妨げになっているとすると、選任の在り方を考える必要が出てくる。
基本計画に基づく取組としては、裁判所の中だけではなく、市町村、あるいは推進機関、社会福祉協議会等で、申立てに至るまでの支援の充実ということが検討されている。申立てそのものに対する支援だけではなく、制度の広報活動やニーズの発見も含めての幅広い支援の中で、受任者調整、いわゆるマッチングということも考えているようである。このような地域の支援には、専門職の積極的な関与も期待される。申立て前の支援が充実することによって申立て前に適切な候補者を立てることができるようになると、予想外の選任結果ということは少なくなる。その結果、制度を利用しやすくなるのではないかと期待される。
また、専門職の役割について、広く国民の理解を得ることも非常に大切なことと考えている。そのためには専門職後見人に期待される役割が何であるか、あるいは専門職を選任することでどんなメリットがあるかについて、いま一度整理して、頼んでよかったと思ってもらえるような制度にしていくことが必要であると考えている。
したがって、単に数字の面で親族後見人の選任割合を高めるべきだという問題ではない。むしろ、家族の在り方や地域とのつながりなどの社会状況の変化もあるので、今後ますます専門職の役割は大きくなるものと考えている。
3 中央での打合せ
後見人等選任の在り方に関しては、日弁連をはじめとする三士会の中央と、最高裁の家庭局が参加して、特に平成30年6月以降、打合せが行われていると聞いている。
この打合せには東京家裁は参加しておらず、その中身について詳しく伝えることは難しいが、後見人等選任の在り方について、専門職が選任されるのはどのような場合か、選任されるときは後見人と監督人のいずれの形態をとるのか、あるいは逆に親族後見人が選任されるのはどのような場合か、また、専門職に期待される役割について、意見交換がされたと聞いている。
4 後見人選任のイメージ
後見人等は1人でなければならないわけではなく、今の法律では複数選任も可能であり、いろいろな選任パターンがあり得る。親族後見人のみを選ぶ場合。親族後見人に監督人を付すという場合。親族後見人と専門職後見人の複数選任の場合。複数選任の場合の中には権限分掌をする場合としない場合がある。専門職後見人だけを選任する場合。専門職を後見人として選んだ上で更に専門職監督人を付す場合。それぞれが複数、例えば、親族後見人が複数、専門職後見人が複数という場合もある。
専門職について、東京家裁の後見センターでは、弁護士や司法書士、社会福祉士などの有資格者のうち、専門職団体から家裁に提出された後見人等候補者推薦名簿の登載者を専門職としている。弁護士であれば当然に専門職ということではない。また、監督人について、家裁が専門職の中から選任することにしているので、原則として自薦の監督人を認めていない運用をしている。
申立て後選任までの検討すべき事項については、全てを説明することは非常に難しいが、まず本人のニーズや課題が何であるかを確認することが選任に当たって非常に重要なポイントになると考えている。ニーズや課題というのは、例えば、財産管理面では、遺産分割や相続放棄、あるいは不動産などの資産の売却、不動産賃貸の管理、自宅改修工事、あるいは日常的な通帳管理なども含まれると思われる。中には訴訟対応、調停対応もある。身上監護面では、施設入所契約や介護サービスの契約などが考えられる。事務の分掌をする場合には、財産管理と身上監護という大きな区分けをすることが多いが、財産管理と身上監護は完全に切り離せるものでもなく、密接に関連していることも多い。例えば、施設入所契約も、施設で生活するという身上面のことでもあるが、当然、費用が掛かるので財産管理面にも関連する。いずれにしても、どういったニーズ、課題があるかということは専門職関与の必要性を検討するに当たっての考慮要素になる。
それから候補者として親族等の候補者がいるかを確認する。確認といっても、申立書の候補者欄に誰が記載されているかを見るということで、最近は専門職の候補者が自薦という形で申立てるケースも非常に多く、その場合にわざわざ裁判所から親族の候補者を立ててくださいと言っていることはまずない。候補者欄が空欄の場合もある。その場合、家裁に一任する趣旨か、単なる記載漏れかが分からないことが多いので、裁判所から申立人、あるいはそのほかの親族の中に候補者がいるかという形で確認することはある。候補者がいない、家裁に一任ということであれば、最初から専門職を選任する前提で手続を進めることになる。
親族等の候補者がいる場合でも、親族等を選任することが相当でない事情がある場合には、いくら有能であっても、その親族は選任せず専門職を選任することが相当と考えられる。親族等を選任することが相当でない事情の典型例は、本人の財産管理や身上監護について親族間に対立があり、親族を選任するとトラブルになることが予想されるようなケースである。親族間の対立が非常に大きい場合は、仮に候補者が専門職であっても、特定の親族から依頼を受けた専門職であるというだけで反発されることがあるので、いずれの親族からも委任関係にない第三者的な立場の専門職を選任することが相当とされる場合が多いと思われる。
親族間対立がある場合のほかには、本人が親族等から虐待を受けているようなケースで、特に虐待が疑われる親族を選任することは相当でないと考えられる。関係機関と連携して適切に対応する必要性が高く、非常に難しい対応も予想されるので、通常は専門職の選任が相当と考えられる。
そのような困難な事情がなく、かつ、親族等の候補者がいる場合は、その候補者が本人のニーズや課題に対応できるかという観点からその相当性を検討することになる。これについては様々な視点が考えられるが、本人のニーズや課題が専門性の高いものであるとか、あるいは親族の候補者の能力や適性から対応が難しいと思われる場合には、専門職を後見人として選任する方向になる。親族等の候補者が、難しい課題は無理だけれども、通常の後見事務は対応ができる場合には、親族と専門職の複数選任ということもある。
難しい課題があるなら、そもそも専門職のみの選任でいいのではないかという考え方もあり得る。しかし、利用促進基本計画の下で、利用者の中には、知らない人にお願いしたくないという意見があることを考えると、最初から親族を排除するのではなく、親族や本人の納得を得られやすいという観点から、親族と専門職の複数選任にするというのは一つの方法と思われる。その場合に権限分掌するかは、そのニーズや課題の内容や親族の能力などから個別に検討することになる。
親族等の候補者の能力や適性に若干不安な点はあるが、周りの支援があれば何とか対応できるという場合には、親族の候補者を選任した上で、支援的な目的も含めて、専門職を監督人に選任するということが考えられる。
専門職を監督人とするのか、後見人とするのかはなかなか見極めが難しく、特に後見がまだ始まっていない段階で親族の能力、適性を見極めるというのは非常に難しい。将来的に中核機関が整備されて、申立て前の支援も含めて中核機関による支援を期待できるようになると、親族後見人の候補者を単独で後見人に選任できるようになることもあり得ると思われる。
不正行為防止の必要性が高いと考えられる事案では、親族後見人を選任した上で監督人を選任することが考えられる。不正行為防止の必要性についてはある程度類型的に考えざるを得ず、非常に抽象的な言い方になるが、財産が多額、複雑で信託等を利用しないケースが典型例である。
また、本人と親族候補者との間で継続的な利益相反関係が生じるような場合には、監督人を選任したり、複数後見にすることも考えられる。
親族等の候補者の中には、信託や監督人選任について裁判所から説明すると、疑われて心外だと非常に怒る方もいるが、不正行為防止の必要性については、ある程度類型的に同じようなケースで同じように対応するという方針で臨んでいる。
5 専門職の関与を必要とする事案と専門職に期待する役割
専門職の関与を必要とする事案として、まず、後見人について見ると、親族間対立があるケース、あるいは虐待事案がある。
親族間対立があるようなケースでは、専門職後見人にはとりわけ後見事務の中立性や透明性が求められる。あるいは本人の権利擁護のために親族間の意見の調整をしなければならないという場面もあるかと思われる。親族間の意見調整は、調整自体が目的ではなく、飽くまで本人の権利擁護のために必要な限度でということではあるが、専門職、特に弁護士の役割は非常に大きい。虐待事案においても、虐待者からの隔離や本人の保護が専門職に期待される役割になると思われる。
専門性の高いニーズや課題がある事案で専門職後見人が選任された場合には、専門職の高い知見を生かした課題解決が期待される。法律的な課題であれば、法律家である弁護士等の活躍の場面であり、本人の障害特性や生活環境に応じた福祉専門職の福祉的な知見を生かすという場面もあるかと思われる。親族後見人の不正が発覚した事案で、後任の後見人として、不正の調査報告あるいは被害回復の手段の検討のために専門職が選任されることもある。
監督人については、不正行為防止の必要性から選任されるのが典型例であるが、後見人への支援が求められるというケースもある。民法の規定から監督人の事務として後見人の支援が直接導かれるわけではない。ただ、監督人は後見人の事務を監督することについて善管注意義務を負っており、後見人が適切に後見事務を行っていない場合には必要な助言、指導をして、後見事務を適正なものにする必要がある。それができないと監督人自身の善管注意義務を問われる可能性もある。また、急迫な事情がある場合には監督人が自ら必要な処分を行って、後見事務に介入するという、民法851条3号の規定もある。これらの観点から監督人には後見人による適切な事務遂行のために後見人に対する指導、助言という形での支援を求めることができると考えられる。
6 後見開始後における選任形態の見直しについて
後見人の交代について、これまでも後見人自身の病気や転居などやむを得ない事情があれば、後見人が辞任して、別の後見人を選任することはあった。
それ以外に、本人の抱えるニーズや課題の変化、あるいは後見人の状況、後見人への支援の有無、固有資産の変化など、後見事務を遂行していく中で状況が変わってくることがある。そのような場合にはその状況の変化に応じて、これまで専門職が関わってきたが今後は親族にスライドしていく、あるいはその逆のパターンなど、これまで以上に柔軟に考えていく必要があると思われる。
例えば、親族から専門職の選任に対して非常に強い抵抗を示されることがある。特に
「報酬が高い」と言われることがあるが、「課題が解決するまでの短期間ですよ」と言うと、それだったらお願いしたいということで納得を得られるケースもある。状況が変わったら選任の形態も変わるという形で柔軟に考えていくことは、利用促進という観点からもあり得る話と思われる。
7 後見人選任に関する質問について
(1)複数後見について家裁の考え方に変更はあったかという質問について
特に変わってはいない。専門職が複数というケースでの質問をいただいたが、複数選任を制限するということはなく、その運用についても特に変わっていない。ただ、選任の在り方についての説明のとおり、選任に当たり様々な要素を考慮しており、申立ての際に後見人等候補者を複数とする理由が分からない場合には裁判所からお尋ねすることはあり得るので、御了承いただきたい。
(2)申立人の意向はどの程度反映されるのかという質問について
先ほどの選任の在り方についての説明のとおりであり、これをもって申立人の意向が案外反映されていると感じるか、あるいは意外と通らないと思うかというところである。親族対立が激しい事案で、親族の申立人が自分を選任してほしいと考えていても、希望が通る見込みは低い。そういうケースでは申立人の意向などを全然聞いてくれないと感じるかもしれない。他方で、特に大きな問題がなく、親族で十分対応できるということで親族の候補者がそのまま後見人として選任されるケースも非常に多くある。そういうケースでは、申立人の意向が尊重されたと感じるものと思われる。いずれにしても、立候補が前提なので、やりたくないと思っている親族が突然押し付けられることはない。
(3)本人の流動資産額がいくらぐらいなら監督人が選任されるかという質問について
昨年度も同趣旨の質問があり、そのときの回答と全く変わらないが、改めて申し上げると、資産が高額であるという理由で監督人を選任することについては、後見人が専門職か専門職でないかによって違いがある。専門職でない親族後見人や名簿非登載の弁護士等の場合は、管理財産のうち流動資産が1000万円以上あり、かつ、信託等の利用がない、あるいは信託等の利用に適さないという場合には原則として監督人を選任している。このことについては後見サイト等でも公表している。他方、専門職である弁護士、司法書士、社会福祉士等が後見人である場合については、その専門職団体で研修を受けて、その専門職団体から事実上の監督を受けているので、流動資産が1000万円以上であるということから直ちに監督人を選任するという運用はしていない。どのような場合に選任するかについては個別判断であり、1000万円を超えてかなり高額となっているケースにおいて、様々な事情を勘案して選任している。なお、金額の目安は現在、公表していないので、御了解いただきたい。
(4)選任の場面で弁護士と司法書士の振り分け基準はあるのかという質問について
候補者一任などで裁判所が推薦団体へ依頼をかける場合に、依頼先は弁護士なのか司法書士なのか、そのほかの専門職なのかは、先ほどの選任の在り方の説明のとおり、本人のニーズや課題などに応じてということになると思われる。特に複雑な法律問題があるか、親族間で紛争が非常に激しくその調整が難しいという場合には、弁護士とすることが多いと思われる。もっとも、そうすると弁護士会には難しい案件しか回らないことになってしまうので、いずれの専門職でも対応できる場合はなるべく偏らないようにということでお願いをしている。明確な線引きは難しく、後見等開始後に司法書士から弁護士に交代するケースもある。後見人の交代についてはそれがよりよい後見制度の運用につながるものであれば、柔軟に対応するつもりでいるので、御相談いただきたい。
基本計画を踏まえた報酬付与の在り方
1 報酬付与の法的根拠と性質
報酬についても選任の在り方と併せて中央 で意見交換がされていると聞いている。ただ、東京家裁として参加しておらず、今後、具体的な検討は最高裁の方から情報提供を受けた上で行うことになると思われるので、現時点ではあまり具体的なことはお話しできないが、入り口のところだけ少しお話ししておきたい。報酬付与については、民法862条に根拠条文 がある。この条文の趣旨については「注釈民法」や「コンメンタール」などで書かれており、後見人の公益的、社会福祉的な性格から本来は無償が原則であるが、後見事務はかなりの負担を伴うものであることから、相当な報酬を支払うことが妥当なことも実際上はあるので、こうした規定が設けられたということが説明されている。
報酬は後見人の当然の権利ではなくて、家庭裁判所の裁量によって付与されるものであり、不服申立てはできない。
2 これまでの報酬付与の在り方と問題点
これまでの報酬の在り方について、後見人が1人だけ選任されていて、監督人が選任されていないという例で説明する。
報酬自体は基本報酬と付加報酬という2つの大きいカテゴリーに分けて考えている。
基本報酬は通常の後見事務を行った場合の報酬で、月額2万円が目安だが、管理財産が高額である場合には流動資産額に応じて2万円から6万円の範囲で決まる。付加報酬は特別困難な事情がある場合や特別な行為をした場合の報酬で、その内容に応じて裁判官の裁量で付加しているが、おおむねこれも利益額に応じたものになっている。
以上のような報酬の体系は、基本的に財産管理を中心としたものになっている。流動資産額あるいは得た利益の額に応じて変わるということで、身上監護面があまり適切に反映されていないのではないかという問題点がある。
基本計画の中で、これまで財産管理面を中心に考えていたが身上監護面も重視していくべきと言われているにもかかわらず、報酬は相変わらず財産管理中心のままでよいのかと、現在、議論になっている。
3 様々な意見と課題
報酬の在り方には、様々な意見がある。そもそも特に身上監護面の後見事務を類型化すること自体が非常に難しく、金額についても、高すぎるとか、逆に安すぎるという両方の意見がある。今ここで、報酬の水準を変えるという話をしているわけではないが、体系を変えるという話になると、高い、低いという意見は出てくるところではある。
また、報酬付与をあまり細かく個別に見ていくという話になると、事務が大変になるということもある。申立てをする後見人側も非常に大変と思われるが、裁判所では現時点でも相当数の報酬付与の審判を行っており、それを効率的にやっていくこともある程度考えなければならない。
そのほか、利用者側から、あるいは後見人の側にとっても、報酬額の目安がないと困るという意見もあり、いわゆる無報酬案件に対する対応が先決ではないかという意見もある。
4 中央での意見交換と今後の予定
中央では、なぜ今、議論するのかの確認、あるいは後見事務の整理、類型化について、意見交換がされたと聞いている。今後、目安をどうしていくのか、具体的に申立書式がどうなるのか、事務フローがどうなるのか、どのように周知していくのかなどが検討課題であると考えており、裁判所の判断事項ではあるが、弁護士会からも御意見を伺い取り組みを進めたいと考えているので、御協力をお願いしたい。
裁判所からのお知らせ
後見制度支援預金について
平成30年6月1日から後見制度支援預金の取扱いが開始され、現在、東京都信用組合協会加盟の金融機関12団体、東京都信用金庫協会加盟の金融機関24団体が取扱いを行っている。全国的に見て運用は拡大傾向にあり、今後も更に拡大が見込まれる。
基本的な仕組みは後見制度支援信託とほぼ同じであり、口座の開設をする際に、解約や入出金の取引をするときは家庭裁判所の指示書を要する旨の特約を同時に付すことになる。信用組合においては、支援預金口座とは別に、同口座を開設した店舗において普通預金口座も開設する必要があるが、既に同じ信用組合の同一店舗に普通預金口座を有している場合はそれを利用することができるので、その場合には新たに普通預金口座を開設する必要はない。支援預金においても、支援信託と同様、一時送金及び定期送金の設定が可能であるが、システム上の理由により定期送金の設定をすることができない金融機関があるので、金融機関の選定に際しては留意されたい。
当庁管内で支援預金の取扱いが開始された時点では、支援預金の取組を行っている家庭裁判所も少なかった。そのため、東京家裁管内にいた本人(及び後見人)が地方に転居して、その後の後見事件の監督は転居先の家裁が行う場合に、それまで利用していた支援預金を使うことができるか否かが不明確であり、一度解約していただく可能性がある旨を説明していた。しかしながら、支援預金は全国的な取組となりつつあり、今後もますます取扱いが拡大していくことが見込まれるので、他の家庭裁判所においても、指示書を出さない等の対応をすることはないと考えられる。したがって、支援信託か支援預金かを選択するに当たっては、将来的な移転が見込まれる場合でも、少なくとも裁判所から解約を求められるリスクを検討していただく必要はないと考えている。
NIBEN Frontier●2019年8・9月合併号


