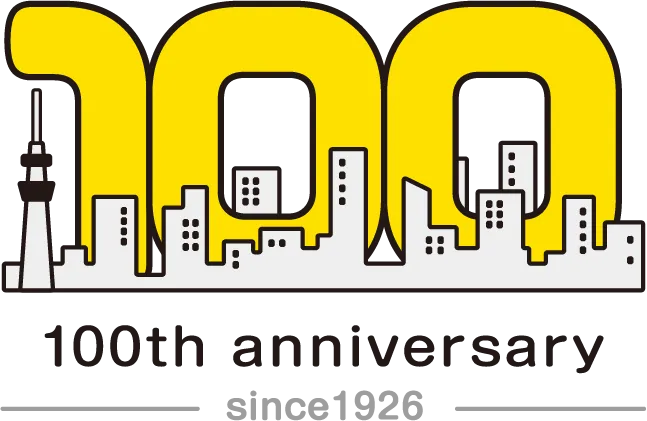山椿

菅野 茂徳(41期)
●Shigenori Kanno
以前本 誌(2016年1・2月合併号)の「この一冊」に執筆させて貰ったとき、その冒頭で「現在の趣味は、読書と美術鑑賞」と書きました。そこで今回は「芸術の秋」にちなみ、私の拙い美術鑑賞の仕方をご紹介しようと思います。俗に身を滅ぼすものとして「ノム・ウツ・カウ」がありますが、この「カウ」には色々あるようで、その1つに骨董品(美術品)があります(某テレビ局の「なんたら鑑定団」という番組を一度見ていただければ、世の多くの人がいかに美術品に散財しているかがよく分かります)。私は一度も美術品を購入したことはありません(というか、散財する程の財が無いというのが実情です)。そこで専ら美術館・博物館での美術鑑賞となります。この際私は勝手に「私のために美術品を丁寧に保管し展示してくれている」と思い込み、一人悦に入って美術品を眺めています。特に、平日昼間の公立美術館に常設展示を観に行くと、時によっては当該フロアに私1人ということもあり、まさに「お大尽」気分に浸れます。そして公立美術館の常設展示なら「地域住民に対する文化の提供」というお題目もあって入館料も数百円と極めて低額なことが多いのです。しかし、そんな美術館でも常設展示している所蔵品のレベルは高く、重要美術品・重要文化財、時には国宝が無造作に陳列されていることもあります。
このような楽しみ方は、仕事で地方の裁判所に出張した際、できるだけ事務所に戻って仕事をしないためによくやります(ちなみに、地方と言ったら怒られますが、大阪地裁の川向こうにある大阪市立東洋陶磁美術館には国宝の「飛青磁花生」や「油滴天目 茶碗」が常設展示されています)。
他方、東京都内では上野の東京国立博物館(トーハク) や竹橋の東京国立近代美術館が横綱級でしょう(トーハク本館2階国宝室では毎年1月上旬、長谷川等伯の「松林図屏風」が展示されます)。
しかし、上野や竹橋では「出張」と言い訳することもできません。そこでこの場合は事務所のある築地と弁護士会館・裁判所のある霞が関との行き帰りにちょっと「寄り道」することになります。私は日頃の移動はできるだけ歩く(ウォーキングする)ことを心がけており、築地・霞が関間もウォーキングコースにしています。そこで私がよく「寄り道」するのは、私立であり常設展示はありませんが、帝劇ビル9階にある出光美術館と丸の内の三菱一号館美術館です。
出光美術館は出光興産創業者の出光佐三翁が収集した東洋の書画・陶磁器が中心です(ここにも国宝の「伴大納言絵巻」があります)。他方、三菱一号館美術館は19世紀の近代西洋美術が中心で、ラファエロ前派、ルドン、ナビ派の展覧会をよくやっています。これらは私立ですので入 場料はさすがに「数百円」とはいきませんが、裏技があります。数千円の年会費を支払い会員になると、1年間有効(かつ同伴者1名も無料で1日何回でも入場可)のパスが貰えるのです。これさえあれば「あの絵だけを20分観に行こう」という贅沢もし放題です。皆さんも是非その目で美術品を観て「心の洗濯」をしていただければと思います。