非上場会社の株価算定の実務 後編 全3回
後編 全3回
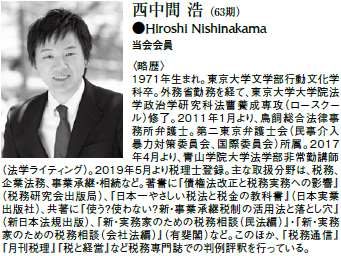
1.相続税法上の時価
(4)特例的評価方法(財産評価基本通達188 ~ 188-2)
前号では原則的評価方式について説明しましたが、これとは別に特例的評価方法というものもあります。財産評価基本通達の188から188-2に書かれています。
①同族株主以外の株主等が取得した株式の評価(通達188-2)
この方式は、「取引相場のない株式(出資) の評価明細書」の第3表「一般の評価会社の株式及び株式に関する権利の価額の計算明細書」の下から2段目の「2. 配当還元方式による価額」のところに入力していけば算定できるようになっています。
計算方法は次のとおりです。
直前期・直前前期平均
(非経常的なものは除く。)← 過去のデータ
÷ 1株当たりの資本金等50円とした場合の株式数(2円50銭(5%配当)未満なら2円50 銭、配当5%未満なら5%と仮定。)
÷ 10%(還元率10%で割戻し、つまり10倍。)
× 1株当たりの資本金等(別表5(1))/50円
まず直前期と直前前期の平均配当額を抽出します。その際、記念配当などの非経常的な配当は除き、通常の配当の平均を取ります。それを1株当たりの資本金等を50円とした場合の株式数で割ります。その数値が2円50銭、これはすなわち5%配当を意味するのですが、5%配当未満の場合は2円50銭で計算します。ですから、配当がゼロでも5%は配当をするという前提で計算するということを意味します。
それを10%で割り戻します。すなわち、10 倍するわけで、10年間は同じような金額をもらえるという前提に立っています。それに50 円で割った1株当たりの資本金等を掛けて元に戻します。要するに、5%配当以上だったらその数字を使って、5%未満なら5%を使って配当の10年分を見るということです。
実際には配当ゼロの中小企業が多いのですが、ゼロの場合は2円50銭の数値を使うことになり、最終的には1株当たりの資本金等の額の2分の1の金額になります。したがって、資本金等として資本金しかない会社の場合、1株当たりの資本金の2分の1の金額が1株当たりの配当還元価額ということになります。これは純資産や類似に比べればかなり低い金額です。
②通達188
この低い金額で株を評価できるのは誰かというのが通達188に書かれています。この通達188の解釈を巡っては争いが多く、この要件を満たすべくいろいろな努力をしている中小企業側と、租税回避的な適用を許さない国税庁側でもめることの多いところです。
ア 通達188(1)
まず、通達188(1)では、「同族株主のいる会社の株式のうち、同族株主以外の株主の取得した株式」についてはこの低い金額で評価できると記載されています。株主グループというのをつくって、その株主グループがそれぞれ持っている議決権数が30%以上だと、そのグループに属する株主は「同族株主」となります。ただし、その株主グループの中で50%超のグループが含まれている場合は、50%超のグループに属する株主だけを「同族株主」といいます。すなわち、過半数を持っているグループがあれば、そのグループだけが「同族株主」となり、過半数を持っているグループがなければ、30%を持っているグループが「同族株主」ということになります。
そういう株主のいる会社の株なら、同族株主以外の株主が取得する株式は全部配当還元価額で評価してよいというのが通達188(1)です。そこで株主グループといった場合にどの範 囲を指すのかということがかなり重要で、その範囲は法人税法施行令4条に書かれています。まず、同条1項に「特殊の関係のある個人」として1号から5号まで規定されています。代表的なのは1号の親族(6親等内の血族、配偶者、 3親等内の姻族)です。2号は、事実婚状態にある方で、3号が使用人です。使用人というと、例えば株主が社長の場合、その会社の従業員もここでいう使用人に該当してしまうのかと思いがちですが、そうではなく、ここでは社長個人が私用で雇っているタクシー運転手等の使用人のみを指し、会社の従業員は含みません。
また、同条2項は「特殊の関係のある法人」について規定しています。これは中心となる株主が「他の会社を支配している場合」にその「他の会社」が該当します。「支配している場合」とは、発行済み株式の総数の100分の50を超える数を持っている場合がこれに当たります(同条3項)。これは直接支配している又は兄弟会社、孫会社など、とにかく支配していればよいという形になっています。
支配しているかどうかを見るときに、同じ内容で議決権を行使するという合意をしている者があれば、その者も含んで判定するというのが同条6項の規定です。
これは特殊の関係があるかどうかに関する規定ですが、この規定を特殊の関係があるかの判定以外のところで使えないかということで争いになったのが、東京地判平成29年8月30 日判決(TAINS Z888-2122)です。この判決では、前述した同族株主30%以上のところでもこの規定が使えないのかという点が争われたのですが、これは特殊の関係のある法人を見るときの規定にすぎないと判示されました。
イ 通達 188(2)
続いて、通達188(2)では、「中心的な同族株主のいる会社の株式のうち、中心的な同族株主以外の同族株主で、その者の株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の5%未満であるもの」とあります。同族株主であっても、例外的に配当還元方式による評価を認めるというものです。
中心的な同族株主とは何かというと、「課税時期において同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含む。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主」をいいます。「同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1 親等の姻族」とあり、先述のグループ株主の範囲より狭くなっています。
この「中心的な同族株主以外の同族株主」についても例外があり、これもまた重要です。同通達では括弧で「課税時期において評価会社の役員(社長、理事長並びに法人税法施行令...に掲げる者)...を除く」と記載されています。要するに、社長、理事長、代表取締役、副社長、専務、常務、それに類する人たちや、会計参与、監査人、監事等は含まれません。例えば、同族だけれど中心的な株主ではないから5%未満の議決権で安心だと思っていたのに、実は会社の役員をやっていましたとなると大変なことになるので、ここまで注意を向ける必要があります。
ウ通達188(3)、(4)
配当還元方式による評価が使えるケースがあと2つあります。(3)は、同族株主がいない会社の株主のうち課税時期において株主の1人及び、その同族関係者の有する議決権の合計数が15%未満である場合です。同族株主がいない場合は15%未満の取得まで配当還元で算定してよいとされています。
(4)は、中心的な株主(単独で10%以上の議決権を有する株主)がいて、かつ同族株主がいない会社において15%以上を取得するグループに自分が入っていたとしても、中心的な株主でないなら配当還元でよいというものです。ただし、ここでも前述した役員は同じように除かれます。
(5)特定の評価会社の株式(財産評価基本通達189 ~ 189-7)
次に、特定の評価会社の株式について説明します。ここでは、前述した比準要素1や、株式等保有特定会社が出てきます。いずれも原則として純資産価額だけで評価しなさいとされています。
実務でもよく出てくるのが土地保有特定会社です。不動産を持っている個人事業主が会社をつくったというような場合です。土地保有特定会社になると純資産価額しか使えません。純資産と類似の評価を比べると、純資産は類似の2倍以上高くなりがちです。したがって、類似が使えた方が株価は下がるのが一般的です。純資産しか使えないということは、株価が2倍以上高く付いてしまうこともあることを意味します。そこで、こういう会社の場合は土地保有特定会社に当たらないようにするのが重要な課題となってきます。
土地保有特定会社の土地の相続税評価額が総資産の相続税評価額の何割を占めているのかという基準で判定します。大会社だと70% 以上、中会社だと90%以上を占めると土地保有特定会社に該当することになります。
(6)種類株式の評価
次に、種類株式の評価について説明します。種類株式の株価評価については国税庁の資産課税課が出している平成19年3月9日付「種類株式の評価について(情報)」というものがあります。
①配当優先株式
まず、配当優先株式の場合、類似業種比準方式の算定は種類ごとに配当金を分けて、その配当金額に基づいて評価します。
次に、無議決権株の場合、議決権の有無を考 慮せず評価するよう記載されています。ただし、一定の条件を満たせば5%控除してよいとされています。しかも、ほかに議決権付きの株式を譲り受けていれば、5%を引いた額をその株の取得価格に加算してよいとされています。なお、税務はこのように議決権を5%の評価 で見ているのだから、会社法での時価の算定においても議決権は5%で評価してよいかというと、これは租税法独自の考え方であり、会社法ではそのまま使えないというのが専らの評価です。
無議決権株で5%を控除できる一定の条件としては3つありますが、実質的に重要なのは「当該会社の株式について、相続税の法定申告期限までに、遺産分割協議が確定していること」です。
②社債類似株式の評価
注意してほしいのは社債類似株式の評価についてです。株式であっても、一定の条件に該当する場合は社債と同じ評価をすることになります。種類株を設計ミスするとこの社債類似株式に当たるとされ、かなり高い評価になる危険性があるということです。
例えば、優先配当額を決めて、配当しないときはそれを累積して必ず払うような形で設計されている、しかも優先配当額を超えて配当しない設計であったり、発行価格を超えて分配は行わず、償還するときも発行価格で償還するといった形になっていたりすれば、社債と同じような感じになってきますので、社債として評価することになっています。
株式の分散を防ぐために種類株式を導入することが事業承継の提案の中ではよくなされますが、出し惜しんで、発行価格で償還する形にしてしまうと、社債類似株式に当たる可能性が出てくるので、注意が必要です。
③拒否権付株式
最後は、拒否権付株式、いわゆる黄金株です。これは「普通株式と同様に評価する」とあります。
実務的な感覚としては黄金株が本当に普通株と同じ評価でよいのかという疑問もあり、もしかしたら、将来黄金株については評価が変わってくる可能性もありうると個人的には思っています。ただ現在の国税庁の考え方は「普通株式と同様に評価する」とされています。
2.法人税法上の時価
ここまで相続税法上の株価の算定の話をしてきましたが、法人税法上の時価が問題になったときは調整が必要になります。法人が株を譲渡した場合、法人が株を譲り受けた場合等に問題になってくる時価が法人税法上の時価です。
法人税法基本通達4-1-6の(1)をみてください。「中心的な同族株主」に該当するときは「小会社」に該当するものとして計算するとあります。相続税法上の株式の評価では、会社を大会社、中会社、小会社と分けて純資産と類似の折衷割合を出すのですが、法人税は、株主が中心的な同族株主の場合は必ず小会社として評価するとなっています。小会社ではL の割合が0.5です。相続税法上の評価では大会社に当たる会社でも法人税法は小会社になるので、類似を勘案できるLの割合が下がり、株価はほとんどのケースで上がります。したがって、法人税法上の株価は相続税法上の株価より上がりがちです。株はできるだけ法人ではなく個人に渡した方が、税金上はお得というのはここに由来しています。
次に、同通達の(2)です。当該株式の発行会社が、土地(土地の上に存する権利を含む) 又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは純資産価格の計算に当たっては、時価によるとあります。つまり、純資産価格方式で算定するときに土地と上場株式は時価で評価するということです。
さきほどの相続税法の時価算定の場合は、土地は路線価でよいとされていました。路線価はだいたい時価の8割未満なのですが、法人税法上の時価を算定するときには路線価を時価に直す必要があります。
大きな違いの最後は、評価差額に関する法人税額等に相当する金額は控除しないとされている点です。これは、相続税法の時価のところでホールディングスをつくり株価上昇を抑えるという方法は、法人に株式を譲渡する際には使えないということを意味します。
3.所得税法上の時価
次に、所得税法上の時価について説明します。個人が株を法人からもらい受けた、個人や法人に売ったというような場合の株価の算定方式です。
まず大前提として、個人が個人に対して株を売った場合、実際に入ってきた売却金額で所得を計算してよいのですが、個人が法人に対して売却した場合は、売却価格が時価の2分の1未満だと時価で売却したものとして所得税を算定するという条文が所得税法59条1項、2 項にあります。もっとも、2分の1以上で売った場合でも租税回避目的があれば否認して時価換算できるといった通達がありますので注意が必要です。このように所得税法上は個人に売るか、法人に売るかで算定が全く異なってきます。法人に低額で売った場合は必ず時価が問題になるというところを最低限押さえていただければと思います。
5.ケース別問題点
最後に、よく実務で問題になるケース別に論点を整理して説明します。
1.少数株主からの支配株主の買取り(締め出し)
(1)価格交渉
少数株主からの支配株主の買取りの場合に価格交渉段階でどういった価格が用いられるかというと、譲渡する側はできるだけ高く売りたいのでDCF法を使いたいところです。ただ、少数株主は対象会社の事業計画まではつくれないことが多いので、つくれないとなると、収益還元法を使うしかありません。もっとも、収益還元法で計算するにも会計士や弁護士に算定を依頼するとかなりコストがかかってしまいますので、通常は中小企業の少数株主がそこまでコストをかけて算定することはありません。
譲り受ける支配株主側はというと、当然安い価格を希望して、さきほど説明した通達に従った国税庁方式による算定価格を軸に買取価格を提案することがほとんどです。支配株主側についた税理士やコンサルティングの方は、税務上の評価価格で買い取ると税金の問題が発生しないのでお得ですといった形で少数株主を説得することが多くなってきます。ところが相手方に例えば弁護士がついたら、時価が国税庁方式に落ち着くわけがないということをご存知なので、すんなりとはいかないことになります。
ただ、さきほども申しましたように中小企業においては、通常は少数株主がコストをかけて会計士や弁護士に算定を依頼することはないので、実務ではだいたい税理士が間に入り、国税庁方式を軸に買取価格については解決することが多いです。よくあるパターンとしては通達上の例外的評価方式である配当還元価格方式での評価額に少し色を付けて買い取るというものです。もともと、なぜその人が株を持っているのかというと、昔の商法では7名以上の株主が必要だったため、社交や義理で株主に名を連ねたということが多く、そういった方々に対してこれまでありがとうございましたという意味も込めて少し色を付けて買い取るといったケースですね。
(2)合意価格の場合の税務問題
当事者が税務上の時価よりも低い価格で合意した場合、例えば本当は税務上、原則評価するところを当事者間で例外的評価に近い価格で合意してしまった場合、当然税務上の問題が出てきます。裁判所も第三者間取引以外の取引で合意された金額をそのまま税務上の時価とみなすことはありませんので、取引をする際には、合意価格をいくらにするかという問題とは別に、税務上の時価はいくらになり合意価格でやりとりをしたら税金がどれくらい発生するかということを事前に考えなくてはなりません。
譲受人が個人で、譲渡人が個人の場合には、相続税法上の時価と差のある価格で売買をした場合、相続税法7条の規定により、その差額分は贈与があったとみなして譲受け側に贈与税を課すとなっています。そのときの時価をどう評価するかについては、相続税法22条にありますが、そのときの現況によるとしか記載されていないため、実務上は通達によって処理されています。
この通達に対しては、特別の事情がない限り、相続税法上の時価は財産評価通達に定める評価方式でよいと判示している裁判例があります(東京地裁平成19年1月31日税務訴訟資料257号順号10622)。したがって、裁判所もこの財産評価基本通達の評価方式には一定の評価をしていることが分かります。ただし、「特別の事情が認められない限り」といった一定の留保がつけられていることから、どういった場合がこの「特別の事情」として認められるかを巡っては争いが繰り広げられてきました。
2.贈与税・相続税
財産評価基本通達によらないことが正当とされる特別の事情
特別の事情がある場合とは、一般論としては「評価通達に定められた評価方式を形式的に適用するとかえって実質的な租税負担の公平を著しく害するなど、右評価方式によらないことが正当と是認されるような特別の事情がある場合」といった言い方がされています。これが認められた具体例としては、将来純資産価格の売却が約束されている場合があります。価格について約束している以上はこれと異なる配当還元方式による買取りはおかしいということで純資産価格が税務上の時価とされたケースです。また、配当還元方式で評価できる場合に、通達にあるような10%の資本還元率、10年分という評価はこのケースではおかしいということを立証できた場合は、別の算式で算定した価格を税務上の時価としてよいということをにおわせた平成17年の東京地裁の判決があります(東京地判平成17年10 月12日税務訴訟資料255号順号10156)。
ほかには、取引先が数パーセントずつ保有し、ぎりぎり同族関係者以外であった場合が挙げられます。この場合は実質的には同族関係者として原則評価が税務上の時価にふさわしいとした判決があります(東京地裁平成16 年3月2日TAINS Z254-9583)。
このように、裁判所では、租税回避的な価格算定方法は、ここでいう特別の事情の中に読み込まれて通達とは異なる評価に変えられてしまうといった傾向をみてとることができます。


