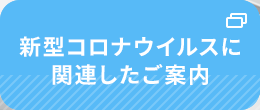この一冊 vol.142『孟嘗君』
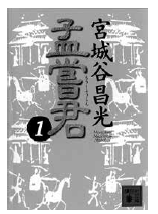
『孟嘗君』
宮城谷 昌光 著 講談社文庫
娘が通っている幼稚園のイベントに「親と子の同時礼拝」というものがある。礼拝 では、聖書の一節を引用し、園長先生でもある牧師さんが説教をしてくれるが、その内容は生き方に根ざした身近な事柄についての話がほとんどであり、不信心者の私は、
「聖書は生き方を示す」と説いていると理解している。
今回ご紹介する『孟嘗君』は、私にとっての聖書である。題名にもなっている孟嘗君は、中国の春秋・戦国時代の戦国四君の一人に数えられ、「鶏鳴狗盗」の故事で知られる。『枕草子』の一首と 絡めてご存じの方も多いかもしれない。
物語は「夏の落日である。夕陽が邸内に射した。ななめの光は、はげしくもするどくもなく、なぜかしずかに降るようであり、その光にふくまれている赤の光が槐の葉や幹をやわらく染めた。」(一巻7 頁)という一文で始まる。初めて読んだ時、「夏の落日」を何と美しく言語化するものだろうかと感動したのを覚えている。主人公の孟嘗君は、実父であり後に斉の宰相となる田嬰に、「5月5日に産まれた子は家に災いをもたらす」との理由で出生後間もなく殺されそうになったところを、 母親によってひそかに逃される。縁あって風洪という無頼者に養育され、諸国を旅するなかで成長し、13歳の時に田嬰の下へ戻り、最終的には父をもしのぐ天下の宰相に登り詰める。この一大歴史大河ロ
マンともいうべき本作には、商鞅、孫臏、孟軻、屈原、張儀など史上に燦然と輝く偉人達が次々と登場するが、彼らと孟嘗君との接点という意味では、そのほとんどがフィクションであり、同時代を生きた偉人達に独自の個性を与え、彼らを絶妙に結びつけて必然の物語を構築した作者宮城谷昌光氏の創造と時代考証の力には驚嘆するほかない。
なかでも、司馬遷の『史記・貨殖列伝』に商業の祖師と記録される白圭が、本作では孟嘗君の養父として実に魅力的に描かれている。元々、剣と遊興にふけっていた無頼の士であったが、剣を捨てて学問に励み、風洪から白圭と名を変えて商人として大成する。その白圭が孟嘗君に説く。「人を愛すれば、勇気が湧く。人のむこうにあるおのれを愛することを仁という。人のこちらにあるおのれを愛することは仁とはいわず、そこには勇気も生じない。」(五巻72頁)と。作中の孟嘗君が白圭のよう
に生きたいと願ったように、純粋な学生時代の私もそう願った。その衝動も手伝って司法試験を志し、「困っている身近な人を助けられる者でありたい」という思いから弁護士の道を選んだ。もちろん、理想と現実は異なる。やはり自分はかわいいものであり、人のこちらにある己を愛してしまいがちである。白圭のように生きることは容易ではない。だから、初心に立ち返りたいとき、私は本作に戻る。そして、その都度、少なくと も家族との関係では、人のむこうにある己を愛したいと思うのである...が、やはり、それも容易ではない。
当弁護士会会員 内藤 勇樹(59期) ●Yuki Naito