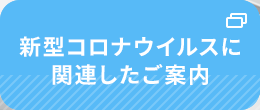病気休職・復職に関する近時の 裁判例の動向と分析(前編)
 石﨑 由希子 ●Yukiko Ishizaki
石﨑 由希子 ●Yukiko Ishizaki
【略歴】
東京大学大学院法学政治学研究科
法曹養成専攻(法科大学院)
2009年~ 東京大学大学院法学政治学研究科 助教
2013年~ 横浜国立大学国際社会科学研究院 講師
2015年~ 横浜国立大学国際社会科学研究院 准教授
CONTENTS
前編
1.はじめに
2.病気休職制度の設計
後編 次号掲載
3.休職事由の消滅(復職可能性判断)
4.リハビリ勤務(試し出勤)
5.おわりに
1.はじめに
高齢化に伴い、疾病を抱えながら働く人の増加が見込まれるほか、職場におけるメンタルヘルス不調の問題も深刻となっています。現代社会においてはそうした状況の中で「病気の治療と仕事の両立」は、国の政策課題であると同時に各企業における経営課題にもなっていると思います。更に、今般の新型コロナウイルスの感染拡大は、病気により仕事を休むということについての社会的関心を高める結果となることが予想されます。
今回扱う病気休職に法律上の定義はありませんが、「私傷病により労務提供不能となった労働者について、比較的長期にわたり労務を免除・禁止すること」と一般的に理解されています。ここで業務上の傷病が除かれるのは、業務上の傷病による療養期間(及びその後30日間)については、労働基準法において、解雇制限が定められており(労基法第19条)、これにより雇用保障が図られているためです。これに対し、民間企業において、私傷病による療養期間について雇用保障を図り、休職制度を設けるべきとする規制は置かれていません。ただし、健康保険からの傷病手当金の支給という形で、私傷病による療養期間(1年6カ月)について所得保障がなされています(健康保険法第99条)。
企業によっては法定外休暇として、病気休暇制度を設けている場合があります。制度の中身に
よっては、病気休職と類似の機能を果たすこともあり得ます。もっとも、休暇という場合には通常、労働者の権利として位置づけられるのに対し、休職については労務を免除するだけではなく禁止する面があること、労働者に不利益を与える側面もあることに注意が必要です。
また、企業が業務命令として発令する自宅待機命令(自宅療養命令)と病気休職発令の違いには相対的な面がありますが、病気休職の場合は比較的長期にわたって就労を免除ないし禁止することが想定されます。そのため、自宅待機命令とは異なり、病気休職の発令に当たっては、契約上の根拠が必要になります。

2.病気休職制度の設計
病気休職を制度として設けるのであれば、就業規則の相対的必要的記載事項になります(労基法第89条10号)。そして、就業規則に規定を設ける場合、定める労働条件は、合理的である必要があります(労働契約法第7条)。
対象者等
病気休職制度の対象者は、基本的には各企業の裁量に委ねられます。独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)の調査シリーズNo.112(平成25年11月)によりますと、48.5%の企業で、非正規労働者に病気休職制度は適用していないということです。
しかし、この点については、非正規労働者と正規労働者との間の格差是正を目的とする均等・均衡待遇規制に抵触しないかに注意する必要があります。つまり、非正規労働者の中でも正規労働者と同視できるような人については、正規労働者に認めている病気休職制度を同じように認める必要があります(短時間・有期雇用労働法第9条)。また、正規労働者と同視できるわけではない場合も、均等・均衡待遇規制との関係で病気休職制度の適用の相違が不合理であってはならないことになります(同法第8条)。「不合理」性の基準は曖昧ですので、どう判断するか難しいところです。
いわゆる「同一労働同一賃金ガイドライン」(平成30年12月28日)には、病気休職についても規定があり、有期契約ではない短時間労働者には、「通常の労働者と同一の病気休職の取得を認めなければならない」としています。他方で有期雇用労働者については、「労働契約が終了するまでの期間を踏まえて、病気休職の取得を認めなければならない」と書かれています。「労働契約が終了するまでの期間を踏まえて」というのがどういうことなのか判然としませんが、ガイドラインでは「問題とならない例」として、「A社においては、労働契約の期間が1年である有期雇用労働者であるXについて、病気休職の期間は契約期間が終了する日までとしている」という例が挙げられています。
この例を具体的なケースに照らして考えてみますと、例えば1年の有期雇用労働者が4カ月勤務
してそこで病気になり、残り8カ月は休職してそのまま契約終了となったのであれば、問題とならないということになるかと思います。しかし、このようなケースで、残り8カ月全部、休職を認めなければ不合理と評価されるか否かははっきりしません。
不合理と言えるか否かは、「待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして、適切と認められる」事情を考慮して判断することになりますので(短時間・有期雇用労働法第8条)、各企業において病気休職制度を行う目的によって結論が異なり得ることになります。
仮に、病気休職とは、長期雇用を前提に、一時的な労働不能について猶予を与える制度であると捉えるならば、長期雇用が前提となっていない有期雇用労働者との間で、特に休職期間の違いを設けることについては、不合理ではないという判断が導かれやすくなります。
他方、労働者の健康保持のため、療養に専念させるための制度だと捉えますと、健康保持は有期であろうが無期であろうが異ならないとして、不合理と判断されやすくなるように思います。
そうしたことを踏まえますと、病気休職の位置付けやその期間、その間の処遇(有給・無給の別)等に係る制度設計を再確認しながら、有期雇用労働者に対する適用を検討していくことが必要になるのではないかと思われます。
なお、病気休職に係る処遇の相違について、短時間・有期雇用労働者に説明をしたり(短時間・有期雇用労働法第14条1項、2項)、労使交渉を尽くしたりしているとの事情が、不合理性が否定される方向に考慮され得る点はその他の労働条件と同様と考えます。
〔付記:大阪医科薬科大学事件・最判令2・10・13労判1229号77頁は、私傷病欠勤中の賃金保障につき、長期にわたる就労が期待される正職員に対して生活保障を図り、その雇用を維持・確保する目的であると認めた上で、職務内容等の相違や登用制度の存在等も踏まえ、勤続期間が2年余りであるアルバイト職員にこれを認めないことも不合理ではないとしています。他方、日本郵便(東京)事件・最判令2・10・15労判1229号58頁は、有給の病気休暇につき、生活保障を図り、私傷病の療養に専念させることを通じて、その継続的な雇用を確保するという目的であると認めた上で、相応に継続的な勤務が見込まれている契約職員との関係で、有給か無給かの相違があることは不合理であるとしています。ただし、同最判は、「病気休暇の日数につき相違を設けることはともかく」としており、日数の設定については使用者に一定の裁量を認めています。〕

期間の長さ
休職期間の長さは、実態としては3カ月から3年超までと様々です。JILPT の前掲調査では、6カ月超から1年未満が最も多く(22.3%)、1年超から1年半未満がこれに次ぐ(17.2%)という状況です。こうしたなかで、期間の長さによって、法的効果に違いが出てくるのかという点が次に問題となります。
この点、就業規則の規定の合理性(労契法第7条、10条)については、休職期間満了で直ちに雇用終了と結び付けられているのか、あるいは休職期間の延長があり得るかなども踏まえて判断されることになります。
ここではっきりしているのは、休職期間として1カ月を下回る期間を設定し、かつその期間満了と自然退職の効果を結び付ける制度設計ですと、30日の解雇予告規制(労基法第20条)の潜脱になるということです。こうした就業規則上の規定については、およそ合理性は認められないでしょう。
反対に、休職期間が1カ月を超えてさえいれば、休職期間満了で自然退職とすることが許されるかと言うと、解雇権濫用規制(労契法第16条)との関係で、そうとも言い切れません。また、逆に、長期間の休職を設けていれば、期間満了で直ちに自然退職にできるのかと言うと、裁判所によって、それだけ長期間待ったのだから、もう少し待てるでしょうという判断を下される可能性もあります(綜企画設計事件・東京地判平28・9・28労判1189号84頁)。
しばしば問題になるのは、メンタルヘルスのケースなど、休職から復帰した後に、病気が悪化して再度休職になったというケースにおいて、前の休職期間と後の休職期間を通算するという規定を入れることの可否です。この点に関しては、メンタルヘルス不調者の復職後の定着の難しさを踏まえて、合理性(労契法第10条)を肯定した裁判例があります(野村総合研究所事件・東京地判平20・12・19労経速2032号3頁)。
もっとも、通算によって休職期間の上限を超えたから常に休職期間満了で自然退職とできるかと言えば必ずしもそうとは言えず、結局のところ、具体的な事情を踏まえて判断されることになると思われます。
通算規定との関係では、同一疾病あるいは類似の疾病についてのみ通算するものと定める必要があるか否かも問題となり得ます。野村総合研究所事件でも、再発のしやすさということが就業規則としての合理性を基礎付ける事情として考慮されていますので、同一疾病としておくことが慎重であると一応は考えられます。もっとも、労働不能への陥りやすさを問題にするのであれば、同一疾病に限る必要はなく、限っていなかったとしても、通算規定の合理性が認められる可能性はあるように思います。とはいえ、通算規定がありさえすれば、常に通算規定の適用により期間満了になったときに必ず労働契約終了の効果は認められるとは限りません。実際には、休職期間や疾病の種類(再発のしやすさ)等によって結論が異なり得るとすると、繰り返される疾病への対応としては、通算規定を設けるのではなく、一定期間内に繰り返し労働不能状態となること自体を解雇事由として規定しておくことも考えられます。

開始要件(休職事由の設計)
休職の開始要件については、厚生労働省のモデル就業規則(以下参照)で示されておりますように、一定の欠勤期間を前提に休職を発令するという規定があり得ます。また、「特別な事情があり休職をさせることが適当と認められるとき」といった包括的な条項を定めることも考えられます。
厚生労働省モデル就業規則(第2章)
第9条 労働者が、次のいずれかに該当するときは、所定の期間休職とする。
①業務外の傷病による欠勤が●か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき ●年以内
②前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき 必要な期間
(1)休職をさせないことが問題となるケース(休職承認)
モデル就業規則のように、「適当と認められるとき」という文言を用いて、休職発令に使用者の裁量を留保することは一応可能です。ただし、裁量権濫用・逸脱と評価され得る場合もありますし、また、休職制度を設けておきながら休職を経ないで解雇すると、解雇権濫用と評価される可能性があります。
日本ヒューレット・パッカード事件(最二小判平24・4・27労判1055号5頁)は、労働者が、被害妄想等によって、有給休暇を消化し切った後で40日間の欠勤をしたところ、これを無断欠勤として諭旨退職の懲戒処分にしたというケースです。最高裁はこのような精神的な不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対しては、健康診断を実施するなどした上で、必要な場合は休職等の処分を検討し、その後の経過をみるなどの対応をとるべきと判示しています。
また、就業規則に定められた90日の欠勤期間を経ずに休職させ、休職期間満了で解雇した事案で、解雇後、労働者が回復したことなども踏まえ、解雇権濫用に当たり無効であるとした裁判例があります(J 学園事件・東京地判平22・3・24労判1008号35頁)。
このように、休職を経ないで解雇することには基本的には慎重であるべきでしょう。ただし、休職を経たとしても回復しないという場合は、休職を命じずに解雇しても解雇権濫用に当たらないとする裁判例もあります(岡田運送事件・東京地判平14・4・24労判828号22頁)。
(2)休職にすることが問題となるケース(休職発令)
制度設計によりますが、休職は、その期間中無給になったり、勤続年数にカウントされず、退職金や賞与が減額されるなどの不利益を伴う場合があります。
クレディ・スイス事件(東京地判平24・1・23労判1047号74頁)は、病気休職のケースではありませんが、このような不利益があることから、休職命令は全くの自由裁量ではないことを確認しています。
欠勤を前提とする休職規定が置かれている場合に、欠勤要件を満たしてないけれども、「やむを得ない理由があると会社が認めた場合」のような包括条項を使って、労働者に休職命令を発令することも可能ですが、発令に相当する事情があるかを確認する必要があります。
富国生命事件(東京高判平7・8・30労判684号39頁)では、欠勤期間を前提とする休職規定が置かれていることも踏まえると、「傷病欠勤の場合と同視できるものであって、通常勤務に支障が生じる程度」の傷病であることが必要であるとしており、包括条項の適用に当たって限定的な解釈がされています。

休職満了の効果
休職期間が満了した場合に、解雇にするという規定や、退職扱いにするという規定(自然退職規定)を設けることが考えられます。自然退職の場合は、労働契約は意思表示によらず自動的に終了することになります。
休職期間満了により、労働契約の自動終了を導くことについては、解雇について合理的理由や社会通念上の相当性を必要とする解雇規制(労契法第16条)の潜脱にならないのかが問題になりますが、エール・フランス事件(東京地判昭59・1・27労判423号23頁)は、自然退職規定の合理性について、休職期間満了で1回復職させて改めて解雇するという迂遠の手続を回避するものとして、合理性を認めています。
しかし、同判決は同時に、自動退職規定を適用するに当たっては、「解雇権の行使を実質的により容易ならしめる結果を招来することのないよう慎重に考慮しなければならない」ということも併せて判示しています。したがって、自然退職と規定したからといって、より簡単に契約終了という効果が導かれるとは限りません。
また、業務上の傷病による療養期間及びその後30日間の解雇を制限する労基法第19条との関係でも、裁判例は、自然退職に対して、同条の適用ないしは類推適用をしたり(社会福祉法人県民厚生会ほか事件・静岡地判平26・7・9労判1105号57頁、アイフル(旧ライフ)事件・大阪高判平24・12・13労判1072号55頁)、あるいは、就業規則の合理的な解釈をすることにより(医療法人健進会事件・大阪地判平24・4・13労判1053号24頁)、業務上の傷病による療養期間中に労働契約終了の効果が生じないような判断をしています。
したがって、自然退職規定を設けること自体は可能ですけれども、基本的には、解雇とほぼ同様の規制がかかってくることになると理解しておいた方が良いでしょう。
休職の延長
休職期間満了時には、雇用終了か復職かが問われますが、もう1つの選択肢として、休職の延長を可能とする制度を設けておくことも考えられます。休職期間満了と自然退職の効果を結び付けている場合、延長の期間を労働者にきちんと明示しておかないと、延長後の休職期間満了による自然退職の効果が発生しない可能性もありますので注意が必要です(北港観光バス(休職期間満了)事件・大阪高判平26・4・23労判ジャーナル29号36頁)。
なお、再度の休職を命じるか否かは使用者の裁量に委ねられており、体調の改善の可能性が認められないとして、休職期間を延長しないことは不当ではないという判断がされたケースもあります(日本瓦斯(日本瓦斯運輸整備)事件・東京地判平19・9・11労判957号89頁)。延長の判断は、このように回復可能性等も踏まえて行うことになります。
休職期間中の義務
休職期間の労働提供義務は当然免除されますが、労働者としては会社の利益を害しない信義則上の義務を負い続けることになります。
マガジンハウス事件(東京地判平20・3・10労経速2000号26頁)は、休職期間中は、療養支援の趣旨を踏まえた生活を送ることが望ましく、その趣旨に反する行動については服務規律違反が問われると判示しています。この事件では、多少の外出、飲み会、旅行については、療養に資する面もあるということで、問題視しない判断がされています。具体的にどういった行為が許されるかは、個々の病状などによって具体的に検討されることになると思います。

休職発令又は復職可能性の判断方法
休職原因となった疾病の回復可能性をどう判断するかについては、医学的な見地から検討することが重要です(前掲綜企画設計事件)。この場合、頼りとなるのは、労働者の主治医や産業医です。
(1)主治医・産業医からの情報取集
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(平成16年10月、最終改訂:平成24年7月)では、休職開始時及び復帰時に、主治医の診断書の提出を受けることが望ましいとされています。しかし、この「手引き」では、「主治医による診断書の内容は、病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、それは直ちにその職場で求められる業務遂行能力まで回復しているか否かの判断とは限らないことにも留意すべきである。労働者や家族の希望が含まれている場合もある」ということも書かれています。
実際に、帝人ファーマ事件(大阪地判平26・7・18労判ジャーナル32号31頁)では、主治医の意見について、原告が従前従事していた業務を通常程度に遂行できる健康状態であったか否かという観点からの検討を主治医はしていないという判断がされています。また、コンチネンタル・オートモーティブ事件(東京高判平29・11・15労判1196号63頁)では、自宅療養が必要だという診断書が提出されてから、わずか18日後に通常勤務可能であるという診断書が出されたという経緯を踏まえ、原告の意向が強く影響して主治医の診断書が作成されているという判断が示されています。
そうだとすると、主治医の診断書は信用できないと思われるかもしれませんが、会社としては、主治医の診断書をただ疑うのではなく、主治医に対する問合せや産業医の意見聴取等、一定の対応をとることが必須となります(第一興商事件・東京地判平24・12・25労判1068号5頁ほか)。
前掲J 学園事件では、主治医から治療経過や回復可能性について意見を聴取しておらず、一度も問合せをしなかったのは、現代のメンタルヘルス対策の在り方としては不備であるという厳しい判断がなされています。また、アメックス(休職期間満了)事件(東京地判平26・11・26労判1112号47頁)でも、復職判定に当たっての行為規範が示されており、会社として診断書等の内容に矛盾や不自然な点があると考えるならば、主治医である医師に照会し、労働者の承諾を得た上で、診療録の提供を受けて、会社の指定医の診断も踏まえて、診断書等の内容を吟味することが可能だったのではないかと述べられています。先ほど紹介したコンチネンタル・オートモーティブ事件においても、人事担当者が産業医に相談し、その勧めを受けて主治医に事情聴取を行ったとの事情が認定されています。
なお、職場の信頼回復がなされたことを条件として復職可能とする主治医に対し、産業医はその条件が整っていないとして、見解が分かれたという事案の下、産業医の方がより職場の事情を把握しているとして、復職可能性を否定した裁判例もあります(日本通運事件・東京地判平23・2・25労判1028号56頁)。 主治医に照会して診療録の提供を受けるに当たっては、要配慮個人情報ですので、原則として、労働者の同意を得ることが必要になります(個人情報保護法第17条2項)。
この点に関して、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成30年9月7日)においては、労働者本人が自発的に情報を提出してきた場合は、労働者本人の同意を得たものと認められるとしています。他方、その情報について、「事業者等」(産業医も含まれるかと思います)が、更に医療機関に直接問い合わせる場合には、改めて同意を得る必要があるとしています。
また、「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」(平成31年3月)におきましては、本人同意は必要ですけれども、労使の話合いや希望する労働者への丁寧な説明を経た上で、情報の取扱いに関する規定を就業規則に盛り込み、周知していた場合には、健康情報等を本人の意思に基づき提出したことをもって、同意の意思が示されたという解釈が示されています。
この点、労使の話合いや個別労働者への説明をすることが前提となっているとはいえ、就業規則という会社が一方的に策定できるものの中に盛り込んでおくことで本人の同意があったものと認めてしまって本当によいのか、若干の疑問も残ります。実務的には、可能な限り慎重に運用し、場面によっては個別同意を得ておくことが望ましいと考えています。
また、上記指針や「手引き」におきましては、病名なども含めた生の健康情報を取り扱える人と取り扱えない人について、原則的な区別を示しています[図表2]。事業場の状況において異なる取扱いも可能とされていますが、特別な事情がない限り、産業保健職が生の情報を扱い、それ以外の者は加工された情報を利用するという形で整備しておくべきと考えます。
いずれにしましても、以上で述べた休職・復職の判定方法や情報の収集に係るルールについては、整備しておくことが重要です。
なお、情報の取得に労働者の同意が必要であるとして、労働者が診断書の提出を拒否するのであれば、復職の判断ができませんので、その後の解雇・自然退職の効力が認められやすくなります(大建工業事件・大阪地決平15・4・16労判849号35頁、トッパンメディアプリンテック東京事件・東京地立川支判平28・11・15労経速2301号3頁)。

(2)本人の病状報告義務
やや特殊な事例ではありますが、休職期間中の病状報告義務を認めた裁判例も存在します(ライトスタッフ事件・東京地判平24・8・23労判1061号28頁)。ただし、メンタルヘルス不調の場合には、職場との接触自体が病気を悪化させるというリスクもあるので、そのようなケースでは休職中の労働者との接触は避けるべきということになると思います(ワコール事件・京都地判平28・2・23労判ジャーナル51号13頁参照)。
(3)指定医等による法定外健診受診等
会社の指定医による検診などを命じることができるかについて、電電公社帯広電報電話局事件(最一小判昭61・3・13労判470号6頁)は、療養者は、健康管理従事者の指示に従い健康回復に努めなければならないという規定があることを根拠として、具体的な指示内容については規定がないにもかかわらず、健康管理従事者において、担当医を指定して検診を命じることができ、これに従わない労働者に対する戒告処分も有効であるという判断をしています。もっとも、この事案は、会社が療養中の補償をしていたというケースでした。そうではない場合に果たして検診・受診命令に従わないことを理由として懲戒処分ができるかという点について、私見としては否定的です。
「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」では、事業者は、心身の情報の取扱いに労働者が同意しないことを理由として、又は、健康確保措置や安全配慮義務の履行に必要な範囲を超えて、不利益な取扱いを行うことがあってはならないとしています。労働者が検診に応じないために復職判定ができないということはあり得ますが、その場合は、復職不可という結論を出せば良いだけです。それに加えて懲戒処分をする必要性や相当性は慎重に考慮すべきと私は考えています。
(4)試し出勤、リワークプログラムの利用
更に、復職可能性の判定に関しては、試し出勤やリワークプログラムを利用することが考えられます。具体的なケースを見ていきますと、試し出勤等がうまく進まなかったケース等におきましては、復職不可との使用者の判断が裁判所によって支持されるといった傾向も認められます(日本テレビ放送網事件・東京地判平26・5・13労経速2220号3頁ほか)。
試し出勤については、「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」(平成28年2月、最終改訂:令和2年3月)において制度の導入が促されていますが、これを実施する義務はないと考えられています(学校法人専修大学(差戻審)事件・東京高判平28・9・12労判1147号50頁ほか)。