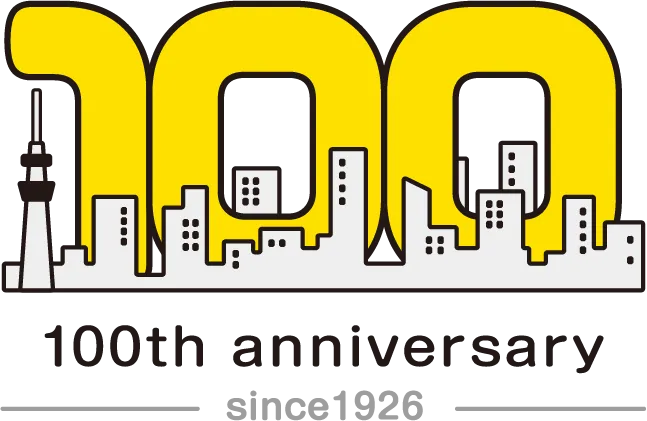少年とともに
委員会ニュース(子どもの権利に関する委員会)

医療的ケア児就園就学などホットライン(後編)
~障がい児の学びと育ちの場の選択~
米本 英美 Emi Yonemoto ―70期
1.ホットラインの概要
第二東京弁護士会では、2020年11月6日に第3回目の「医療的ケア児就園就学などホットライン」を実施しました。
このホットラインは、たんの吸引や人工呼吸器等の医療的ケアを必要とする子どもが保育園や幼稚園に入れない、希望する学校に入れないなどの問題に対応するため、2018年から毎年実施しているものです。
2020年のホットラインの相談件数は22件であり、2018年、2019年と比較して相談が増加しており、就園就学に際して、医療的ケア児やその保護者が困難に直面していることがうかがえました。
2.実際の相談内容
実際の相談として最も多かったのは、医療的ケアが必要であることを理由とする就園就学の拒否についての相談です。
例えば、子どもを保育園に入園させ、母親は復職したいと考えているが、行政機関からは、設備や看護師がいない等の理由で医療的ケア児を受け入れられる保育園が市内にはない、仮に受け入れ可能な園があるとしても、看護師の募集が必要なので本年度の入園は難しい等の理由で、申込みをしても入園許可は出ないなどと説明され、入園申込みの前から就園を拒否されるような事案です。
申込み前の段階から、行政機関から申し込んでも意味がないと繰り返し言われてしまうと、申込みをしても無駄だ、諦めなければならないと考えてしまう方も多いと思います。もっとも、児童福祉法では、「保護者の労働又は疾病その他の事由により、その看護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、当該児童を保育所...において保育しなければならない。」(児童福祉法24条)と定められており、医療的ケアや障害を理由に申請する機会すら奪うことは、障がい児に対する不当な差別といえます(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、「障害者差別解消法」)7条1項、8条1項、憲法14条)。
また、保育園の入園申込みをしたが医療的ケアが必要なことを理由に不許可となり、不許可処分に対する審査請求や、議員の協力を得て請願も行ったが、それでも入園を認めてもらうことができない、後は訴訟しかないが、訴訟は費用も時間も掛かるし、子どもの成長に伴い医療的ケアが不要になる可能性もあり、訴訟までは踏み切れないという相談もありました。
費用も時間も掛かる訴訟に踏み切れないという気持ちはよく分かりますし、そもそも訴訟をしなければ(あるいは訴訟をしても)就園の機会を得られない、又は健常児であれば誰でも当然に就学できる地域の学校への就学を拒まれるというのは、子どもの尊厳を傷つける差別といえます。
更に、保育園等で医療的ケア児を受け入れる場合でも、看護師が常駐できる時間が決まっており、それ以外の時間は預かることができないと言われたり、設備の関係で医療的ケア児を受け入れられるのは市内で1つの園のみと言われ、その園は職場からも自宅からも遠く実際には利用できなかったりなど、受け入れ先が条件に合わず、更なる問
題に直面しているとの相談もありました。このように、条件に合わない保育園、幼稚園であるとしても、受け入れ先を確保できなければ結局入園させることはできませんし、一方で、入園後も保育時間の延長や転園の交渉なども行う必要が出てきます。このような問題は、保育時間が限られていると結局は復職できない、育児休暇を使い切り、介護休暇を取得してなんとか失職しないようにしている等、保護者の復職との関係でも大きな障壁になっているようでした。
このほか、ホットラインへは、地域の小学校への就学を希望したが、特別支援学校を指定されてしまいそうである、学校が医療的ケアを実施してくれず、保護者の付き添いが要求されているなどの相談もありました。
前編でも詳しく述べたとおり、障害者差別解消法では、「行政機関等は、...障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状況に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。」(同法7条2項、8条2項)と定められており、上記のような対応は合理的配慮義務に反しているといえます。
このように、ホットラインには切実な相談が多く寄せられました。
3.ホットラインの相談を受けて
私自身は、ホットラインの相談に初めて参加しましたが、医療的ケアを必要とする子どもやその保護者が切実に悩んでおり、相談先を求めていることを感じました。
電話相談だけで解決に至る問題ではなく歯がゆい思いをすることもありましたが、「何度相談しても、行政からは、医療的ケアが必要だと入園は難しい、子どもの安全を確保できない等と言われるので、保育園に預けようとしている自分が間違っているのではないかと思ってしまっていた。弁護士から間違っていないと言ってもらえてよかった。まずは、申込みをしてみようと思う。」と話してくださった方もおり、ホットラインを実施した意義を感じました。

触法少年事件における付添人活動
加賀山 瞭 Ryo Kagayama ―67期
1.K先生からの電話
ちょうど1年前くらいになるだろうか。事務所で仕事をしていたら、少年事件チーム長のK先生から電話が入った。「お願いしたいことがあって...」とのこと。二つ返事で「いいですよ。どんな事件ですか?」と言ったところ、「ショクホウショウネンの事件でして...」とK先生。ショクホウショウネン? あぁ、触法少年か、これは大変そうだ...。ひょんなきっかけで初めての触法少年事件を担当することになった。
2.触法少年事件の特殊性
触法少年とは、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年をいう(少年法3条1項2号)。しかし、刑罰法令に触れる行為があっても、刑事責任能力がないので(刑法41条)、犯罪としては扱えず、したがって捜査をすることもできない。その分、児童相談所の関与の度合いが強まり、例えば、家庭裁判所に送致するかを判断するのも、原
則として児童福祉機関の判断に委ねられている(児童福祉機関先議の原則、児童福祉法27条1項4号)。
このような特殊性から、手続についても通常の少年事件とは大きく異なっていることに注意が必要である。
①事件の発覚・触法少年の発見
②警察による触法調査(≠捜査)
③児童相談所長への通告・送致(児童福祉法25条)
④児童相談所による調査(一時保護を利用した身体拘束下の取調べも可能(児童福祉法33条1項)。ただし、一時保護期間は、通常3~5日程度。)
⑤家庭裁判所送致
⑥家庭裁判所による処分(児童自立支援施設や児童相談所長といった福祉的措置がとられることが多い。)
3.触法少年事件における付添人活動の留意点
(1)付添人の選任等
東京三会では、一時保護された触法少年について、「触法調査少年当番弁護士」制度を設けており、この制度をきっかけに触法少年を担当することになる場合が多いだろう。
少年及び保護者はいつでも弁護士を付添人に選任できるが(少年法6条の3)、保護者に資力がなくても、家裁送致前は日弁連の委託援助事業(子どもに対する法律援助)を使って、送致後は国選付添対象事件であれば国選付添人に切り替え、また、対象事件でなければ日弁連の委託援助事業(少年保護事件付添援助)を使って、付添人に就任することが可能である。
(2)面会の際の注意点
触法少年は、低年齢であり、心身ともに未成熟であることに加え、発達上の障がいを抱えている場合も多く、通常の少年以上にコミュニケーションを取ることが難しいことが多い(触法少年に限らず、非行少年のこうした特徴を取り上げたものとして、宮口幸治『ケーキの切れない非行少年たち』(2019年、新潮新書)。 )。
したがって、面会の回数を増やし、少年からじっくり話を聞くことができる環境を作ることが大切である。
それでもコミュニケーションに支障が生じる場合も少なくないと思われる。そんなときは、刑事司法ソーシャルワーカー(東京社会福祉士会、東京TS ネット等)の利用も検討してみてはどうか。当会では、社会福祉士や精神保健衛生士との連携及び費用援助制度も用意されている(会員向けページ>弁護士業務>刑事弁護援助基金>社会福祉士・精神保健衛生士との連携及び費用援助制度)。
4.触法少年事件を担当して
K先生からの電話を受けて、触法調査少年当番弁護士として、某区の児童相談所に赴いた。部屋に通されて待っていたところ、職員の方に連れられてやって来たのは、まだあどけない面影の13歳の男子中学生だった。「こんにちは!」と言ってハキハキと挨拶してくれた。
この少年の非行事実は同年代の子どもに対する性犯罪であった。とはいえ、この年代の中学生が保健体育の授業で習うような知識はほとんど有しておらず、自分のやったことの意味もあまり分かっていない様子だった。
少年にいろいろと質問してみたところ、少年なりに一生懸命答えようとしてくれているのだが、どうも問いと答えがかみ合わない。後で分かったことであるが、少年は幼少期から注意欠如多動性障害(ADHD)、自閉スペクトラム症、平均下位の知能という診断を受けていた。
加えて、少年は、外国人の父と日本人の母との間の子であったが、両親の離婚後、日本語が話せない父と同居し、公立学校に通っていた。父は少年に対し、たっぷり愛情を注いでおり、少年は上記障がいを有しながら公立学校に通っていたものの、学校の先生とのコミュニケーションが上手く取れないという難しさもあった。
以上のような状況から環境調整が難航することが予想されたため、私は、前述した当会の費用援助制度を用いて、東京社会福祉士会の刑事司法ソーシャルワーカーの方にも入ってもらうこととした。刑事司法ソーシャルワーカーの方には、成人刑事事件で行うような更生支援計画の作成に準じて、ADHDの治療薬の服薬や認知行動療法を受診することなどのご示唆をいただき、審判の際の付添人意見に反映させることができた。
また、被害者意識を有していた少年に対し、それでもやってはいけないことがあるということを、面会の度に何度も粘り強く伝えるようにした。
少年は在宅での更生を希望していたが、審判では、非行内容の重大さに鑑み、児童自立支援施設送致という結果になった。
元々有している障がいゆえ、施設を出た後も継続的な見守りが必要であるが、児童相談所を中心に、福祉、医療、学校が連携を取っていくことが決まっている。私も元付添人として何かできることがあれば協力したい。