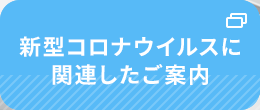本当に怖い非弁提携
 深澤 諭史(63期) ●Satoshi Fukazawa
深澤 諭史(63期) ●Satoshi Fukazawa
当会会員
【略歴】
平成22年弁護士登録
非弁護士取締委員会副委員長、
弁護士業務センター副委員長
【著書】
〔改訂版〕これって非弁提携?弁護士のための非弁対策Q&A(第一法規)、
まんが 弁護士が教えるウソを見抜く方法(宝島社)等
1 はじめに
当誌2017年10月号で『本当に怖い非弁提携』と銘打った特集を執筆させていただきました。その内容は2部構成となっており、第1部では、非弁提携の基本や実情、そして関連規程を解説しました。第2部においては、若手弁護士が非弁提携業者の甘言に乗せられて、知らず知らずに非弁提携に陥り、資格も財産も失ってしまうという経緯をドキュメンタリー風に解説しました。
当会広報室のご厚意で、『非弁フロンティア』と題した豪華な(!)中表紙も用意していただきました。また、テーマも非弁提携ということで、非常に注目を集めたと、掲載後、広報室から教えていただきました。
さて、昨今もなお、非弁提携事案や、あるいは非弁提携を疑われるような事案が発生し、話題になっています。
非弁提携は、伝統的には、月額いくらで弁護士が非弁提携業者に職印や名刺を預けて、「丸投げ」をするというものでした。
しかし、最近流行の非弁提携(前回の特集でも取り扱った形態)は、伝統的な非弁提携とは異なり、提携弁護士が半ば騙されるような形で引き込まれる、事務所支配の実権を非弁提携業者に握られる、ずさん処理で市民を食い物にするだけではなくて、事務所資金の横領や経費流用で、最終的には弁護士の財産も食い物にする、というものです。弁護士も自業自得とはいえ、膨大な被害を被る、市民も横領等により甚大な被害を被る、ということが、従来の非弁提携と大きく異なる点です。
このような新型非弁提携は、若手弁護士が騙されて陥るというケースが後を絶たず、大きな問題になっています。
その一方で、最近は、明確に非弁提携とまではいえない、また、弁護士が非弁や非弁提携のリスクに気がついていない、というケースがあります。
このようなケースは、非弁提携にはなるのですが、事務所を乗っ取られるとか、重大な結果をもたらすことは多くはありません。いわば「ライト非弁提携」ともいうべき案件が散見されます。
今回は、重大な非弁提携ではなくて、最近増えているライトな非弁提携について解説したいと思います。
なお、私は非弁護士取締委員会の副委員長ですが、ここで述べる見解は私個人のものです。また、いくつか類型を挙げていますが、その類型の事業が全て非弁提携に該当すると判断するものではありません。あくまで、関わり方などによってはリスクが生じる、という趣旨で指摘をするものです。
2 なぜ非弁提携が許されないのか
私たち弁護士は、法律の専門家として、法律に関係する業務について、ほぼ無制限に業務を行うことができます(弁護士法第3条1項)。
その反面、弁護士法第72条本文により、ごく一部の例外(他士業など)を除いて、非弁護士が業として報酬目的で法律事務を取り扱うことは禁じられています。また、これには罰則も定められています(弁護士法第77条3号)。
いわゆる非弁(行為)とは、それにもかかわらず、弁護士でない者が、弁護士業務を行うことをいいます。
弁護士法で弁護士の法律事務取扱いの独占が認められているのは、弁護士に厳重な資格制度、規制が定められているからに他なりません(弁護士法第1条等)。
弁護士が取り扱う法律業務においては、依頼者と相手方との利害は対立し、時には、葛藤の大きい紛争を扱うことがあります。
かような業務を無資格者に行わせると、「資格もなく、なんらの規律にも服しない者が、みずからの利益のため、みだりに他人の法律事件に介入することを業とするような例もないではなく、これを放置するときは、当事者その他の関係人らの利益を損ね、法律生活の公正かつ円滑ないとなみを妨げ、ひいては法律秩序を害することになる(昭和46年7月14日最高裁判所大法廷判決 『判例タイムズ』265号92頁)」と考えられています。つまり、弁護士に法律事務の独占が認められているのは、公益のためであるということです。そして、非弁行為はこの公益に反することになります。
さて、非弁提携というのは、弁護士法第27条、弁護士職務基本規程(以下「規程」)第11条〜13条に定められた、非弁護士との許されない一定の関係(提携)をいいます。
具体的には、非弁行為者から事件の紹介を受けたり(弁護士法第27条)、そのような者を利用したり(弁護士法第27条、規程第11条)、報酬を分配したり(規程第12条)、紹介料を払ったりもらったりすること(規程第13条)が禁じられています。
弁護士でない者が行う非弁行為だけではなく、弁護士が非弁護士と提携する非弁提携行為も禁じられているのは、非弁行為の禁止を徹底するためです。
つまり、非弁行為を放置すると「法律秩序を害すること」になります。そして、これは「資格もなく、なんらの規律にも服しない者が」弁護士を隠れ蓑に使って、非弁行為を行う場合も同様です。
更に、弁護士には、弁護士自治制度をはじめとする諸制度により、高度の独立性が保障され、また要求されています。事件の紹介を受けることや、紹介料授受、報酬分配といったものが横行すると、弁護士の独立性が害されるだけでなく、それらの費用が依頼者に転嫁されたり、粗雑な事件処理が行われたりするリスクがあります。
こうして、法は、非弁行為のみならず、非弁提携行為をも禁止しているのです。
3 禁じられている行為
次に、具体的に禁じられている行為について、解説します。
まず、非弁護士なのに、弁護士業務を行い、あるいは、そういう事件の紹介業を行っている者(非弁提携業者)から、事件の紹介を受けることが禁じられています(弁護士法第27条)。
ここでのポイントは、紹介元の非弁提携業者に報酬目的は必要ですが、弁護士には不要であるということです。ですから、無料で紹介を受けても、紹介元が非弁提携業者であれば弁護士法第27条違反は成立する、ということになります。これには、弁護士にも刑事罰があります(弁護士法第77条1号)。
また、この定めを拡大したものが規程第11条です。これによると、非弁行為をしている者、あるいは、そうであると疑わしい者から事件の紹介を受けたり、利用したりする行為全般が禁じられています。
要するに、非弁については疑わしい者とは関わり合いを持ってはいけない、ということで、かなり広範な(厳しい)規制であるといえます。
次に、弁護士は、弁護士報酬を非弁護士と分配することが原則としてできません(規程第12条)。
ですから、例えば、事件を紹介してもらって報酬を折半するとか、あるいは、一緒に仕事をしたから3分の1あげるとか、そういうことを非弁護士に対してすることはできません(ただし、例外あり)。
また、弁護士は、自分が依頼者を紹介する、あるいは、依頼者を紹介してもらうことについて、紹介料をもらう、あるいは、支払うことはできません(規程第13条)。これについては、少しややこしい問題がありますので、注意が必要です。
以下では、最近頻出している非弁提携のリスクがある事案について解説します。
4【事例1】不動産会社への紹介料
家事事件や債務整理事件においては、不動産の処分が必要になる場合があります。
例えば、弁護士Aが、不動産会社Bに、処分が必要になった依頼者Cの不動産の売却案件を紹介したケースを想定します。
この場合、B が、A に対して、この紹介について紹介料を支払うことは許されるのでしょうか。
規程第13条2項は「弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない」と定めています。
そうすると、弁護士であるAは、依頼者であるC を、B に紹介して、それで謝礼をもらっているということになり、規程第13条2項に違反する、ということになりそうです。
もっとも、規程はあくまで弁護士の職務に関する定めです。となると、この規程第13条2項の「依頼者」というのは、紹介先にとっての弁護士業務の依頼者であり、本件のようなケースでは当てはまらないのではないか、という疑問もあります。
この点について、『解説「弁護士職務基本規程」第3版』(2017年、日本弁護士連合会弁護士倫理委員会)30頁では、紹介と依頼者の意義について「『紹介』には、弁護士に対するものだけでなく、弁護士以外の者に対するもの、例えば、遺産分割事件や任意整理事件で不動産の処分を不動産業者に依頼し、その業務上の顧客となる者を紹介する場合の紹介行為も含む」とされています。
つまり、この依頼者には、紹介先の弁護士以外の者にとっての依頼者も含むということですので、上記のケースで紹介料をBがAに対して支払うと、規程第13条2項に違反することになります。
これについては、同項の「依頼者」に、弁護士業以外の依頼者を含むのは広きに失するのではないか、という批判もあり得ます。ですが、上記の解説では、「弁護士としての職務を行わずに紹介料という対価を自ら領得するものであって品位を害する」という見解です。
筆者としては、このようなケースで弁護士が紹介料を受け取るべきではない、という結論には賛成しますが、理由付けは異なります。
このようなケースでは、依頼者には選択の余地が余りないことが多いです。弁護士が推奨した業者について、別の業者を使いたい、というのは、なかなか言い出しにくいということもあるでしょう。したがって、弁護士が、ある種の優越的な地位を用いて依頼者を紹介し、それで利益を得るのはやはり適切ではない、と考えます。
さて、紹介料という制度自体は、何も悪いものではありません。むしろ他の業界では当たり前のことであり、ここまで厳しい規制のある弁護士業界が特殊なのです。
したがって、気をつけないと、不動産業者等から「悪気なく」紹介料を持ちかけられて、これに応じて違反をしてしまう、ということがあり得ます。
紹介料規制については、様々な議論があるところであり、筆者個人としては、立法論(規程改正)として、緩和もあり得るのではないかと思っています。
5【事例2】事務職員への営業歩合
事務職員が関与した案件、あるいは、受電(電話を受けて)して、その後に受任できた事件について、報酬の一定割合や、一定金額を支給する、いわゆる営業歩合を支給する場合はどうでしょうか。
勤務弁護士である場合、主任手当という形式で支給される例もあろうかと思いますが、これは、その事務職員版ということです。
事務職員を事件処理において活用するケースでは、このような給与体系を採用していることもあろうかと思います。
さて、このような給与体系ですが、規程第12条に違反する可能性があります。
規程第12条は「弁護士は、その職務に関する報酬を弁護士又は弁護士法人でない者との間で分配してはならない。ただし、法令又は本会若しくは所属弁護士会の定める会則に別段の定めがある場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない」と定めています。
事務職員が、直接報酬を依頼者から受領する場合はもちろん、弁護士を経由して賃金として受領する場合も、報酬分配と扱われる可能性があります。
弁護士の売上げ(弁護士報酬)や件数と比例して、業務(事務)の一部を担当する非弁護士が報酬を受けるというのは、非弁提携の典型です。
もっとも、事務職員に歩合を支払うのは、その努力や成果に比例するものであって、給与体系として合理的です。何らかの形で報いたいというのは自然かつ必要なことでしょう。
そこで、受任件数や売上げに比例し、あるいは、それを直接の指標とすることはできないとしても、事務所全体の業績や、普段の事務職員のパフォーマンスに鑑み、賞与を支給するということが合理的でしょう。
あえて、非弁提携リスクを負担してまで、受任件数や事務担当案件売上げを指標にする必要はないと思います。
6【事例3】他士業(会社)連携
他士業交流会に参加したことはあるでしょうか。他士業の方々と交流して、人脈を広げ、相互に仕事を紹介したりする機会を得る会です。
弁護士は、法律事務については、無制限の資格ということになっていますが(弁護士法第3条。
ただし、税理士業務について税理士法第52条の例外あり)、資格上「できる」といっても、十分な知識経験があるとは限りません。
餅は餅屋というように、登記にしろ、税務にしろ、弁護士が自分でやるより、その道のプロに依頼したほうが適切です。例えば、相続案件を受任する際は、登記について司法書士に頼む、税務申告については税理士に、ということは、通常よくあることです。
基本的に、弁護士が単独で受任して、登記や税務申告だけピンポイントで依頼者から司法書士・税理士に依頼するのであれば、弁護士法令上の問題はありません。
問題は、弁護士と他士業、あるいは株式会社が共同で同じ案件を受任する場合です。まず、前提知識として、弁護士が他士業、株式会社と一緒に契約をして仕事をする(共同受任)ことそれ自体は、何も問題はありません。
問題は、その共同受任が、非弁提携に該当するかどうか、つまり、規程第11条〜13条に違反するかどうか、ということです。
すなわち、共同する他士業について、非弁行為を行っていないし、その疑いもないこと(規程第11条)、紹介料の授受もないこと(規程第13条)が必要です。
この紹介料の部分がくせ者で、例えば、事件を取ってきた人が、業務量に比して高額な取り分を受け取ると、それが実質的に紹介料になる、という可能性があるので注意が必要です。
そして、最も問題になるのは規程第12条です。
他士業や株式会社と共同して仕事をする以上は、弁護士以外の共同者に報酬を分配しなければなりません。まさか、「報酬分配は禁止なので、タダ働きしてください」というわけにはいきません。
報酬分配の問題については、分配先が非弁行為者でなく(規程第11条)、また、実質的にも紹介料ではなければ(規程第13条)、分配は可能です。
規程第12条ただし書は「ただし、法令又は本会若しくは所属弁護士会の定める会則に別段の定めがある場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない」としているためです。
問題は、この正当な理由の内容ですが、『解説「弁護士職務基本規程」第3版』28頁は「隣接専門職との協働によるワンストップ・サービスの提供の場合においても、分配について正当な理由があるとされることがあり得る」としています。ですが、具体的な基準について定説はありません。
筆者の私見としては、概ね、次のような要件をいずれも満たす必要があると考えています。
① 各担当者の業務が適法(資格の範囲内で行っている)である。
② 報酬の分配割合やその算定根拠についての合意がある。
③ 分配の割合や金額は、それぞれの業務内容に照らして適正である
④ 共同者についても非弁行為の疑いはない。
まず、①については、他の共同者について、あくまで資格の範囲内で業務を担当させることが重要です。このあたり、いわゆる事件性必要説(弁護士法第72条本文で、非弁護士が禁止される業務は、紛争性のある案件に限る、という見解)を前提にしてしまうと、問題が生じることがあります。もちろん、この点について弁護士会の公式見解があるわけではありませんが、日本弁護士連合会調査室編著の『条解弁護士法〔第5版〕』の見解は、事件性不要説(紛争でなくても弁護士法第72条本文の適用があり、非弁護士は取り扱えな
いとする見解)を採用しています。
したがって、事件性不要説の見解を前提に、他の共同者が非弁護士行為をしていない、それぞれの資格の範囲内(株式会社であれば、無資格でできる行為に限る)であることを確認し、合意を得ることが重要です。
②については、通常、単独で受任した場合と比べて不自然に高額ではないこと、業務内容と金額とが明記されて合意することが重要です。根拠を予め定めておけば、非弁提携の疑義をもたれた場合も、説明は容易でしょう。
③については、これも、②と同様に不自然に高額ではない、というところがポイントです。例えば、相続案件をワンストップ・サービスでやる場合、通常、同種案件で司法書士は登記報酬として10万円を受領しているところ、事件を持ってきたということで、15万円にするといったことをすると、実質的な紹介料あるいは正当な理由を欠く分配と評価されるおそれがあります。
④について、規程第11条は、非弁行為の疑いのある者との関係を規制しています。ですから、この案件では問題がなくても、別のところで非弁行為を行っていないのか、念のための確認が必要です。
法的サービスへの需要が多様化する現在、他士業連携は必要かつ有効です。ですが、そのためのルールがやや未整備な感もありますので、このあたりは、日弁連等がガイドラインを作成することを期待したいと思います。
7【事例4】会員になると事件紹介をしてくれる
これも、最近増えているパターンです。会費を支払って、○○会、○○ネットワークのメンバーになると、事件を紹介しますよ、というものです。
表向きは会費であり、あるいは、それらの「公式ページ」への掲載の広告料なのですが、その広告からの受任は余り見込めず、あくまで、紹介を目当てとするものです。
会費(定額)なので問題がない、と勧誘されますが、事件紹介の対価であることの評価と定額であるとの事実は両立します。焼き肉食べ放題の代金は、定額であっても飲食代金と評価できる、ということと同じです。
8 おわりに
以前の非弁提携といえば、弁護士も非弁提携をするぞ、と決断して、いわば非弁提携であるという法的評価について故意があるケースがほとんどでした。
しかし、前回の特集で取り上げたような騙されるケースもあれば、今回のように、事務所を乗っ取られるわけではないが、非弁提携とは思わずにそうなってしまう、いわばライトな非弁提携というべきケースが増えています。
弁護士は、他士業や株式会社と連携することで大きな力を発揮することができます。ですが、注意しないと、非弁提携の落とし穴にはまりかねません。言われたことをそのまま丸呑みにするのではなくて、きちんと、自分自身で調査して非弁提携該当性を判断することが重要です。