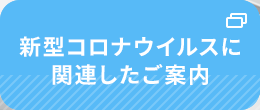会長鼎談
井上 由美子氏【脚本家】×黒崎 博氏【演出家】×神田 安積会長
 本号の特集は、当会会長ゆかりの方々をお招きして行う会長鼎談です。今年は、神田会長が、弁護士を主役にしたNHKドラマ『マチベン』の制作をきっかけに知り合ったお二人と鼎談しました。
本号の特集は、当会会長ゆかりの方々をお招きして行う会長鼎談です。今年は、神田会長が、弁護士を主役にしたNHKドラマ『マチベン』の制作をきっかけに知り合ったお二人と鼎談しました。
井上由美子さんは、兵庫県出身の脚本家です。テレビ東京勤務の後、脚本家デビューされました。主な作品は、『ひまわり』(NHK 連続テレビ小説)、『GOOD LUCK』(TBS)、『白い巨塔』(CX)、『緊急取調室』シリーズ(EX)など多数で、2006年には向田邦子賞と芸術選奨文部科学大臣賞を、2020年には紫綬褒章を受賞されています。
黒崎博さんは、岡山県出身のTVディレクター・演出家です。NHKに入局後、『ひよっこ』(NHK 連続テレビ小説)をはじめ、数々の番組に携わられ、最近では2021年大河ドラマ『青天を衝け』の演出を手掛けておられます。また、同年公開の監督作品『映画 太陽の子』(GIFT OF FIRE)は、米国アウェアネス映画祭グランプリを受賞しています。
今回の鼎談では、弁護士がコンテンツ制作に監修としてどう携わるかという点のみならず、日常的な弁護士業務に示唆を与えてくださるお話まで盛りだくさんです。新たな目標を立てたい新年にふさわしい内容となっていますので、ぜひご一読ください!
ドラマ『マチベン』での出会い
編集部 お三方が出会われたきっかけは、2006年に放映されたNHK の『マチベン』というドラマだったとお伺いしています。まず、脚本を書かれた井上さんからお話をお伺いできればと思います。
井上 今現在弁護士さんの仕事は身近にはなってきましたが、15年前は、世間では弁護士というとまだ企業顧問でお金持ちの弁護士か、逆にえん罪事件で活躍する事件弁護士のどっちかというイメージだったと思います。しかし、弁護士さんの仕事の面白さというか、意義は、そのちょうど間にあるなと思ったので、一般の方々の身近な問題を取り上げる弁護士さんをテーマにしたいと思ったのがきっかけです。
編集部 黒崎さんは、演出を担当した3人のうちのお1人でしたね。
黒崎 まだ駆け出しの頃で、とても面白そうな企画が進行していたので、どうしても1話撮らせてほしいと上司にお願いしました。
神田 私は、井上さんが脚本を書かれる前の段階で、新しい切り口での弁護士ドラマをNHKで作るので、アイデアを聞かせてほしいという依頼を受けました。ですから、お声掛けいただいたときには、どのような弁護士ドラマになるのかはまだ流動的だったと思います。
黒崎 第4話では安楽死をテーマとして取り扱ったのですが、当時としては、かなりとんがったドラマだったと思います。企画段階から、ちょっと特殊な回だと思っていました。安楽死をテーマにするのかどうかから取材を始め、たくさん井上さんと話して進めた記憶があります。
編集部 タイトルを『マチベン』にしたのは、何かお考えがあったのですか。
井上 身近な弁護士を描きたかったのが一番です。事件は会議室ではなくて、事案は町で起こっているというイメージで、とにかく「町」という言葉を使いたかったのです。
神田 お2人は、事前の準備の中でたくさんの弁護士にお会いになって、取材しておられました。
今から15年前になりますが、弁護士に会ったときの印象はいかがでしたか。
井上 たくさんの弁護士さんにお会いしたのですが、本当に個性豊かだなと思いました。法律をもとにお話をされるお仕事なので、みんなだいたい同じ着地になるのかなと思ったら、弁護士さんによってかなり違うのですね。だから、逆に言えば法律というよりどころがあるから人間性の違いを出せ、生き方の違いが見えてくるのはすごく面白いなと思った覚えがあります。
黒崎 こんなに人によって違うのかなと、僕もびっくりしました。僕らは新橋とかの雑居ビルの1室でやってらっしゃる先生のところにも行ったし、当時ピカピカだった六本木ヒルズの事務所もお訪ねしました。こんなに違いがあるのに、それぞれの道を自分で選んでお仕事をされているという、それが面白いなと思いました。

ドラマの制作
編集部 少し『マチベン』を離れて、ドラマの制作についてお聞きしたいのですが、ドラマはどのようないきさつで制作されていくのでしょうか。
黒崎 僕が今回演出を担当したNHK 大河ドラマ『青天を衝け』の場合は、3年くらい前に、NHK の上層部からこの年の大河ドラマを担当せよと言われました。ネタは自由、誰と組むかも自由、全部考えてくれ、という話です。
編集部 責任が重いですね。
黒崎 そうですね。僕はプロデューサーの肩書きもありますが、立場としては演出家です。脚本は大森美香さんにお願いすることになり、そこから3人でたくさん芽出しをしていきました。
大河ドラマや朝ドラの場合、最終的にはNHKの上層部の判断が必要なので、それも踏まえて今の形ができ上がってきています。
編集部 オンエアの前が大変なのでしょうか。
黒崎 オンエアが始まったら放送と撮影の追い駆けっこになってあっという間に終わっていくので、むしろそこまでが大変です。撮影開始から放送が始まるまでに1年以上ありますし、自分たちは企画から2年近くやっています。成果が見えるオンエアまでが一番苦しいですね。
編集部 ドラマの現場では、コロナの影響は大きかったですか。
黒崎 はい、大きな影響を受けました。今回の大河ドラマはクランクインが3か月くらい遅れてしまいました。本来なら早くから始めて少しずつ慣らしながら撮っていくのですが、東京都から出るのが難しい状況にもなったし、スタジオでマスクをして撮影ができるのかどうかも最初は誰にも分からなかったので。だから何もできない3か月を過ごしました。それでやっと緊急事態宣言が解除され、そこからは急ピッチで撮り進めなくてはいけなかったので、そこが大変でした。
編集部 ハードだったのですね。
黒崎 でも、結局今までのところ感染者を出さずにやってきているので、スタッフにもキャストにも本当に頭が下がります。ロケに行かせてもらっているだけで、「本当にすみません、お邪魔します」と思いながら群馬県に行かせてもらいました。
演出家の役割
編集部 演出家は、撮影現場ではどのような役割を果たしているのでしょうか。
黒崎 役者と演出家の関係は、撮影現場に入るまでにほとんど決まっていると思います。それまでにどれくらいキャラクターについて話し合っているかとか、演じようとしている役の方向性についてどれくらい僕が理解できているかとか、そういうのって現場に入ったときにはもうだいたい関係性ができ上がっていると思います。
演じるのは俳優なので、ここで右手を出して左手を出してと細かいことを言ってももう時すでに遅しですね。本番で俳優が何をやって何を感じてどれくらい出すかというのを見て、よければいいし、悪ければもう1回やろうと言うしかないなみたいな、ちょっと独特な関係性ができ上がっています。
俳優にどういう言葉で指示を伝えるか、というのは演出家にとって最も大切なことの一つです。
演技という感覚的なものについて、言葉で伝えるのはとても難しい。言葉を尽くして話し合うこともあるし、できるだけ簡潔な言葉で伝えることもあります。信頼関係が出来上がっているときには、声をかけない、という選択をすることもあります。
声をかけないというのは凄く意味を持っていて、何人かの俳優に声をかけていって、一人にだけは視線を送るにとどめる、ということもあります。
そうすると、その俳優は「今の方向で存分にやれという意味だな」とか、何かを絶対感じているはずです。そういう微妙なやりとりが現場では繰り広げられています。
大河ドラマ『青天を衝け』
神田 『青天を衝け』で取り上げられた渋沢栄一は小さいときから、特にお母さんから、世のため人のためということを教えられていますね。この教えは月並みではありますが、ドラマではとても説得力のあるものになっています。その影響を受けて、彼は身分を超えて、また考え方も柔軟に変えながら、自分の在り方を選択していきます。
弁護士も依頼者の利益とともに公益も考える仕事です。このドラマを通じてのメッセージとして、どのような思いを込めて演出されたのでしょうか。
黒崎 お母さんが主人公の栄一に向かって、「みんなが幸せなのが一番なんだで」と繰り返し言います。それが大人になっても実業家になってもずっと彼の信条になっていきます。いろいろな伝記資料を読んでも書いてあるので、きっと本人も実際にそれを思い続けていたし、言い続けていたのだろうと思います。ドラマでそれに説得力を持たせるために、まず僕はこのドラマの冒頭で彼が暮らしている血洗島という名前の村を、お百姓さんの生活にどれだけリアリティを持たせられるかが重要だと思ったので、これに最大限注力しようとスタッフにも言いました。ロケハンして回って群馬に土地を見つけて、実際にスタッフが藍畑や桑の畑を手で植えて作って。今でも、1週間に1回か2回、水やりに行っています。ラストシーンを撮るためにあの畑を維持しています。
主人公の根っことしての農業にリアリティを持たせられるかどうかがこのドラマの勝敗の分かれ目だと思っています。あのコミュニティで、農家の人が暮らしていくためには自分1人が幸せだということはあり得ないですよね。自分だけが成功するというのは無理です。ここに虫が付いたらみんな全滅するし、ここだけ肥やしをやっても、ここだけ育っても、藍を採っても、それでは村のみんなが暮らしていけないわけです。
だからあのお母さんは、みんなが幸せにならないと村はやっていけないし、村がやっていけないとこの家もやっていけないということを、すごく実利的な意味で言ったんじゃないかなと思います。それが、夢物語じゃないから響いて、プラグマティスト実際主義者の渋沢栄一をつくっていったのかなと僕は解釈しております。
『映画 太陽の子』
神田 監督をされた『映画 太陽の子』についても聞かせてください。この映画では、広島、原爆、戦争といったテーマを取り上げていますが、今これらを描くことについてどのような思いがあったのでしょうか。
黒崎 僕は十数年前に広島で2年過ごしたことがあります。そのときも原爆が少し関係するドラマを1本作りましたが、そのドラマは戦争の被害者の視点から描いたものでした。今回作った『太陽の子』は、日本人が原子爆弾の研究をしていたという話なので、ある意味で加害者にもなり得たという視点があります。
とてもデリケートな話ではあるのですが、戦後76年、これまで視点が偏り過ぎていたのではないか、日本人の戦争観、特にフィクションの世界での戦争観が被害者という視点に偏って一面的に描かれていたのではないかという思いがありました。それを逆から描いてみたいという思いです。
描かないと、そういうものも作っていかないと何か全体像がもっと見えてこないし、全体像が見えてこないと本当に戦争のことを分かって次に生かしていくみたいなことができないのではないかという焦燥感みたいなものがありました。
神田 76年たってからというのは、遅すぎたような気がします。
黒崎 遅すぎたのだろうと思います。ただ、この『映画 太陽の子』の企画書を10年ちょっと前に初めて書いて映像化したいという話をしたときには、触るのは危険だという人があまりにも多くて相手にしてもらえませんでした。いろいろな経緯があって、東日本大震災や原発の事故も経てその温度が上がったり下がったりしながら、今そのバジェットとこの企画に賛同する人が集まって作ることができたので、「やっとこれが作れるようになった」と、ある種の運命みたいなものは感じています。
神田 本作は柳楽優弥さん、有村架純さん、そして三浦春馬さんが演じた3人の主人公がいることで、若い方にも届くドラマになっていると思うのですが、手応えはいかがでしたか。
黒崎 当初、こんな企画危な過ぎて無理だよとたくさん言われました。「日本人が核開発をしていた」ということだけがセンセーショナルに取り上げられて、一人歩きしてしまうのではないかと恐れられていたのですが、意外とそういう受け取り方をする人はいませんでした。
特に若い人が見てくれた感想として、青春ドラマとして、生きていくのが非常に困難な世代だけども真っすぐ生きている姿が頼もしかったとか感情移入できたということを言っていただけているのが、自分としてはすごく勇気づけられています。
今は例えば大学生なんて2年間も大学のキャンパスに行けてないじゃないですか。だから大学で勉強を続けるという一言を取ってみても結構切実なのだろうなという問題があって、ちょっとそれを重ねて見てしまっている部分を感じます。

脚本家の仕事
神田 井上さんにお聞きしたいのですが、お仕事を引き受けるときの基準はありますか。
井上 正直なところを申し上げると、スケジュールの空きを踏まえて、話が来た順番に引き受けています。というのは、自分の好きな人とばかり仕事をしていると似たような仕事になってしまう恐れがあるからです。それが縁だなと思って。もちろん、どうしても、もう一度、組みたいと思う方もいるので、その場合は全てのスケジュールを開けてご一緒します。
神田 そうすると、頼まれたお仕事は断らないということですか。
井上 はい。決まった人と長年タッグを組んで、成果を挙げている脚本家もいるけど、私は世界観を広げてくれる出会いを求めています。どちらが正しいではありません。弁護士さんも依頼人を選ぶ方、選ばない方、それぞれではないですか。
神田 私は自分が選ばれれば、断らないようにしています。NHK では、演出する作品は割り当てられるんですか、それとも自分から手を挙げるということもできるんですか。
黒崎 僕はここ十数年は幸運なことにほとんど手を挙げてやらせてもらっています。
特に『マチベン』は、井上由美子脚本だったからやりたくて手を挙げました。僕は誰とやるかということが大事です。
脚本家と演出家
神田 脚本家と演出家は、初めは相思相愛だったのに、制作の過程で、ぶつかったり、ギャップが出てきたりするということがあると思います。
特に脚本家である井上さんからしてみると、台本が演出によっていかようにも変わってしまうということがあるのではないでしょうか。そのイメージギャップに困ったり、クレームを入れたりしたことはあるのでしょうか。作品は、映像が完成してからでないと見られないとは思うのですが。
井上 脚本の段階はただの紙、二次元ですから。これを三次元の動くものにするのは演出家なので、もう任せるしかないです。
ただやっぱりでき上がってきたものがイメージと全然違こともあります。事前のイメージと全く同じということはまずない。がっかりということもあるし、いい意味でえーっと驚くこともあります。黒崎さんは挑戦してこられるんですよ。脚本の穴をさらに掘って埋めたり、語りすぎのところをズバッと切ったり。ドキッとさせられるところがあって、そこがとてもいい。ハイリスクハイリターンの演出家の方が私は好きです。そういう思い切った演出をやってこられたから今があるというか、手を挙げた企画にみんなが乗ってくれる立場をお築きになったんだと思います。
黒崎 生々し過ぎてドキドキします(笑)。でも不思議ですよね。やっぱり井上さんの脚本に書かれているものが全てで、俳優もスタッフもみんながそれをラブレターなり設計図だと思って受け取っているので。そこからみんながどれくらいイマジネーションを広げられるかですから。僕だけじゃなくて、俳優さんだって一読したとき分からなくても、それを5回10回と読んでいって、ああ、こういうことが書いてあったんだ、見つけましたよと言ってくれることもあるし。
だから日々発見しながら撮っていくんですよね。
でもそのときにもともと書かれていることをねじ曲げたら絶対失敗するんですよね。井上脚本に書かれている本筋を絶対間違えてないぞという自信が持てている限り自由にやってくださいと言えるんだけど、そこを迷ってしまったらきっともう次の仕事はなくなるので、その緊張感で。だからいつも1話目を撮り上げて井上さんに送ってから電話がかかってくるまでの間は、めちゃめちゃ緊張して。
神田 井上さんも見られるのですか。
井上 はい。でも、これは初めて言うのですが、実は、見ないこともあります。怖くて見られないこともあります。もちろん黒崎さん演出の作品はちゃんと見ますけど。特に無言のシーンとか。
無言のシーンは演出を信じてないと書けないので、この演出家とは目指すものが違うなと思っているときはべらべらしゃべらせてしまうところはあるかもしれないですね。
黒崎 井上さんの「...」のせりふは怖いんですよ。ものすごい責任を感じて。「...」「...」「...」で最後にト書きで「ぐっとくる」と書いてあるんですよ。
井上 今の視聴者は、早見再生で見るようになってきたから、何かでき事が起こったりしゃべったりしないところは早送りされてしまう。だから「...」の記載がしづらい。
神田 脚本家と演出家の関係は、私たちの世界でいうと、いわば立法と司法の関係に似ています。演出家が脚本を書き換えられないのと同様に、私たちも法律を書き換えることはできません。
しかし、紛争の解決のために様々な利益のバランスを考えて、法律を柔軟に解釈することはできるし、可能な限りそうしていかねばならない。黒崎さんも、演出している中で、脚本のとおりではなく、このせりふはこうした方がいいのではないかという葛藤に直面することもあるのでしょうか。
黒崎 本質を踏み外すと間違えちゃうと思うんですよ、きっと意図したものとは違うものができ上がってしまう。でも例えばト書きで「泣く」と書いてあるけれども、クライマックスに至るまで役者さんが演じてきた末に、「泣く」と書いてあるところで、「私、笑いたくなってしまいました、どうしたらいいでしょうか」と言われたら、これはもう自信を持って、「じゃあ、笑っていいからやってみましょう」と言いますね。井上さんが見たら絶対喜ぶからというコンセンサスがあれば。
神田 私たちも同じような思いを抱くことがあります。そのような気持ちが強くなって、弁護士として裁判所を相手に仕事をしているだけでは物足りなくなり、国会議員になって法律を変えていこう、という人もいます(笑)。さて、井上さんは、次から次へと、お断りせずにお仕事を引き受けておられる中で、様々なアイデアをためておられると思います。アイデアのインプットはいつどんなふうにしているのですか。
井上 あえてアンテナは立てないようにしています。物書きではなく、一人の生活人として生きていて、腹が立ったり、悲しかったり、感情が揺さぶられたりしたことを覚えておいて、物語の種にしていく。見ている人と同じ目線で感じる方が伝わるかと思って。取材しに行って新聞を広げて一生懸命目を皿にして何かいいネタはないかと思うとだいたいあまり面白い話にならないので。
神田 でも世代間ギャップというか、若い人たちのことを描こうとしたときに想像と実態が違っていることもあるじゃないですか。そこのギャップは埋められるものなんですか。
井上 いや、埋まらないでしょうね、それは。
別にあきらめているわけではないですけど、無理に埋めずに、私が見た、感じた若者を臆さず書いた方が伝わるのではないかと。リサーチして描くと、現象は現代的でも、いかにもな若者になってしまうと思うんです。だから主観でいいのかなと私は思っていますけど。
神田 黒崎さんはどうですか。ご自身に自信を持って演出の仕事をやっていくにはいろいろなアンテナを張ってないといけないと思うんですが。
黒崎 確かにそういうある種のプレッシャーみたいなものもあって。今はYouTubeでもすごくクオリティーの高い映像がいくらでも見られるじゃないですか。それと同じことをやろうとしてもできるわけないし、かないっこないし、だから結局は自分がいいと思うことをやるしかないのかなという。そこにどれくらいインプットしたものが作用しているのか、自分でも分からないですけれども。

『マチベン』第4話「安楽死」
編集部 続いては最初に名前の挙がった『マチベン』の中で「安楽死」をテーマとした第4話について詳しく掘り下げてお聞きしたいのですが、ご覧になっていない方のために少しあらすじを説明します。
ある末期がんの患者が安楽死をさせてほしいと弁護士に相談します。がんが脳に転移すると、人間らしく生きられなくなるので、安楽死させてほしいとの依頼でした。弁護士はそれを受任し、病院を相手取って、安楽死を認めるべく仮処分を申し立てます。裁判所の審尋では、甲斐甲斐しく面倒を見てくれている看護師さんと患者本人の尋問が行われましたが、結局、患者の請求は認められませんでした。ざっとこのようなお話です。
神田 安楽死は、実務では刑事裁判で問題になることがありますが、このドラマでは、民事事件で、患者が病院に対して安楽死を請求するという物語でした。
井上 自分が安楽死したいと思ったときに、どういう行動に出るかという現在進行形のドラマにしたいなと。そうすれば、視聴者が自分のこととして考えられる。だから、民事だと、やっぱり、ああいう形になるのかなというのもありました。
神田 安楽死というテーマは、生命の自己決定に関わる重いテーマですが、このドラマでは、自分の最期の時間を自分らしく生きたいという前向きなメッセージにとらえていました。どのような思いが込められていたのでしょうか。
井上 私はこのドラマの1年半ぐらい前に『白い巨塔』の脚本を書いていて、たくさんのお医者さんに会いました。あるがんの専門医の先生から、死ぬ前というのはだいたい医療の流れに乗っていくしかできないから、そこに医療の限界があるみたいな話を伺ったことがふっと浮かんできて。やっぱり人生の最期って何かを選べることが一番幸せな死であり、幸せな生の振り返りなのかなと思いました。安楽死というのは1つの選択なので、そんなことが描ければいいなと思いました。
神田 井上さんのそのような思いを踏まえて黒崎さんは、演出ではどのような工夫をされましたか。
黒崎 僕もそのお話の流れを自分なりに考えている中で、弁護士の方ともお話ししたし、もちろん神田先生にいろいろなサゼスチョンをいただいて、それから当時まだ珍しかった緩和ケアを専門にする大学病院の先生とも話をしました。今では当たり前になった言葉ですけど、クオリティー・オブ・ライフ(QOL)、つまり人生の最期をどういうふうに豊かに生きるのかが延命よりも大事かもしれないという考え方が始まった頃でしたよね。
まだ世の中に一般的に受け入れられてない考え方だったのですが、今にして思えば、そういう考え方の先駆けとして、井上さんが主人公に反映させ、どう生きるかということと同時に、どう死ぬかということを選ぶ権利があるんじゃないかと。それを法律的にドラマに落とし込むにはどうしたらいいのか、いろいろなヒントを神田先生にいただきながら作ったことを思い出しました。
プロット、つまり話をどのように運んでいくかについて、僕はかなり詳細に書いて、最初にこんなシーンがあって、それで第1回の審尋の期日ではこんな話をして、第2回で証人として、受け持ちの看護師がこういう話をしてという流れを書いて井上さんにお渡しして、何度もやりとりをしながら、初稿を井上さんが書かれました。それは、プロットに書いてあった流れにほぼ即した形だったのですが、ドラマとしてものすごく胸を打つかというと、何か足りないなと思って。井上さんが送ってきたメールには、「今、書き直していますから、もうちょっと待って」と書いてありました。
その次に井上さんが書かれた第2稿は、プロットで考えていた流れを壊してあって、訴えを起こした患者の面倒を見ていた看護師が実は幼いころに離別した娘だという裏の設定があるのですが、その看護師が最後に、「裁判のことはよく分かりませんけど、私は最期まで面倒見ます」と、それだけ言って終わることになっていました。つまり、裁判を描いてきたドラマなのに、「裁判のことはよく分かりませんけど」という一言にして、物語が激変した瞬間だったのです。最後に残るのは人の気持ち。それが、井上さんが最終的に見つけられたドラマなのかと。ドラマってこういうふうに作るのだということを教えられた気がして、今でもすごく覚えています。
法律監修の仕事
編集部 病院相手に安楽死を求める仮処分を行うという流れですが、リアルの弁護士として見ていて、こんな事件絶対受けないなと思って(笑)。
井上 やっぱり、そうですよね(笑)。
神田 ドラマの法律監修は、実務に裏付けられたリアリティを伴うドラマにするという役割があります。しかし、リアリティにあまりこだわりすぎると、エンターテインメント性を損なうことになってしまいます。そのバランスをどこで取るかが難しく、でも、その点が法律監修のやりがいです。
『マチベン』の事務所には、全員で4人の弁護士がいましたが、リアリティさを出すために、主人公以外の弁護士は皆、受任に反対するわけです。
裁判のスピード感もリアリティと関係します。
依頼者は不治の病、いつ亡くなられてもおかしくはない。そうであるとすると、ゆっくり裁判をやっているわけにはいかず、仮処分手続を取る必要がありますとアドバイスしました。
それは、それでご理解いただいたのですが、傍聴人のいる法廷で、しかも証人尋問のシーンを撮りたいという希望が出てきた。いやいや、仮処分は非公開で法廷を使うことはなく、証人尋問も行われませんよとお話ししたら、それは困ると(笑)。
小部屋じゃ絵にならないと。
井上 そうでした。ご無理を言いましたね(笑)。
神田 合計2回の審尋の撮影がありましたが、1回目はラウンドテーブルにしていただき、2回目はやむなく法廷にしました。もちろん傍聴人なしです。そして、仮処分の審尋では、通常、証人尋問が行われることはありませんが、異例ではあるけれど、行われる例もないわけではない、ということで、ギリギリ悩んで、証人尋問のゴーサインを出した、という記憶があります。
編集部 事前にドラマを拝見して、この事件で裁判所が患者の請求を認める決定を出すわけがないので、結末が心配になりました。
井上 裁判所が認めるわけがないというのは、早くから神田先生に聞いていました。要するに、認められようが、認められまいが、そこで自分の気持ちを表現したいという患者を主人公とした物語にすれば、法律に詳しくない視聴者にも理解いただけるのではないかなと思いました。
神田 「こんなの実務上あり得ない」という批判を受けても、きちんと私は説明できると確信していました。
なぜかというと、依頼者である主人公が本当に安楽死を望んでいるのではなく、自分らしい時間を過ごしたいという自己決定権を主張しており、視聴者にはその思いがきちんと理解されるはずだと。
そして、依頼を受けた弁護士が、裁判の勝敗ではなく、依頼者の思いに寄り添うことが大切であり、裁判はそのための一つの手段にすぎないと思っているというメッセージが伝わってきました。だから、物語としてのエンターテインメント性もあるし、リアリティからもかけ離れない、井上さんがそういう物語を作られて、黒崎さんがそのように演出されていたと思います。
裁判は必ずどちらかが負けます。弁護士は、半分は負ける仕事をやっています。だからといって、そのときにあなたは負けますよと依頼者に言っているかというと、必ずしもそうではありません。見通しをきちんと伝えながら、一生懸命に依頼者に寄り添う伴走者として仕事をやっているじゃないですか。勝ち負けという結果ではなく、4話の弁護士も、これは沢田研二さんの役でしたが、依頼者の伴走者としての仕事を果たしたのです。
編集部 カッコよかったですね。
神田 弁護士にとって一番つらいことは何かというと、依頼者に裏切られることだと思うんです。このドラマで、沢田研二さんはかつて岸部一徳さん演じる依頼者に裏切られて、懲戒処分にまでなりそうになる。それでも今回の事件を受けるのですよ。そこがすごくよく分かるところで、私たちって裏切られても、やっぱり依頼者を突き放し切れないことがある。そこがまた私たち弁護士にとってのリアリティだったのです。
もう1つは、裁判での半分は負けと言ったけれど、勝てなくていいやではなくて、やっぱりそれは勝ちにいかなくてはいけない。たとえ見通しが厳しくても。もちろん依頼者に必ず勝てますよと言ったら、うそになっちゃうけれど、裁判所に対しては、必ず勝つという気持ちでやっている。そこをきちんと描いていただいていたので、リアリティがあったのです。
井上 法律ドラマというか、弁護士ドラマの面白さって、裁判に勝つことが負けだったり、裁判に負けたことが人間としては勝ちだったりというところではないかと思います。そこが見えたときはうまくいったなという気がしますね。

法律事務所の描き方
編集部 ところで、『マチベン』のようにドラマに出てくる法律事務所は、実際にはないと思うのですが、テレビでは不思議と法律事務所っぽく見えます。何か工夫があるのですか。
黒崎 『マチベン』の時は昭和の看板建築みたいな建物をたくさん見て歩いたのを覚えていますね。ばらばらなキャラクターの弁護士4人がここで集まって、それぞれが居心地のいい居場所を猫みたいに見つけているというイメージです。
取材していて不思議に思ったのは、同じ目の高さで分かりやすくお話ししてくださる弁護士の先生の後ろには、山のように全く理解できない書類が積み上がっていて、本棚にも全く理解できない法律の書物があるということです。
今日、僕は弁護士会館の9階で待っているときに思ったのですが、窓の外の景色がすごいじゃないですか。ここは霞が関の真ん中で、見渡す限り日本の中心地で。でも、ここで、神田先生とお話しすると、全く同じ目の高さで話してくれる。この2つのワールドが存在しているというのがすごく不思議だなと思います。
神田 この霞が関にいると見えない景色があると思っています。これが世界の景色だと思い込んだら大変なことになっちゃう。ここには法律相談センターもあるのですが、真に困った人たちが来やすい場所なのかというと、決してそうではない。
2021年7月に、当会では、弁護士会館ではなく、あえて秋葉原のレンタルルームを借りて、しかも「法律相談」から「法律」をとって、「女性のための生活、仕事、子育てなんでも相談会」という企画を実施しました。
真に困っている女性の方には、弁護士会のHP等での告知だけでは届かないのではないか。そう考えて、上野、池袋、新宿、秋葉原、五反田、そういった場所のシェアハウスや風俗店の上にある24時間託児所などを1件1件回り、チラシを置かせてもらいました。それを写真に撮って、Twitter で拡散する。そんな周知をしたところ、緊急事態宣言の直前だったにもかかわらず、2日間で合計123件もの相談者が実際に来て下さったのです。この東京に弁護士は2万人近くいるのに、私たち弁護士の力が届いていない人たちがこんなにいるんだと改めて思いました。
相談者が書いて下さった感想文の中に、「聞いてもらえただけで本当に救われた」という感想が多く寄せられました。私たち弁護士は、いかに法律という武器を使って戦うかということも大切ですが、依頼者の話をきちんと受け止める、いわば傾聴する力がもっと大切なのです。
だから、私たちの法律事務所も、依頼者が本当に自由に心を開いて話せる雰囲気なのかというところをしっかり考えなければならない。『マチベン』の事務所は、むしろあるべき理想の事務所といえるのではないかと思います。
映像制作における弁護士の役割
編集部 法律監修のほかに、映像制作の世界で弁護士がお役に立てることは何ですか。
黒崎 これは広範にわたるのではないですかね。今は膨大なコンテンツが世界中で、いろいろな形で作られるようになっていますし、個人個人がその映像を使うことも、はるかに簡単になっているじゃないですか。だからこそ、どこで歯止めをかけるかなどで弁護士さんのお力を借りることはすごくあると思います。
NHK でも法務部とはたくさんやりとりをします。1つのコンテンツを、世界にも展開したいと思ったときに、その裏付けが法律的に取れていないと、はなから戦えなくなってしまうので。年々知的財産に関する法務の役割が大きくなっているように思います。
井上 私は、法律ものではないドラマでも、このせりふが誰かを傷つけることにならないかと思った時は、弁護士さんのお力を借りることが多いですね。ハラスメントや差別など、揉め事の最前線にいらっしゃるので、結構細かいことまで弁護士さんに頼っています。
黒崎 それでいうと、また『マチベン』の数年後に井上さんとご一緒して、神田先生に助けていただいたNHKのテレビ60周年記念ドラマ『メイドインジャパン』(2013年放映)という企業のドラマがあって、日本人の技術者が中国へ渡って仕事をすることをめぐってのドラマだったんですが、技術を持ち出すことの倫理的、法律的是非を問う場面がたくさん出てくるんですよね。
そういうことについても、たくさん神田先生に教えをいただきました。今は、中国や韓国の技術にもものすごく高い分野があるということが認知されるようになりましたけど、その当時、まだ雲をつかむような話だったところで、法律的に黒か白か以前に、これは社会的にどういうふうに受け止められるドラマなんだろうみたいなことは、たくさん話をさせていただいたのが印象に残っていますね。
編集部 法律が守られているからセーフとは、言えない時代なんですよね。それを超えてどうあるべきかを企業にアドバイスしなければいけないという時代だなと思います。
神田 法律監修といっても、脚本をチェックするだけに留まらず、さまざまなご相談がありました。日付が変わってもNHKで打合せをしたり、早朝までメールのやり取りをしたこともよくありましたね(笑)。
黒崎 無理なお願いばかりですみませんでした!しかし神田先生も妥協されないので(笑)。 皆のアイディアが尽きて諦めそうになってからの先生の『もう少し考えましょう』というけん引力が凄いんです。
今後のテレビ番組
編集部 今は家にテレビがないという家庭が結構多いようですが、どうお考えですか。
井上 私は作品がテレビでの放送ではなくウェブでの配信になったとしても、ソフト自体は求められるとは思っていますね。シェイクスピアの昔から、「面白いドラマを見たい」という人間の欲求は続いています。ただ、媒体が増え、鑑賞の機会が多くなったことで、より目が肥えていくんだろうなと思っています。
黒崎 Amazon やNetflix も同列にテレビで映るし、パソコンで見ているわけなので、NHK の番組を作るというより、1人のディレクターとして面白いコンテンツを作り、自分の作ったものがその中で選んでもらえるかどうかということで考えたとき、すごく刺激的なものを作ればそれが正解なのか、ものすごくバジェットの大きなものを作ればそれが正解なのか、分からないですね。そのどっちも必要かもしれないし、どっちも間違っているかもしれないし、それぞれの作り手が自分の基準をしっかり持って作っていかないといけないと思っています。このテレビ局だからここまで作ればオーケーみたいなことが全く今、なくなってしまっているのかなと。
編集部 NHK 自体が本当にいろいろな媒体を持っていますよね。
黒崎 そうですね。今はスマホで朝ドラを電車の中で見てくださる方もたくさんいらっしゃいますし、そういう方に向けて、スマホで楽しんでもらえるドラマというのもすごく大事だし、片や4Kとか8Kとかがあって、大画面で見てもらうことを前提に作っているところもあるし、それを両立させなければいけないというのは、NHK だけじゃなく世界中の作り手が今、直面している問題なのかもしれないですね。Netflix のドラマだって、映画館でやっても鑑賞に堪えなきゃいけないし、そういうグローバルなクオリティーが求められていることにものすごくプレッシャーを感じますね。
井上 2000年代までは、地上波のゴールデンでドラマを制作するときって、みんなが見たい作品を目指していました。視聴率が30% を超え、老若男女が見て、明くる日の学校や職場などで話題にしてくれるドラマです。配信となると、ある人には、くだらないドラマと思われても、一部の人がお金を払ってでも見たいというものを作らないといけないんですよね。現在も視聴率はありますので、やっぱりたくさんの人に見ていただかなきゃと思ってしまう時もありますが、それよりも一部の人が熱狂するものが求められています。そこの意識改革は必要ですね。
若い世代に向けて
編集部 若い人が、これからの世の中を生きていくためには、どのような能力が必要なのでしょうか。
黒崎 今ドラマの撮影をやっていても、みんな本番以外はマスクを付けているわけですよ。そうすると本番のときに初めてマスクを取って、あ、この俳優さんはこういうお芝居、表情をしていたんだということが分かるんです。それは仕方なくて、みんな命を守るためにやっているわけで。ただそうすると、せりふがどういうふうに伝わってくるかということも、やっぱり口が見えていると見えてないでずいぶん違うわけですね。
言葉がどういうふうに伝わるかを考えたり、その言葉が本当にこの人の心から出てきてしゃべってくれているのかを感じ取ったりする能力がすごく大事だなとつくづく感じます。口が見えなくても、やっぱり伝えたいことが伝わると思う人もいるし、口が見えないと本当何を言っているかよく分からないと思っちゃう人もいるし。
井上 今後コロナがどうなるか分からないですし、人間のコミュニケーション能力がどう変化するかも分かりません。でも、人間はどんなに世の中が変わっても変わらない部分を持っている、そこを物語というフィクションを通して伝え続けたいですね。
神田 僕らの子どものときって、その時間にテレビの前に座らなくて1回見逃しちゃったら絶対に二度と見られないから、どんなことがあっても家に帰って真剣に食い入るように見ていたわけですよね。ビデオもオンデマンドもないけれど、今考えるとそれはとても幸せな時代でした。私はその後BPOの委員を務めましたが、最近BPOやコンプライアンスがテレビをつまらなくしているんじゃないか、というような言われ方をするときがあります。
少し脱線してしまいますが(笑)、BPOという組織は、放送局の取締り機関ではなく、放送局による自主的・自律的な向上を促し、視聴者の信頼を高めて、放送の自由を確保することを目的としています。テレビをぜひ面白くしてほしいという励ましを意見書の最後に書き添えることも少なくありません。
これからの時代、弁護士にとってどのような能力が必要かという点はとても難しい質問です。与えられた課題に対応するのでなく、自ら課題を発見する力、弁護士の力を届けるために発信する力、他の様々な組織や個人と連携する力が必要になるように思います。
当たり前だけれど、そういった努力が求められる時代です。でもその努力をすれば、仕事は広がっていくと思います。どのような業界もそうですが、資格をとれば安心ということではなく、資格をとった後の継続的な努力こそ必要であり、それは私自身の自戒でもあります。
井上 それを実践されているのは本当にすごいと思います。
神田 私は、その後もお2人といくつもお仕事をご一緒させていただきましたが、できれば次はぜひ2人に力をお借りして、法曹志望者が増えるようなドラマを作っていただきたいです。
井上 ぜひそうしたいですね。それから、今、中国のドラマ制作会社とやりとりしているんですけど、本当に権利面は課題がいっぱいです。著作権などは弁護士さんのお力が絶対に必要ですし、海外に向けても広がりがある仕事になると思います。
神田 お2人とも同世代の同業者の方のほかにも若い人たちのライバルがいると思うんです。そういう方々の作品を見て刺激を受けたり何か参考にすることもあるんですか。
井上 もちろん刺激を受けることが多いです。
焦ることもありますね。似たものは作らないというのが唯一のプライドです。だから若い人がとりあげたネタや切り口は、あっ、これはもうできない!と、扱えなくなります。必死で別の切り口を探します。どんどん封じ手が増えて、苦しくなりますが。
黒崎 会社に身を置いていると、ドラマを作るとお金も掛かるしリスクもあるから、見たことあるものが求められるんですよ。刑事ドラマで成功したら刑事ドラマがどんどん作られていくし。
漫画原作が売れていてすぐそれが映像化されるのは、それはある種の成功を見たことあるからですよね。
でも、あまたあるコンテンツの中でこれを選んでもらう理由というのは、今までに見たことないからということが非常に大きいんじゃないかなと。
自分自身にとって見たことがないもの、自分が本当に見たいと思うものを作ろうというのが心掛けていることなのかなと思います。
神田 これからの夢や目指していきたいものはありますか。
井上 これまで日本語のドラマって、外国語に翻訳されて輸出されることは多くなかったんですが、海外へも伝わるものを書いてみたいなとは思いますね。
黒崎 こんな鬱々とする気分が続く時代だからこそ、ちょっと突き抜けたコメディーが作れたらいいなと思っています。
編集部 最後に、会長は何をされたいですか。
神田 私は、そろそろ弁護士会の仕事から離れて、一人一人の依頼者に向き合い、一つ一つの事件に丁寧に取り組むという弁護士の原点に戻りたいですね。
編集部 今日は様々なお話をどうもありがとうございました。