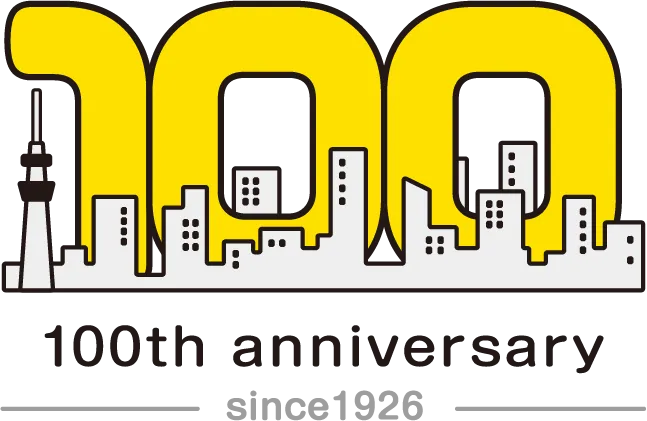インハウスレポート
チームの一員として働く
【当会会員】仲村 文博 Fumihiro Nakamura(64期)
インハウスローヤー(組織内弁護士)とは、企業に役員や従業員として所属する企業内弁護士、及び、省庁や自治体に職員(
に任期付き職員)として勤務する弁護士の総称です。
本企画は、当会所属のインハウスローヤーに経験談を紹介していただく連載企画です。
はじめに
私は、人材サービス企業の経営企画部門に所属しております。現在の職場は2社目となりますが、ファーストキャリアからずっと企業内弁護士をしております。現在の職場には1人目の法務担当者として入社しました。現在まで様々な部門を経験し、株式公開にも携わりましたので、ベンチャー企業における法務部門の役割やキャリア形成に関する経験をお伝えできればと思います。
アーリーステージのベンチャーについて
アーリーステージのベンチャー企業において、最初の法務担当者を採用する場合には会社に「何もない状態」なので一緒に会社を作っていきたいと経営者から伝えられることがほとんどだと思います。
私が入社した2014年はまさに会社に「何もない状態」で、ワークフローや職務権限が整備されておらず、締結された契約書を各担当者が管理しているなど、やるべきことが山積みでした。
また、アーリーステージであることから、会社が成長し続けなければ会社の存続自体にも影響があるため、コーポレート部門とはいえ事業成長への貢献が強く求められる時期でもありました。
そのため、契約相談や顧客とのトラブルなどの一般的な「法務」としての業務もありましたが、法務に関わる課題か否かに関わらず、とりあえず解決できそうだからと「よろず相談」を受けました。仮にそれが専門外のビジネス上の課題であっても、一緒に乗り越えることで事業の成長へ貢献し、同時に社内で法務の潜在的需要の顕在化を行うことで「法務」部門としての地位を確保・確立してまいりました。
ベンチャー企業では、法務に限らず社内のリソースが圧倒的に足りていないため、業務の境界線を明確に引かずに、拾えるボールは拾うタイプの人が活躍できると感じています。
法務から経営企画へ
私は、ビジネスモデル構築や人事制度制定など、法務の枠に留まらず幅広く課題解決に取り組んでいました。会社の事業成長が軌道に乗り、株式公開の準備が始まるに当たり、自らの経験の範囲を広げるため、新しいチャレンジとして法務部門を離れて経営企画部門に異動しました。
経営企画部門では、主体的にコーポレートガバナンスやM&A、資本業務提携、株式報酬制度、投資先管理などの各種プロジェクトを立案し、全社の従業員を巻き込んで実行していくことが求められています。具体的なプロジェクトとしては、物流プラットフォーム事業の買収や上場企業との合弁事業の推進などを担当しました。
それぞれの事業ストラクチャの設計・交渉という初期段階から関与し、M & A 実行後の統合プロセス(PMI)や事業計画の進捗モニタリングなど、M & A の適切な手続の実践と事業推進のバランスを図るなど、法務の経験を活かす機会がありました。
また、IT 大手のパートナー企業との合弁事業において、合弁会社に法務として出向したことにより、大企業のグループガバナンスや内部統制などを学ぶ機会を得られました。

株式公開における役割
私自身は、株式公開の主幹事選定から証券会社の審査、東証による審査や各種書類作成など一連のプロセスに関与してきました。
①コンプライアンス体制の整備
コンプライアンス体制の整備では、業法を含めた各種法令を順守できる体制の整備や反社会的勢力排除体制などが含まれます。当社の場合、審査項目全体からすれば事前に想像していたよりも対応項目が多くはなかったため、自らの業務をコンプライアンスのみにこだわっていた場合には経験できた範囲が狭かったと思います。
② ガバナンス・内部統制のフレームワークへの準拠
株式公開に向けた各種規程類・業務プロセスの整備や各種会議体の運営などは、一定程度のフレームワークが確立されています。
社内事情を踏まえて最適化する一方で、自社の事業成長や事業展開のスピードが速く、絶えず組織と運営体制が変化するため、フレームワークの本質を捉えて、変更内容が全体のフレームワークに影響がないか、常に判断する必要がありました。
③内部監査の実施
内部監査部門の立上及び初年度監査を担当しましたが、株式公開において求められる内部監査は主に規程監査であり、具体的には社内規程と社内業務の差をチェックし是正を進めていくことになります。会計知識は必ずしも必要がなく、また是正もガバナンスや内部統制の構築に関わることから、法務担当者や組織内弁護士が貢献できる部分と感じました。
④証券審査・東証審査への対応
証券審査においては証券会社の引受審査部門から、東証審査においては日本取引所自主規制法人から、一問一答形式の質問とインタビューを受けることになります。
社内の状況を知らない相手に、社内体制や事業について整合性を持って説明することが求められ、社内の各部門から回答に必要となる情報を提供してもらい、全体の整合を取って回答を行いました。
⑤ 各種説明資料と有価証券届出書の作成
東証審査で必要となる各種説明書類と有価証券届出書等の法定書類の2種類を作成し、後者については金融商品取引法の制限を受けます。目論見書(有価証券届出書)に記載がない項目についてはオファリング時に投資家に説明ができないため、法律事務所を含め様々な方からのコメントを踏まえて入稿日直前まで修正作業を繰り返しました。
おわりに
私は入社以来、多くの仲間に支えられて、法務に限らず様々な経験を積ませていただきました。ベンチャー企業では社内のリソースが限られるため、自分から手を上げることでキャリアの選択肢を広げることが可能だと思います。
これからベンチャー企業への転職に挑戦する方の参考になれば幸いです。