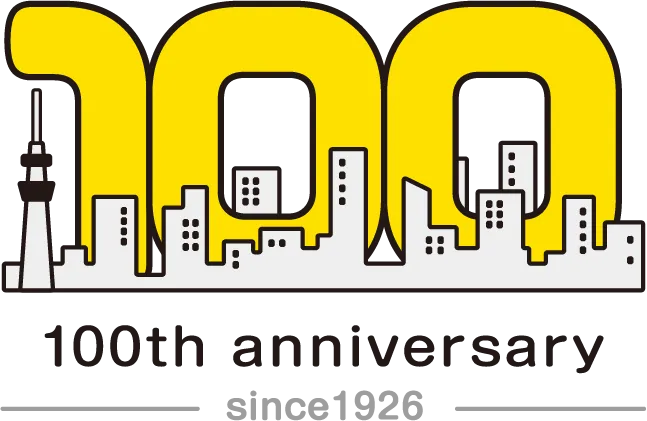少年とともに
少年とともに(約半年の付添人活動)
中野 博喜 Hiroki Nakano(73期)
1.礼儀正しいが、甘えが残る少年
本件は、大麻共同所持という大麻取締法違反事件で、私が少年の被疑者段階から国選弁護人、国選付添人として活動した事案です。初回接見で、私は少年に対して、派手な見た目とは裏腹に、礼儀正しい少年という印象を抱きました。初回接見の際、少年は接見室に入るとき丁寧に一礼し、接見室に入ると椅子の横に立ち、私に促されてから座りました。私と話すときは常に敬語で、聞かれた質問にも正直に答えてくれました。
他方で、少年は過去に喫煙による補導、バイク窃盗で家庭裁判所に送致されたことがありましたが、勾留にまでは至っていませんでした。そのため、今回の逮捕時も、特に深く考えず、すぐ家に帰れると考えていたようでした。しかし、今回は状況が違うこと、初回接見で今後の見通し(勾留として10日間の身体拘束が見込まれること)を伝えると、事の重大さを認識したようでした。
2.少年の生活状況
少年は逮捕当時18歳で、高校に進学せずに父親のハウスクリーニング業を手伝っていました。少年は、仕事に真面目に取り組み、いつか自分も父親のように一人前の仕事ができるようになりたいと語っていました。他方、逮捕される1年以上前から、少年は深夜に外出するようになり、多くの仲間と遊んでいました。少年は、仕事を通じて一人前になる目標はあったものの、日常ではどこか物足りなさを感じていて、高揚感を得るために仲間と大麻を吸うようになり、逮捕当時には、理由もなく大麻を吸う生活をしていました。
また、大麻の購入資金のために、大麻の転売もしていました。少年としては、大麻が悪いことであることを認識しているからこそ、自分と同様に大麻を使う仲間ができることが嬉しいという感覚もあったそうです。
少年は、自身の大麻使用を同居の両親には気づかれていないという認識でいました。実際に母親は、少年の大麻使用を知らず、父親は懸念していたが、少年本人に確認したときに使っていないと言われ、それを信じたということでした。
3.環境調整の際の付添人としてのスタンス
私は、少年の生活状況を聞き、少年が大麻を断つための環境調整として、①保護者の指導監督、②交友関係の整理、③少年に仕事の具体的目標を持たせることを意識しました。
このうち、保護者の指導監督については苦悩しました。少年は父親の指導の下で仕事に従事していたため、多くの時間をともに過ごしていました。
そこで父親に少年の指導監督をお願いしたところ、少年の父親は「自分も18歳までは、不良グループにいたけど、変わらなきゃいけないと思って、住居も友人関係も仕事も全部新しくした。息子も今同じ年齢だから、親に管理されているからとかそういう問題ではない。自覚の問題だ。」と話されました。もちろん父親は、少年にはそれができると期待してのことですが、私は少年の話を聞いている限り、少年が自覚だけで変われるとは思わなかったため、戸惑いました。
私は、育児経験もなく、少年の父親よりも一回り年下のため、「親としてこうあるべき」と話し合いをすること自体が適切か悩みました。そこで、私は現状の少年の様子を伝えた上で、「保護者の指導監督なしでは更生の環境としては不十分と思われる」と少年の父親に話しました。
結果的に少年の父親から指導監督するという同意を得ましたが、保護者との間で、少年との向き合い方に相違があるときに、どう話し合うかは悩ましい問題だと思いました。
4.厳しい評価
私は、当初、大麻取締法違反で初めて送致された事件であるため、保護観察になるのではないかと甘い見立てをしていました。しかし、家裁送致後に法律記録を読むと、私の聴取不足で知らなかった多くの事実があることが分かりました。調査官としてもその事実を重く受け止めて「少年院も視野に入れて検討する必要がある。」という認識でした。
そしてこの多くの事実の中には、少年が大麻を断つきっかけになり得るものがありました。しかし、それらの事実があったにもかかわらず、少年が大麻との関係性を断つことができなかったことを踏まえると、少年が自発的に変わることは難しく、少年院という選択肢も視野に入れるとの調査官の意見にも納得できました。
5.少年の内省
少年は勾留・観護措置を通じて一貫して大麻をやめたいと話していましたが、手続が進むにつれて、少年の大麻をやめたい理由に変化が生じてきました。勾留当初は、「この不自由な生活がつらい。これなら大麻やらない方がマシ。」という回答でした。しかし、勾留満期の頃になると(本件は勾留延長されて、勾留期間は20日でした。)、「家族に認めてもらいたい。特に弟・妹の前では頼れる兄ちゃんでいたい。大麻やっている今の自分はダサい。」と答えました。また観護措置の期間に、少年は、「小さいときはサッカーを頑張っていたら褒めてもらえて、もっと頑張ろうと思えた。これからは仕事とかで一人前になって家族とか友人とかに褒めてもらえるような人になりたい」と語るようになりました。
少年は、私が面会に行くたびに、A4サイズの用紙に目標を書いて渡してくれました。そこには、仕事を通じて一人前になるという目標と、それに向けてどのような行動をすればよいかなど、少年が真剣に考えた日常の意識などが細かく書かれていました。
6.3か月半の挑戦
私は調査官と電話や面談などで積極的に意見交換し、調査官が気にかけている事情については、次の面会の際に私からも同様に話をして、考えを深めてもらいました。その後も調査官の憂慮している事情を少年と話して、問題解決に向けた少年の考えを具体化するよう試みました。
その結果、調査官意見では少年の内省や環境面の変化が期待できることから、試験観察との意見になり、裁判官も審判では少年に厳しく指導をしましたが、少年の内省状況や更生も期待できる環境であるとして、試験観察に付されました。
私としては試験観察中に何をすればいいのか戸惑いましたが、少年と保護者が調査官と2週に1度面談をするということで、それに合わせて、少年や保護者と電話や面談をすることにしました。結果として試験観察中、少年は調査官との約束、保護者とのルールを全て守ることができ、私は何か特別な活動をすることなく、定期的に報告を受けるに留まりました。そこで、私から提案し、調査官との約束の中で「規則正しい生活」がルールに挙げられていたが、それはなぜ必要なルールだったのか、理由を考えてもらいました。
そして約3か月半の試験観察期間を経て、少年は2回目の審判で、「規則正しい生活の中には大麻も、大麻を使う人間関係も入ってこなかった。」と回答してくれました。また、裁判官からも試験観察期間における少年の生活を高く評価され、少年自身「100点」という自己評価をし、結果、保護観察となりました。
7.再出発
少年は試験観察中に、自動車の免許を取得し(大麻共同所持としての逮捕時に、少年は仮免許しか有しない状態で、所定の要件を満たさずに自家用車を運転していたため、仮免許を取消しされていました。)、仕事では父親から独り立ちが近いことも伝えられていました。私は審判後に、「私としても、少年は試験観察期間中、とても頑張ったと思う」と伝えたうえで、少年に逮捕されたときと今で一番大きく変わったと思うことは何か聞くと、少年は「逮捕されたときは物事を深く考えなかった。今は、自分の行動とか、ちゃんと1つ1つのことを考えるようになった。ありがとうございました。」と答え、丁寧に一礼してくれました。
約半年という期間で、少年が大きく変わることができたこと、またそれを付添人の立場で見届けることができたこと、私自身とても勉強になりました。
GIGAスクール構想の現状を知ろう
上沼 紫野 Shino Uenuma (49期)
1.研修の目的
学校で1人1台のGIGA 端末を、というGIGAスクール構想に基づき、2021年から学校で子どもたちは各自1台の端末が利用できるようになっている。
子どもや学校の実情を知ることは相談を行う上で重要であるが、GIGAスクール構想の現状は地方自治体において状況が異なるため、実際の現場の状況に詳しい西田光明氏(文部科学省ICT活用教育アドバイザー、柏市教育委員会教育研究専門アドバイザー)に「GIGAスクール構想の現状と課題」についてご講演をいただくことになった。本稿では、かかる研修のポイントを報告したい。
2.GIGAスクール構想の背景と課題
GIGAスクール構想とは、1人1台の端末と高速容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別な支援を必要とする子どもを含め、多様な子ども達を誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化され、資質・能力を一層確実に育成できる教育ICT環境を実現するものである。その背景には、日本の生徒の学習到達度の低下などがある。
2018年のPISA(OECD 生徒の学習到達度調査)では、日本の生徒の学習到達度、特に読解力の順位が大きく落ち込むこととなった※1。その理由として、テストの方式がオンライン化されたため生徒がその対応に慣れていなかったことなどが挙げられているが、別の質問調査では学校の授業でデジタル端末を利用する時間がOECD 加盟国の中で日本が#anc最下位であったこともあり※2、2019年に4年をかけて進めていく予定でGIGAスクール構想が予算化された。また、情報活用能力を「学習の基盤となる資質・能力」と基礎づける学習指導要領が2020年度から順次実施されることとなっており、日本において教育現場でのICTの利活用が重要視されるようになった。
GIGAスクール構想自体は上記のとおりICT活用能力の向上のために重要な施策であるが、コロナ禍もあり急速なオンライン対応が求められたことからその整備が急遽前倒しされることとなり、結果として2020年中に学校の通信ネットワークと児童・生徒に対する1人1台の端末が整備された。
例えば、端末やネットワークの仕様の決定なども含め、多くの部分がその導入過程で地方自治体の裁量に任される形になっているため、統一した対応がなされず、現状は各地方自治体による運用の差異が大きい。さらに、教育現場においても必ずしもICTの知識が豊富な人員がいるとは限らないことから、学校などの教育現場でも混乱が生じ、対応が追い付いていない部分も存在している。
例えば、GIGA端末の自宅への持ち帰りを認めるか否か、対象のGIGA端末でどのようなアプリを利用可能とするか(例えば、SNSの利用を許すか否か)、フィルタリング等の設定・運用など、各現場において決定し対応することが求められている状況である。保護者からGIGA端末を損傷した場合の責任の所在についての懸念が示されていることや、ネットいじめが問題となっている現状※3を鑑みれば、学校の管理下であることが明確でない状況ではGIGA端末は使わせない(GIGA端末を持ち帰らせない)、また、SNS等は利用させない、という保守的な運用となることも理解できるところであり、実際にそのような運用がされているところもある。とはいえ、元々のGIGAスクール構想の目的からすれば、GIGA端末を積極的に利用できるような環境を整えることが望ましい。
3.基本的視点
西田講師は、(情報モラルを含む)情報活用能力を学習の基盤とするための学び方として、①個別最適な学び、②協働的な学びについて言及された。続けてデジタル環境への子ども達の参加、取組に関し、子どもの最善の利益・権利を保護する旨を謳った2021年OECD勧告※4を引いた上で、学びの道具として、ICTを児童・生徒が主体的に活用できる能力を習得し、新しい時代に必要となる資質・能力の育成が重要となること、及び、情報社会を体験と通して学ぶことの重要性を述べられた。さらに、このような教育は、学校だけでは完結せず、社会につながる教育が重要であることを述べられた。学校だけでは完結しないということは、社会においても更なる支援を行うことが重要であることを意味する。
4.弁護士として考慮すべきこと
かかる研修において、今後子どもの問題に関わる弁護士として、今後以下のような点が重要であると考えさせられた。
(1)子ども達のネット利用の現状を知ること
子ども達がどのようにネットを利用し、どのようなリスクを有しているかを知ることは、事前の助言及び問題解決にあたって重要である。
(2)現場の状況を知ること
現場において何を懸念しているのか、何がボトルネックになっているかを知ることで、例えば、ルール作り等への助言などを通じて、これらの解決への支援を行うことができる。
(3)研修等の方法を再検討すること
ICT を利用した個別最適かつ協働的な学びが強調されているということは、講師が伝えたいことを一方的に伝達する従来の講座型ではなく、自ら考える機会を重視した研修方法が求められているということを意味する。近頃の弁護士会が学校等で行う研修でもワークショップ型の研修が求められるようになっているが、今後、そのような機会はますます増えるであろう。今後とも、子ども達に必要なことを効果的に届ける方法を考えていく必要がある。
なかなか学校現場の現状を詳細に知る機会はないところ、今回は、(テーマにふさわしくオンラインで)GIGAスクール構想の背景等を含めて詳細なお話を伺うことができ、貴重な機会であった。
改めてお礼を述べたい。
※ 1 2012 年調査では1位だったものが2018 年調査では11位と後退した。
※ 2 一方、児童・生徒の学校外でのデジタル端末の利用率はOECD 加盟国中でも高く、「ネット上でチャットをする」「1 人用ゲームで遊ぶ」率は、いずれもOECD 加盟国中1 位だった。
※ 3 令和2 年度文部科学省「児童・生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査」によれば、いじめの認知件数中、ネット上のいじめの割合が中学では8.1%、高校では、18.7%となっている。
※ 4 Recommendation of the Council on the Protection of Children Online(2012 年のRecommendation on the Protection of Children Online を改定したもの)