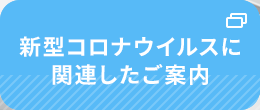東京三会合同研修会
日時:2021年12月20日(月)午後6時00分
場所:弁護士会館 2階 講堂クレオ(Zoom併用)
司会:第一東京弁護士会成年後見に関する委員会 副委員長 野嶋 真世
- 開会の挨拶:
第一東京弁護士会 会長 三原 秀哲 - 講演:
東京家庭裁判所判事 村主 幸子 氏
東京家庭裁判所判事 日野 進司 氏
東京家庭裁判所判事補 島田 旭 氏 - 閉会の挨拶:
第二東京弁護士会高齢者・障がい者総合支援センター運営委員会
委員長 大澤 美穂子
Ⅴ 後見事務
2 預り金の保管方法などについて
本人死亡後の支払に備えた預貯金の引き出しと、引き出した現金の管理方法について、どのようにしたらよいか。
現金の保管方法について、後見センターでは、ほかの財産と混同しない形での管理が不可欠であると考えている。このため、本人が死亡する前と同様、本人が死亡した後においても、弁護士個人の預かり金口座で保管することは認めていない。預かり金口座での保管については、ほかの預かり金と混同する危険性があり、本人財産の管理状況を確認するために、預かり金口座全体の履歴を確認する必要が生じ得ることから、弁護士が預かり金口座の届出や記録を行っているということのみをもって、直ちに預かり金口座による保管を許容することは相当ではないと思われ、どのような条件が整えば許容する余地があるかについても慎重に検討する必要があると考えている。
また、2020年12月に行われた三弁護士会の合同研修でも説明差し上げたとおり、紛失や盗難の危険を考慮し、成年後見人等による本人財産の管理は、預貯金の形で行っていただき、現金による管理額は50万円を超えない限度とするスタンスを原則としている。すなわち成年後見人等が50万円を超える現金を保有する場合には、本人名義の預貯金口座へ入金を求めるということになる。

こうした原則の例外の1つとして、本人の死亡が間近に見込まれる状況において、本人の死亡後に想定される必要な費用の支払いの原資として、成年後見人等が、その管理下にある本人名義の口座から50万円を超える現金を引き出して保有することは、当該引き出し及び保有の必要性がある場合に該当すると考えられる。後見人等の事務の仕方としても不当なものではなく、後見人等の裁量の範囲内における事務遂行と考えられる。
こうした状況における必要な範囲での現金の引き出し及び保有については、必ずしも裁判所への事前連絡は必要ではなく、後見終了時の報酬付与申立てに伴う最終報告において、事後的に説明していただければありがたい。
また、本人の死亡直後、本人名義の口座凍結前に、緊急に必要となる費用の支払い原資を確保する場合などの理由で、本人名義の口座から必要な範囲で50万円を超える現金を引き出すことは、本人の死亡に伴う成年後見人等の任務終了後の行為となり、後見等の終了時の応急処分や本人の相続人全員のための事務管理としての要件を満たす限り正当化されるが、通常はいずれかの要件を満たすものと考えられる。
したがって、本人の死亡直前の時期における引き出しの場合と同様に、必ずしも裁判所への事前の連絡は必要なく、終了時の報酬付与申立てに伴う最終報告において、事後的に報告していただければよいと考える。もっとも、事後報告においては、裁判所に対し、当該現金の引き出し及び保有が合理的理由に基づく必要な金額の範囲で行われたことを説明していただく必要があるため、裁判所においてもこの点に疑義があれば、追加の説明や資料の提出を求めることがある。
なお、原則の例外として50万円を超える現金を引き出した後の保管方法について、当初の見込みと異なり長期間保管するといった状況が生じたため、弁護士個人の預かり金口座で保管することの可否について問い合わせを受けることがあるが、先ほど述べたとおり、弁護士個人の預かり金口座で保管することは、ほかの預かり金との混同をする危険性があることから、認めていない。
長期保管となる場合の保管方法について、そのような混同の危険性がなければ、その余の具体的な管理方法の選択については、後見人等の裁量判断に任されていると考えている。例えば、本人死亡後であっても、金融機関に入金が可能であれば、いったん本人口座に入金し、支払いの必要が生じた段階で死後事務許可を受けて払い戻しを受ける、又は早期に相続人へ引継ぎを行うといった対応も考えられる。また、場合によっては、後ほど説明する民法918条2項の相続財産管理人選任を検討することも考えられる。もとより長期保管とならないように、本人の死亡後に想定される必要な費用の発生する時期及びその額の算定、引き出し時期の正確な見通しの検討が大切だと考えられる。
3 本人が遺言執行者となっている場合の処理
被後見人等である本人が遺言執行者となっている場合、後見人等としてどのような対応が考えられるか。
被後見人、被保佐人、被補助人であるということは、まず遺言執行者の欠格事由には当たらないため、本人が遺言執行者となることはできるということになる。そして本人を遺言執行者に指定する旨の遺言が存在する場合、本人は就職を承諾するか否かを決定することになるが、その判断に保佐人、補助人の同意は原則として必要ない(もっ
とも保佐人、補助人の同意を得なければならない旨の審判がなされている場合には、同意が必要となる。なお、本人が被後見人であって判断能力がない場合には、承諾は無効になる。)。
本人が相続人などから就職を承諾するか否かの催告を受け、相当期間内に確答しなかったときには、就職を承諾したものとみなされることになる(なお、本人が被後見人である場合には、意思表示の受領能力がないため、就職を承諾したものとはみなされない。)。
本人が就職を承諾しなかった場合、当然のことながら後見人等が関与する必要はまったくないので、何も問題は生じないことになる。本人が就職の承諾をしたか、あるいは期間経過によって承諾とみなされた場合、実際には本人が遺言執行者としての職務を遂行するのは困難なことが多いと考えられるが、本人の財産管理能力が不完全であれば、解任、辞任の正当事由があるときに当たると考えられるため、利害関係人が遺言執行者の解任を請求するか、本人が辞任の申立てをするということが考えられる。なお本人が被後見人である場合には、後見人が本人の承諾を取り消すということも考えられる。
通常は解任、辞任で対処すれば足りると考えられるが、復任のやむを得ない事由があるとして、保佐人、補助人に遺言執行者の任務を委任することも考えられる。仮に本人が保佐人、補助人に遺言執行者の任務を委任する場合には、代理行為目録の既存のチェック項目にチェックするのではなくて、例えば「被相続人〇〇の遺言執行者としての職務」などと明確に記載することになると考えられる。
なお、本人が被後見人である場合には、本人が復任契約をすることはできず、後見人が本人に代わって遺言執行者になるとしても、遺言執行者の一身専属性との関係でも疑問が生ずる余地はある。本人が遺言執行者として遺言執行できない場合において、後見人などを候補者として遺言執行者選任の申立てをすることについては、遺言の内容などにもよるが、本人が受遺者であるときに、後見人等が遺言執行者に選任されると、本人との関係で利益が相反することになることは念頭に置く必要があると考えられる。
もっとも、東京家庭裁判所における事務分配の関係において、遺言執行者を選任する家庭裁判所は後見センターではない。このため、どのような基準及び考慮要素に基づいて遺言執行者を選任するか、本件のような場合についてどのような基準に基づいて判断するかについては後見センターでは判断しておらず、その点について回答することはできない。
なお、後見人等が遺言執行者に選任された場合、遺言執行者の報酬は、遺言者がその遺言に報酬を定めたときにはその額になる。定めがないときには、遺言執行者は相続人に対して報酬についての協議を求める、又は家庭裁判所に報酬付与の申立てを行うことになる。家庭裁判所は後見人等の報酬とは別に、遺言執行者の報酬を定めることにな
る。遺言執行者の報酬は、一般的に遺言執行の状況、遺言執行に要した労力、遺言執行者として管理していた財産の額や内容、種類、遺言執行の難易、遺言執行者と遺言者及び相続人との身分関係、諸般の事情を考慮して定めることになる。
遺言執行者の報酬は、当該裁判所の報酬決定に基づき受け取ることとなるため、後見センターにおいて遺言執行者の報酬決定があったのか、その決定を受けて報酬を受領しているのか把握することはできない。そこで後見人等の報酬付与の申立てを行う場合には、遺言執行者の報酬については別途受領済みである旨の記載をしていただくとともに、遺言執行者の報酬決定の写しなどを資料として添付していただきたい。

4 代理権付与の取消しについて
代理権付与の取消しについて基準などはあるのか。本人の意向、本人保護の必要性、保佐人・補助人の意見などは考慮されるのか。
代理権の対象行為には、継続的に行うものもあれば、1回限りでその目的を達して終わるものもある。1回限りの代理権については、当該行為が終了すれば当該代理権を存続させる必要はなくなり、継続的な代理権についても、その存続の必要性がなくなる場合や、本人の判断能力の回復に伴い、ノーマライゼーションの観点から、一部に限定する場合などがあると考えられる。例えば、預貯金の管理全体ではなくて、一部の口座に限ることもある。
このため、保佐及び補助について、民法の規定に基づき代理権付与の一部又は全部の取消しを定めているところである。具体的にどのような場合に代理権付与の取消しが認められるのかについての形式的な基準はなく、事案に応じて個別に判断している。
一般論としては、代理権付与の取消しの必要性、相当性ということになり、代理権の対象行為の性質、本人の判断能力の状態、本人の生活状況、財産状況、代理権付与の継続による具体的な本人保護の必要性、本人の意向等が考慮要素として考えられ、これら考慮要素から総合的に判断している。そのため本人の意向が強いとしても、本人保護の必要性などが高ければ、その申立てを却下するということになる。
他方で、申立時において預貯金等、金融機関の預貯金及び出資金に関する金融機関等との一切の取引〔解約(脱退)及び新規口座の開設を含む。〕という定型的にある代理権付与がされていたところ、本人の判断能力の程度、本人の生活状況などを踏まえた本人保護の必要性などから、特定の口座について本人の管理に委ねるといったことはあ
ると考えられる。
例えば、本人が就労施設で働いていて、工賃などを受け取っている場合、この工賃については本人の管理に委ね、その他の口座については保佐人又は補助人が管理するということも考えられる。こうした場合には、特定の口座についてのみ代理権を付与する内容に変更することは考えられる(当初の代理権付与の内容との比較においては、一部
取消しということになると考えられる。)。
代理権付与の取消しの審判をするに当たっては、本人の陳述聴取、保佐人、補助人の陳述聴取は必要とされていないが、申立人が本人であるときを除いて、何らかの方法で陳述を聴取していることが多く、本人や保佐人、補助人の意見も判断の際には参考にしている実状にある。
5 本人の居所変更について
本人が入院した場合、どの程度の期間が経過したときに、家庭裁判所へ報告すべきか。報告すべきかについて、どのような事情を考慮すべきか。
本人が入院するなどにより、一時的に本人の居場所が変更になった場合に、逐一ご報告いただく必要はない。ただし、当該入院が長期に及ぶなど、本人の居所の実質的な変更につながるような場合には、定期報告時期ではなくとも裁判所に連絡票などで報告していただきたい。
もっとも、どの程度の期間をもって長期に及ぶと見るかについての具体的な基準はなく、本人の状態、退院見込みの有無、及び時期などの事情を考慮して、後見人等において判断してご報告いただくことになる。なお、定期報告において、後見等事務報告等を提出していただいているところ、現行の後見等事務報告書においては、本人の生活状況を記載することになっているため、前回の定期報告以降、本人の住所又は居所に変更があった場合には、資料とともに報告していただくことになっている。
そして長期入院等による本人の居所の変更など生じた場合、通常、定期支出の変動や臨時支出が生じていると考えられる。こうした定期支出、定期収入の変動、臨時支出、臨時収入などがある場合には、定期報告で提出される後見等事務報告書に忘れずにその旨を記載していただきたい。そのほか代理権付与の申立て、辞任、選任の申立てなどを行う機会には、手続上、本人に書類を送る必要があることから、本人の居所を報告していただく必要もある。
本人の居所の変更に際しては、裁判所がどのような点を説明していただきたいのか、どのような資料を求める場合があるかなどについては、「成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック(Q&A付き)」(令和3年4月)26ページ以下に記載しているため、そちらも参考にしていただきたい。
Ⅵ 後見制度支援信託・支援預金
1 支援信託、支援預貯金を利用する場合について
1 利用を要しない場合があるか
高額な資産を有している場合、家庭裁判所としては、不正防止の観点から、本人の財産を適切に管理するための措置を講じる必要があり、その方法として、支援信託や支援預貯金を利用する方法のほかに、後見監督人を選任することが考えられる。したがって、高額な資産を保有している場合でも、後見監督人が選任され、後見監督人において適切な監督がなされていれば、必ずしも支援信託や支援預貯金を利用することは求めていない。
2 専門職関与の要否
後見制度支援預金は平成30年6月から、後見制度支援貯金については平成31年4月から、それぞれ運用が開始されているが、後見センターにおいては、それ以降、現在に至るまで、管理継続中の事案(いわゆる継続事案)のうち、親族後見人において単独で支援預貯金の利用を検討することが相当と認められている事案については、専門職関
与を不要とする旨の運用を行っている。他方で、後見開始直後のいわゆる新規事案に加えて、継続事案のうち本人の収支状況が不安定であるとか、親族後見人の理解が十分でないなど、親族後見人において単独で支援預貯金の利用を検討することが相当でないと判断された場合には、専門職の関与は必要とするという旨の運用を行っている。
これに対して、親族後見人が後見制度支援信託を希望する場合には、現状では、新規事案か継続事案かを問わず、一律に専門職の関与を必要とする旨の運用を行っている。ただし、後見制度支援信託を利用する際に、専門職関与をどこまで必要とすべきかという点については、親族後見人などの強い要望や、基本計画が掲げる不正防止の徹底と利用しやすさの調和の観点などに鑑みて、当庁においても中央での議論の推移等を見極めた上で、今後あらためて検討する場合が生じてくるかもしれないと考えられる。
3 有価証券等の組入れの要否
支援信託等を利用する目的は、不正を防止することにあるため、信託利用後に後見人の管理する流動資産が高額にならないということを前提としている。その場合の流動資産は、現預金のみならず、換価が容易な有価証券も含まれるということになる。したがって、親族後見人等において、本人の意思や配当金収入のメリットを考慮して、有価証券をそのまま保有したいというような意向を有している場合には、監督人を選任することが多い。
なお、後見人において、有価証券を売却した上で信託を利用したいという意向を示した場合には、それを認めているが、裁判所のほうから信託利用のために有価証券を売却するよう求めることはない(有価証券売却の意向がなければ、裁判所としては監督人の選任を検討することを基本としている。)。
Ⅶ 後見人等の辞任
1 どのような場合に辞任が認められるか
実務上よく見られる申立て理由の例として、①本人、親族との関係悪化により後見等事務の継続が困難になった場合、②成年後見人等の高齢、病気その他状況の変化によって、後見事務の継続が困難となった場合、③成年後見人等ないしは本人の遠隔地転居により、後見等の事務の継続が困難となった場合、④専門職が対応すべき課題が解決するなどして、今後は成年後見人等を専門職から親族等に交代することが望ましいと考えられる場合、⑤信託等後見人における信託の適否判断・手続の終了などが挙げられる。①から③は、現後見人等による事務継続が困難であることを理由とするものであり、④と⑤は状況に即した選任形態の変更ということで整理できる。成年後見人の辞任については、「正当な理由」という要件が課され、裁判所の許可を要するとされているが、これは成年後見人等の辞任によって本人の利益が害されることを避けるためである。したがって、成年後見人等の辞任に正当な事由があるといえるかどうかは、一般論としては、①成年後見人等が主張する辞任の必要性が実際に認められるかどうか、②当該辞任によって本人の利益が害されるおそれがないといえるか否かという観点から判断をしていくことになる。
そして、先ほど説明した辞任を求める理由のうち、現成年後見人等による後見等事務の継続の困難さを訴える場合については、成年後見人の主張する事情によって後見事務の継続が真に困難であると認められれば、本人のために成年後見人等の交代はむしろ必要ということになるので、通常は正当な事由があるものとして辞任が許可されると
考えられる。
他方で、辞任許可の申立てに理由が挙げられているけれども、当該主張に係る事実関係の実態が認められないなど、実質的には辞任の必要性が認められない場合には、正当な事由があるものとはいえず、辞任は許可されないということになる。
また、不正行為や不適切事務などを行った後見人が、自らの不正行為や不適切事務などを認めて辞任許可の申立てをする場合には、当該事実が解任事由に該当し、結論として解任相当であると判断される場合には解任の判断が先行するので、結果として辞任は許可されないということになる。
上述の④、⑤の状況に即した選任形態の変更については、選任形態の変更が必要であり、かつ変更後の体制による後見等事務の遂行に不安がなければ、通常は辞任が許可されるということになる。この状況に即した選任形態の変更については、柔軟な選任形態の見直しという観点からもう少し詳細に説明すると、実際の実務においては、本人の
抱える課題やニーズの変化、成年後見人等の状況、成年後見人等への支援の有無、保有資産の変化など、後見等開始後に状況が変化することで専門職を新たに関与させる必要が生じたり、逆にそれまで専門職が対応してきたけれども課題が解決した後は親族だけで対応できるようになったり、あるいは市民後見人等の単独選任に選任形態を変更することが相当であったりすることがありうる。
成年後見制度利用促進基本計画において求められている、「利用者がメリットを実感できる制度・運用」への改善の一環として、本人の権利擁護の観点から、状況の変化に応じて成年後見人等の選任形態を見直し、よりよい運用をしていくための成年後見人等の交代や追加選任については、これまで以上に柔軟に考えていくべきである。
例えば、本人が保有する不動産をめぐる紛争を解決し、不動産を売却し、そして本人が施設に入所するまでの間は専門職が後見事務を担い、その後、本人が施設で安定的に生活できるようになり、収支が年金収入で、支出は口座引落しの施設利用料程度というように収支が単純化された段階では、親族に後見事務をバトンタッチするというようなことは十分考えられる。
もちろんそのようなケースは専門職に代わって後見事務を行うべき親族候補者がいるということが大前提になるが、そもそも専門職の選任に反対していた親族であっても、課題解決までの短期間であれば専門職の関与に納得していただける場合もあるので、ケースに応じて柔軟に対応していくことが求められていると考えられる。
したがって、裁判所においても、このような観点から、当初予定していた課題が解決し、専門職後見人等の関与が不要と考えられる場合や、事後の課題の変化等により他職種への変更が必要と考えられる場合(例えば、法的な課題があって弁護士が後見人に選任されていたが、その後法的課題が解決されて、他方で身上保護面での課題が生じたような場合には、弁護士から社会福祉士への交代ということも考えられる。)には、従前の専門職後見人等に辞任を検討していただくということがあり得ると考えられる。
また、事案によっては専門職に後見等監督人として関与いただいていたが、当初の見立てよりも課題が複雑困難であったということが判明した場合には、後見人等として関与していただく方が望ましいという場合もありうる。そういった場合には、後見監督人を辞任していただいた上で後見人にスライドしていただくことも考えられる。
裁判所としては、本人の課題やニーズに応じて柔軟に選任形態を見直していく必要があると考えているので、専門職後見人等におかれても、こうした観点で後見人等の交代が必要と考えるような事情であるとか、あるいは監督人としてではなく後見人として関与する方が望ましいと考えられるような事情がうかがわれる場合には、ぜひ情報提供をお願いしたい。
2 資産高額を理由に選任された専門職後見人等の辞任について
どのような場合に辞任が認められるか、その目安はあるかという問題については、まず流動資産が高額になった場合の後見センターの運用につい
て説明する。
後見センターとしては、親族後見人が選任されている場合は、一般的に本人の流動資産額が概ね1000万円以上であり、後見制度支援信託・預貯金の利用をしないときは、原則として専門職後見監督人を選任することにしている。なお、本人の流動資産額が概ね1000万円以上であるか否かにかかわらず、重点的な監督を要すると考えられるケース、例えば、本人と後見人との間に高額な立替金があり、その清算について本人の利益を特に保護する必要がある場合や、本人から親族に対する多額の贈与が予定されているというような場合にも、後見監督人を選任することがある。
このほか親族後見人が後見事務を遂行するについて、監督という観点から指導、助言を要すると認められる場合に、後見監督人を選任することもある。このような東京家裁における後見監督人の選任のあり方については、「後見センターレポート」の22号(令和2年1月号)、あるいは「後見・保佐・補助開始申立ての手引」(令和3年4月版)11ページにも記載があるので、これらもご参照いただきたい。
後見監督人を選任した場合にも、その後の事情変更や課題が解決するなどして監督の必要性がなくなった場合には、後見監督人において辞任を検討していただくことになる。
したがって、高額な流動資産額があることを理由に専門職が選任された場合については、事情が変更すれば当然辞任していただくことはあり得る。具体的には、親族が後見人等である場合で、収支が赤字であるなどして流動資産額がおおむね1000万円を上回る可能性がない場合で、ほかに課題がなく、かつ親族後見人等のみで事務を遂行していくことが可能と監督人において判断された場合は、辞任を検討していただくこともあり得るであろう。
Ⅷ 本人死亡後の引継に関する問題
1 民法870条の後見の計算について
民法870条の条文は「後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算をしなければならない」となっている。
まず、本人が死亡した場合には、成年後見等は当然に終了し、成年後見人等の法定代理権等の権限も消滅する。この場合、後見人等は2か月以内にその管理の計算をする義務を負うものとされている。ここにいう「管理の計算」とは、成年後見人が就職してから後見終了に至るまでに後見事務の執行に関して生じた財産の変動及び現状を明らかにすることとされている。この「管理の計算」のことを「後見の計算」ということもある。
なお、後見監督人があるときには、「後見の計算」は監督人の立会いをもってしなければならないとされている。
この「後見の計算」につき、誰に報告をすべきかという点については、民法に明確な規定はないが、本人死亡の場合には、その相続人に対して行うべきものと一般的には解されている。なお、裁判所や後見監督人は、後見監督の作用として当然に計算書の提出を求めることができるとされている。
2 同意書の要否
本人死亡後に相続人に相続財産を引き継ぐに際し、相続人が複数存在する場合であっても、相続人のうちの1人が相続財産を引き継ぐ意向を有しているのであれば、ほかの相続人の意向にかかわらず相続財産すべてをその相続人に引き継ぎ、引継書を提出していただくことで差し支えない。したがって、後見センターとしては、相続人全員の
同意書の提出までは求めていない(相続人間で相続財産をめぐる紛争が生じたとしても、それは相続人間で解決すべき問題である。)。
もっとも、元後見人等がそのような引継ぎをした場合に、後に相続人間のトラブルに巻き込まれるおそれもあるため、専門職後見人等としては、一般的にはそのような引継ぎを行うことには消極的であり、相続人全員の合意によって受領代表者を選任していただいて、その者に引き継ぐという形が多いものと認識している。他方で、既に財産管理権を失っている元後見人等が長期間にわたって相続財産を管理していることは、法が想定しないものとも考えられ、また、既に後見事務終了までの報酬を付与している以上、引継ぎまでの財産管理に要した労力を報酬に反映させることが困難な場面も出てくる。
そのため、相続人間の対立が激しく、引継ぎが困難であるなどの事情がある場合には、民法918条2項に基づく相続財産管理人の選任の申立てを検討していただくことになると考えられる。
3 民法918条2項の相続財産管理人選任について
1 どのような場合に申立てするのか
後見センターに申立てがされるのは、元後見人等において相続人に財産を引き継ぐことが困難な事例ということになる。例えば、先ほど説明した、相続人のうちの1人が引き継ぐ意向を示しているものの、相続人間の対立が激しく、その者に相続財産を引き継ぐことによりほかの相続人から責任追及されるおそれがある場合や、あるいは、相続人全員が遠隔地に居住していたり高齢であったりして、引継ぎに応じないというような場合、このほか元後見人が親族である場合で、独力による相続人調査ができずに、戸籍上の相続人の存否が確定できないような場合にも、申立てを検討していただくということになる。
2 申立てに際して必要な資料
申立てに当たっては、本人が死亡したことを裏付ける資料(死亡記載のある除籍謄本や後見登記閉鎖事項証明書等)のほか、以下のような資料が必要となる。
まず1つ目として、本人について相続人が存在することを裏付ける資料が必要となる。戸籍謄本等が考えられるが、申立ての段階においては、相続人が1人でも存在することが明らかであれば、必ずしもすべての相続人を戸籍によって明らかにする必要はない。
それから2つ目として、相続財産の保存のために相続財産管理人の選任を要する事情の裏付け資料が必要となる。例えば、元後見人等が相続人に引継ぎに応じるよう求めた連絡文書であるとか、これに対して引継ぎを拒絶する内容の相続人の回答書などが考えられる。申立書において具体的な事情が説明されている場合、疎明資料は必ずしもそこまでは求めていない。もっとも、通常は後見事件の記録において、ある程度の事情は判明していることが多いと考えられる。
その他、相続財産目録及びその裏付け資料については、元後見人が候補者となっている場合には、申立て時点で必ずしも提出しなくてもよいが、提出がない場合には、選任後の初回報告で提出を求めるということになる。
以上は一般論であり、事案に応じて提出いただく資料は異なることがあるため、あらかじめご照会いただくか、ひとまず申立てをした上で追加の指示をお待ちいただきたい。
3 誰が選任されるのか
裁判所において当該事案ごとに適任者を選任しているが、後見事務の内容や親族の状況等を把握している元後見人等に委ねた方が相続人への引継ぎが円滑になされると判断された場合には、元後見人等がそのまま相続財産管理人として選任されるということもある。このため、もしそのまま相続財産管理人としてご協力いただけるということであれば、そういったことを申立書にご記載いただきたい。
4 選任に要した手続費用
審判書においては、手続費用は申立人の負担とされていることが多いかと考えられるが、元後見人による相続財産管理人選任の申立ては、相続人全員のための事務管理と見ることもでき、本来的にその費用を元後見人自身が負担する理由に乏しいと考えられることから、相続財産管理人としての立場において、申立てに至った元後見人等の間で精算することは十分あり得るものと考えている。
5 民法918条2項の相続財産管理人の職務
民法27条ないし29条が準用されているため、不在者財産管理人の権限と同一の権限を有するということになる。ただし、民法918条2項の相続財産管理人の具体的な職務としては、相続人に相続財産を引き継ぐということになる。したがって、引継ぎに向けた準備、すなわち元後見人等から相続財産を引き継ぎ、戸籍を調査して相続人を確定して、財産目録を作成するといったことをしていただくことになる。
注意していただきたいのが、民法952条の相続人不存在の場合の相続財産管理人との違いで、民法952条の相続財産管理人は、相続財産の清算に向けられた手続きの積み重ねが予定されているが、民法918条2項の場合にはそういったことは予定されていない。
したがって、選任公告や相続債権者等に対する請求申出公告等は予定されておらず、相続財産を換価したり清算するということも想定されていない。
また、預貯金については、被相続人名義でそのまま引き継いでいただければ足り、不動産については相続財産管理人名義に移転登記することは想定されておらず、そのまま管理をしていただければ足りる。中には管理人において不動産の登記名義を変更しようとしたり、不動産を売却して清算しようとされたというようなケースもあったが、そのようなことは想定されていないため、ご注意いただきたい。
6 相続人不存在が判明した場合
相続人の不存在が判明した場合には別途民法952条の相続人不存在の相続財産管理人の選任が必要となるため、この場合には家事1部1係の方に別途申立てをしていただくことになる。
7 管理期間
管理期間については、相続人に相続財産を引き継ぐために選任されているため、引継ぎ業務が終了するまでということになる。より具体的には、相続人に相続財産を引き継いでいただいた上で、管理終了報告と併せて相続財産管理人選任処分取消しの申立てをしていただき、裁判所において選任処分取消審判がなされた時点で任務が終了ということになる。
8 法改正について
令和3年4月の民法等の一部改正によって、新たに民法897条の2第1項の相続財産管理人の制度というのが新設されたが、この条項による相続財産管理人の権限、義務、職務については、民法27条ないし29条の不在者財産管理人に関する規定が準用されているため、現行の民法918条2項の相続財産管理人の権限から変更はないものと考えられる。
なお、相続財産保存のための相続財産管理人の選任要件について、民法897条の2第1項ただし書で限定が付されている。すなわち、①相続人が1人である場合において、その相続人が相続の単純承認をしたとき、②相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、③民法952条1項の規定により相続財産の清算人が選任されているときには、新しい民法897条の規定による相続財産管理人は選任できないこととされているため、この点はご注意いただきたい。
4 火葬・埋葬契約等について
1 死後事務に関する規定の概要
本人が死亡したときには成年後見は当然に終了し、後見人の法定代理権等の権限も消滅する。しかし、その後も後見人であった者において本人の火葬に係る契約などを締結して、その費用を支払うために預貯金を引き出すなど、一定の事務を行うことが期待され、事実上これを拒むことが困難な場合がある。
成年後見終了後の事務に関しては、従来から応急処分や事務管理の規定によって対応されてきたと考えられるが、こうした規定によっては十分な対応ができない場合があり、また後見人が行うことのできる事務の範囲も明確でないと指摘されてきた。そこで、成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法
律(いわゆる「円滑化法」)の制定によって、民法873条の2において死後事務に関する規定が新設され、後見人は、本人の死亡後も同条1号の特定の相続財産の保存行為、同条2号の弁済期が到来した相続債務の弁済、そして、同条3号の火葬又は埋葬に関する契約の締結、その他相続財産の保存に必要な行為を行うことができるものとされ、後見人の権限の明確化が図られた。また、同条3号の行為については、一般に相続人等に与える影響が大きいことに鑑みて、家庭裁判所の許可を要するものとされている。

2 火葬又は埋葬に関する契約とは
「火葬又は埋葬に関する契約」とは、本人の遺体の引取りや火葬等のために行う葬儀業者等との契約の締結をいう。なお、「火葬」と「埋葬」については、墓地、埋葬等に関する法律2条に定義があり、「火葬」は「死体を葬るためにこれを焼くこと」をいい、「埋葬」は「死体を土中に葬ること」、いわゆる土葬ということになっている。両者は両立しない関係にあるが、この2つを同時に申し立てられる例が散見されるため、注意していただきたい。
実務上、「火葬又は埋葬に関する契約」に当たるか否かが問題になるものとして、納骨や葬儀、永代供養などがある。納骨は、火葬に関する契約に準ずるものとして、死後事務許可の対象になり得るものと解される。これに対し、葬儀や永代供養については、その施行が公衆衛生上不可欠というわけではなく、法律上の義務として課せられているわけでもない上、供養のあり方は宗派や規模によってさまざまな形態が考えられるところ、その施行方法や費用負担等をめぐって事後に相続人との間にトラブルが生ずるおそれもあることなどから、これを「火葬又は埋葬に関する契約」や「その他相続財産の保存に必要な行為」に含まれると直ちに判断するのは困難であると考えられている。もっとも、実務上、通夜や告別式等の宗教儀式を伴わない火葬のみの葬儀形態(火葬式)については、本来の許可対象である火葬に伴い、社会通念上いわば必然的に生ずる役務の提供等と評価し得る限りは、1個の火葬に関する契約と解した上で、死後事務許可の対象とされることもある。ただし、火葬と一体の関係にあるか否かは、事案ごとの個別の判断ということになる。
3 預貯金の払戻しについて
後見人が火葬や納骨等に関する契約を締結し、これに基づく費用の支払いをすることは、相続財産に属する債務の弁済となるため、当該支払いのための預貯金の払戻しは、通常は、「その他相続財産の保存に必要な行為」に当たるものとして、許可が必要になる。
これに対して、葬儀に関する契約については、先ほどの説明のようにそれ自体が「相続財産の保存に必要な行為」に該当すると判断されない場合には、その費用の支払いのための預貯金の払戻しについても「その他相続財産の保存に必要な行為」に該当するとは直ちには判断されないこととなる。
また、相続人の1人が喪主として葬儀を執り行って葬儀費用を支払ったというような場合には、当該費用は葬儀に関する契約を締結した相続人において負担すべき性質のものであり、当該相続人への支払いを直ちに相続財産に属する債務の弁済と解することはできないので、特別の事情のない限り、当該相続人への支払いのための預貯金払戻し
を「相続財産の保存に必要な行為」と見ることは困難である。
4 死後事務が許可されるための要件について
民法873条の2により死後事務の許可が認められるための要件は、①必要性と②「相続人の意思に反することが明らかなとき」でないことの2つである。まず、①必要性については、例えば、本人の相続人と連絡が取れないとか、相続人が遺体の引取りを拒んでいるなどの事情によって、成年後見人が火葬等の契約を締結する必要がある場合や、入院費の支払いを請求されているが、相続人の連絡先が不明であるなどの事情によって、成年後見人が支払いをしないと相当期間債務の支払いがされないこととなる場合などが想定される。
次に、②「相続人の意思に反することが明らかなとき」でないことについては、本人の相続人が同意していることまでは要求されていない。そこで、当庁の申立書式は、相続人の意思に反することが明らかでない場合として、相続人の存在が明らかでない場合、相続人が所在不明の場合、そして相続人が疎遠である場合という3類型を示した上で、その具体的な説明を求めることとしている。
また、民法873条の2による死後事務は、「相続人が相続財産を管理することができるに至るまで」という時間的な制限が設けられている。これは、基本的には、相続人に相続財産を実際に引き渡す時点までを指すものと解されている。もっとも、成年後見人は本人の死亡後2か月以内に管理の計算をして、相続人に財産を引き渡す義務を負っていることからすれば、成年後見人が相続財産を相続人に引き渡さない限り、いつまでも死後事務を行うことができるというのは相当ではない。したがって、成年後見人が引継義務を履行することができる状況にあり、かつ、相続人もいつでも相続財産の引継ぎを受けることができる状態になった場合には、相続財産を管理することができる状態
に至ったものと考えられ、成年後見人は死後事務を行う権限を有しないことになるものと考えられる。
5 従来の運用との関係について
円滑化法の施行により、火葬等の契約は家庭裁判所の許可を得て行うこととなるが、他方で、従前から存在する応急処分又は事務管理の規定に基づいて死後事務を行うことは直ちに否定されるものではない。したがって、民法873条の2第3号に該当する行為であっても、それが応急処分に該当するものと認められる場合には、成年後見人が家庭裁判所の許可を得ることなく行うことも許容されるものと考えられる。
6 保佐、補助に適用されるか
民法873条の2に基づいて死後事務を行うことができるのは成年後見人のみであり、保佐人や補助人は含まれていない。これは、保佐人や補助人は成年後見人のような包括的な財産管理権を有しておらず、特定の法律行為について同意権や取消権又は代理権を付与されているに過ぎないため、仮に保佐人や補助人に死後事務に関する権限を付
与するものとすると、保佐人等が生前よりもかえって強い権限を持つことになりかねないからであるという説明がされている。
したがって、民法873条の2は、保佐人や補助人には適用されないものと解される。
なお、後見人の場合と同じように、保佐人や補助人についても従前から存在する応急処分や事務管理の規定に基づいて死後事務を行うことは、直ちに否定されるものではない。