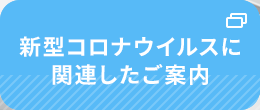裁判員裁判レポート
●大薗 昌平 Shohei Ozono (67期)
●開原 早紀 Saki Kaihara (73期)
裁判員裁判対象事件の国選名簿
当会では、通常の成人国選弁護人名簿のほかに、裁判員裁判対象事件の国選弁護人名簿が存在する(S 名簿)。特定の研修の履修などが名簿登載の条件となっている。名簿に登載されると、裁判員裁判対象事件の国選弁護人の指名打診が行われるようになる。
裁判員裁判対象事件では、「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる事件」の場合、刑事訴訟法第37条の5に基づいて、国選弁護人の複数選任を認める運用が裁判所でも採用されている。そのため、裁判員裁判対象事件の配点があった場合、所定の手続を経て、裁判所に複数選任の申入れをすることができる(なお、裁判員裁判対象事件の中でも、傷害致死被疑事件など、法定刑の要件を充足しないために被疑者段階における複数選任が認められない罪名も存在する。)。
今回は、初めて1人目弁護人として配点された裁判員裁判対象事件についての活動を振り返る。
初回接見
今回の裁判員裁判対象事件は、強盗致傷被疑事件であった。事案は、万引きをして逃走中に追いかけてきた店員に怪我をさせたという事後強盗致傷事件だった。
被疑事実では、被害金額は安くはないものの、怪我は加療約1週間とされていた。被疑事実の内容から、検察官が終局処分段階で窃盗と傷害に罪名を落として起訴することで、裁判員裁判にすることなく処理する可能性のある事案だった。
初回接見で、本人は暴行内容を否認していた。裁判員裁判対象事件である以前に否認事件と発覚し、黙秘の必要性がより一層高まった。
さらに、直近の万引き前科で罰金刑になっていることや、示談金を工面する余裕がそれほどないこともわかった。
依頼者には早速、黙秘を指示した(初回接見以降、依頼者は完全黙秘を貫くことができた。)。
悩ましいのは、示談が可能か、という点であった。示談が成立した事情が加われば、窃盗と傷害による起訴をより確実に狙え、場合によっては起訴猶予もあり得た。
一方で、依頼者は暴行を否認していて、怪我をした被害者との示談に否定的であった。初回接見の時点で、少なくとも示談方針について依頼者を説得するには時間を要するとの予想が立った。
依頼者は自宅に残してきた子供のことを常に心配していたが、子供の携帯電話の番号を覚えていなかった。また、自身の携帯電話は押収されており、携帯電話の宅下げを受けて連絡先を確認することはできなかった。弁護人としても、身体拘束からの解放のために家族と連絡をとる必要があったが、容易に依頼者の家族と連絡がとれる状況ではなかった。そこで、初回接見の翌日、依頼者の自宅まで行く予定を立てた。
裁判員裁判対象事件である強盗致傷被疑事件では、捜査段階でも裁判所に対して複数選任の申入れが可能である。今回の事件では、当会の大薗昌平弁護士に2人目の国選弁護人を依頼した。
複数の弁護人で事件を担当すると、弁護人の目が増える分、1人では気付かない事件の特殊性に気付くことができる。
大薗弁護士から、被害品を隠した依頼者のかばんはパンパンに膨れていたはずだとの指摘を受けた。そして、依頼者が今回の商品の盗み方で万引きが店舗に発覚すると思わなかったのだろうか、という疑問を呈示いただいた。私はこの疑問を聞いて、ハッとした。1人で被疑事実を見た際には、本件の万引き態様としか思わず、発覚しやすい万引き行動をとったことに疑問を抱かなかった。このことで自分の想像力の乏しさにも気付くことができた。
捜査段階では、当然のことながら弁護人は捜査資料も証拠も一切見ることはできない。弁護人の情報量が極めて限定的である捜査段階では、限られた情報から疑問を取りこぼすことなく、弁護活動につなげる必要がある。今回の事件の複数選任を通して、捜査段階で発見できる不自然さや、疑問点の重要性を再認識した。
捜査弁護(足を使って情報収集)
事件現場は、留置施設の周辺若しくは近い距離にあることが多い。私は接見ついでに現場に寄るようにしている。
今回は留置施設と犯行現場が近い位置関係になかった。そこで、依頼者の自宅に行く前に犯行現場である店舗に寄ることにした。現場で防犯カメラの存否や、万引き現場の様子を確認して、写真を撮影した。店内に防犯カメラが存在しないことも確認することができた。
また、店舗出入口には、盗犯防止用に、未精算の商品を持ち出そうとした場合にブザーがなる設備が存在することも一見して明らかだった。
店の利用者は店舗出入口を通らずして入店できないため、依頼者がこの設備を見ていることも明らかであった。これを知りながら万引きをしたのであれば、万引きの発覚リスクにも気付いていたはずであった。もし万引きが発覚しないと思っていたのであれば、それは不自然ではないか、との疑問も持つことができた。
被疑事実や店舗の様子から犯行態様の疑問に気付いたことで、何らかの病気の影響の可能性にも気を配ることができた。大薗弁護士と相談し、依頼者の自宅にて、依頼者の家族から依頼者の常備薬や服用中の薬、通院歴等も確認した。今回は大きく取り上げるべき情報はなかったが、病気等も含めた依頼者の状態を把握することは、その後の弁護方針にも影響を与えるので、丁寧な調査活動が重要であると感じた。
依頼者の家族から、身柄引受書と身柄引受人の身分証の写しも取得した。
しかし、捜査段階での黙秘が事実上悪影響を与えて準抗告は功を奏さなかった。
捜査弁護(示談)
初回接見から懸念していた示談について、大きく2つの問題があった。
1つは、依頼者の示談の意向だった。依頼者は店舗への被害弁償や示談には前向きであるものの、暴行を否認しているために怪我をした被害者との示談の抵抗は強かった。
依頼者の最大の望みである身体拘束からの早期解放を実現するには、示談をする方が圧倒的に有利なように思えた。
依頼者には、示談のメリットとしては
・窃盗、傷害の罪名による起訴の可能性がより高まること
・示談成立の事情が身体拘束からの解放との関係で有利であること
・示談成立の事情が最終的な刑との関係でも有利に働くこと(執行猶予の可能性がより高まること)を説明し、デメリットとしては、
・否認を維持した状態での示談となると、被害者の抵抗が強まり示談交渉が難航すること
・仮に暴行を争わない方針を採用して示談交渉を開始すれば、公判で主張をひっくり返して争うことはできないこと(否認主張が認められる可能性が極めて低くなり、かつ主張をひっくり返したこと自体が不利になること)を説明した。示談すべきとの弁護人の意見を依頼者に伝えた上で、示談をするか否かについて依頼者と何度も話し合った。
最終的に、依頼者は示談をするという意向を固めた。
最終的な意思確認には、大薗弁護士にも同席していただいた。暴行を否認している依頼者にとって、認めて示談をしていいのか、認めないが示談は進めてほしいのか、その意向の内容を明確にする必要があったからである。意向の最終確認を曖昧にすると、後で争えない等、依頼者に大きな不利益が生じることを改めて自覚した。
依頼者の意向が整った段階で、もう1つの問題は示談資金だった。示談金の原資を集めるのはそう簡単ではなかった。まずは親戚で示談金の支援者を探したが、親戚と連絡を取ることも容易ではなく、やっと連絡の取れた親戚からの援助もそれほど期待できない状況であった。
勾留期間内という時間制限では、示談交渉の時間確保も踏まえると、示談金の工面にそれほど時間をかけることはできなかった。最終的には、少ないながらも依頼者が自ら示談金を準備することで、示談の準備が整った。
刑事事件の弁護活動をする上で、刑事事件としては依頼者のメリットになるが、日常生活としては依頼者のデメリットになり得る場合がよくある。示談を締結すること自体も、依頼者の示談金支出や示談条項に基づく義務など様々な負担を強いることになる。常に依頼者の不利益になる可能性を見据えて、依頼者への説明を尽くす必要があると再認識した。
ほとんどの事案で、弁護人は依頼者の人生の一時点でしか関わらないが、依頼者にとっては一時点での出来事がその後の人生に大きな影響を与え得ることを、今回の件で身をもって体感した。
終局処分
依頼者の示談の意向と示談金の準備が整い、検察官から被害者の連絡先を聴取する段階になった。検察官としては、示談が成立した方が被害者に罪名落ちの説明をしやすいし、上司の決裁もとりやすい。そのため、検察官に最初から示談の意向があると伝えれば、検察官は示談が成立しない状況下での終局処分見込みをどうしても回答しづらくなってしまう。そこで、率直に終局処分の見込みを聞いた後に示談を検討していることを伝えて、不起訴若しくは罪名落ちの可能性が狙える示談内容を聞き出せないか、交渉することした。
今回の交渉を経て、これ以上情報は得られないのでは、と早めに撤退していた自分のこれまでの終局処分見込みの聴取方法を反省した。特に今回は、依頼者が否認していながら示談の意向を整えて、身を削って示談金を用意した。依頼者にとってはとても勇気のいる示談だった。その示談の効果の程度、最終的な終局処分への影響の程度を最大限聞き出すのは弁護人の務めであった。
今回の検察官は、弁護人とも率直に意見交換をしてくれる検察官だったため、粘り強く電話で交渉した。
その結果、決裁までに示談が成立すれば不起訴を検討している様子がうかがえた。
しかし、結果的に怪我をした被害者に示談の意向はなく、連絡先の回答は得られなかった。
従前の検察官の様子では、被害店舗との示談だけでは不起訴は狙えない様子だったため、被害店舗への示談は起訴を待ってから考えるということになった。
最終的に、依頼者は強盗致傷から窃盗と傷害に罪名が落ちて起訴された。執行猶予が十分に見込まれることと、怪我の程度が軽いことが理由だったと思われるが、依頼者が裁判員裁判になって長期の拘束を強いられることにならなくて、ほっとした。
公判と判決
公判段階では、起訴直後の保釈を請求したが、検察官の求意見には、「窃盗と傷害の罪名だとしても実質的には事後強盗である」と記載されていた。裁判員裁判を回避したとしても、罪名や事案の影響力は起訴後も消えていなかった。また、裁判官からは国選弁護人選任前に捜査機関によって作成された供述調書の内容も指摘された。
早期の身体拘束からの解放のために、依頼者と相談し、公訴事実は争わず、証拠意見も不利な部分に限定して不同意とした。依頼者は第一回公判期日前に保釈され、待ち望んだ家族のいる自宅に戻ることができた。
公判準備としては、やれることは全てやりたいとの依頼者の意向を踏まえて、被害店舗の連絡先を、手を尽くして入手し、示談の申入れをした。しかし、被害店舗に示談の意向はなく、交渉はできなかった。
依頼者が示談金を準備したこと、示談の申入れをしたことを示談経過報告書にまとめて、示談金準備の裏付けとなる添付資料をつけて証拠調べ請求をした。今後の生活があるので、供託まではしないという方針を採った。
示談の次にネックになると感じたのは、「直近で罰金刑になった万引き前科があるのに今回に及んだ」ことである。確かに万引きは、起訴猶予→罰金→執行猶予→実刑という経過をたどることが多いが、傷害罪が加わっている(しかも起訴後に傷害結果は加療約3週間に変わっていた)ため、安心はできないと考えていた。
犯情の議論は行うとして、被告人質問で依頼者のどの側面をうまく見せたら執行猶予にすべきとの事情が伝わるか考えた。その中で、依頼者の最大の原動力は家族だと気付いた。
そこで、被告人質問では、依頼者が家族のために二度とやらないと誓っていることを上手く語ることのできる質問を練り続けた。
その後、依頼者は執行猶予判決となった。
最後に
近年、裁判員裁判対象事件だけではなく、捜査段階において、取調べ対応として、黙秘を選択することが増えている。このこと自体は本来あるべき捜査弁護方針である。しかし、捜査官もそのことを認識している。そのため、逮捕直後の弁解録取や、検察官送致の際の弁解録取において、詳細に事件の内容を録取するケースも増えていると聞いている。国選の場合、検察官の弁解録取を終えてから選任されるため、弁護人のアドバイスを聞く前に詳細な供述調書が作成されていることは少なくない。制度上、やむを得ない部分はあるにしても、選任された場合にすぐに接見に行く重要性がより一層強くなっている。特に本件においても、弁護人が選任されるよりも前に作成された供述調書の記載を理由に、起訴後の保釈がなかなか通らなかったことがあった。
捜査弁護が発展していくのと同時に、それに応じた捜査機関の対応があることを常に頭に置き、より研さんを積むことの重要性を感じた事案であった。