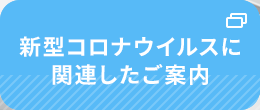少年とともに
研修:2021年少年法改正の概要と付添人活動における留意点
2022年2月15日実施
金矢 拓 Hiraku Kanaya (61期)
玉田 尚 士 Naohito Tamada (73期)
藤井 智紗子 Chisako Fujii (73期)
第1 はじめに
改正少年法が令和3年5月21日に成立し、令和4年4月1日に施行されました。同法は、18歳、19歳の少年(以下「特定少年」といいます。)につき、①保護処分決定の方法、②刑事処分の選択(逆送)を重視する事件類型(いわゆる「原則逆送」)の拡大、③推知報道禁止の公判請求後の解除、④ぐ犯の適用除外、⑤刑事事件の特例の一部不適用など、大規模な改正となっています。特定少年の事件は、弁護士が主に関わる観護措置がとられた事件の過半数を占めているため、今後は改正少年法について理解した上で事件に取り組んでいただく必要があります。
第2 少年法改正の概要
1 改正の経緯のポイント
本改正にあたっては、民法の成年年齢の引下げ等に併せて、少年法の適用年齢を引き下げ、罪を犯した18歳、19歳は成人として取り扱うべきではないかという議論が行われてきました。しかし、結果として少年法の適用年齢は引き下げられず、18歳や19歳については、20歳以上の成人と同様に取り扱うのではなく、少年法の中に新たに設けられた「特定少年の特例」の規定が適用されるということになりました。したがって、18歳、19歳の「特定少年」は少年法と異なる法律によって規律されるのではなく、少年法の枠内で一部18歳未満と異なる規律が及ぶことになったものであり、少年法の趣旨が及ぶことに変わりはありません。
2 保護処分決定の方法
(1) 少年院
- ア 家裁は、審判時に少年院送致の決定とともに、収容期間の上限(3年以下)を決めることになりました(改正少年法(以下法名省略)64条3項)。これまで18歳、19歳についても少年院法により20歳とされていた(ただし、収容継続によれば23歳まで、あるいは26歳まで可能な場合もありました。)収容期間の上限を、3年以下の範囲内で、犯情の軽重を考慮して個別に決めることになったものです。したがって、矯正教育が計画どおりに進まず、予定されていた処遇期間が長引く場合であっても、審判で決められた収容期間の上限をもって処遇(少年院仮退院後の保護観察を含みます。)が終了することになります。
- イ 第五種少年院が新設されました(少年院法4条1項5号)。同少年院は、施設送致申請事件(※2(5)で詳述。)で少年が送致される少年院です。同少年院は、少年院で処遇を終えるのではなく、保護観察で改善が図られる状態まで指導し、保護観察につなげることを目的としています。
- ウ 未決勾留の日数を少年院の収容期間に算入できるようになりました(64条4項)。しかし、実際には、55条移送されるような、観護措置等による拘束が長期間継続した場合等に限られると考えられています。
- ア 従前、保護観察の期間について定めはありませんでしたが、2年間の保護観察と6か月の保護観察が規定されました(64条1項)。
- イ 家裁が2年の保護観察決定をするときには、施設収容される期間の上限(1年以下)を定めることになります(64条2項)。この施設収容期間は、保護観察の遵守事項違反等の場合に対象とされる施設送致申請事件で少年院に収容される場合の収容期間の上限を定めるものです。
- ウ 6か月の保護観察では、施設送致申請事件に発展することは想定されていません。また、罰金以下の事件では、今まで保護処分に制限はありませんでしたが、6か月の保護観察のみが適用されることになりました(64条1項ただし書)。
①保護処分を決める際、②少年院の収容期間の上限を決める際、③保護観察決定時に少年院の収容期間の上限を決める際に、「犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において」決定することになりました(64条1~3項)。「犯情の軽重」の考慮とは、保護処分が行為責任の上限を上回ってはならないという趣旨であり、行為責任によって下限が画されたり、行為責任に比例して処分が選択されたりしなければならないとするものではありません。また、「犯情」という言葉が使われていますが、「犯情」重視という趣旨ではないことにも注意が必要です。
(4) 基準時
基準時は処分時です(64条1項)。犯行時に17歳であっても、処分時に18歳であれば、改正少年法の保護処分の対象となります。
(5) 施設送致申請事件
施設送致申請事件とは、保護観察中の少年が遵守事項を遵守せず、その程度が重い場合に、保護観察所長が家裁に対し、少年院送致の処分を求める事件です。改正少年法では、保護観察所長による少年への警告という要件がなくなりました(66条、更生保護法68条の2)。
3 刑事処分の選択(逆送)を重視する事件類型 (いわゆる「原則逆送」)の拡大
(1) 刑事処分相当の検察官送致
今までは、罰金以下の事件は対象となっていませんでしたが、罰金以下の事件についても検察官送致が可能となりました(62条1項)。
(2) 62条2項対象事件(いわゆる「原則逆送」の対象事件)
- ア 対象事件の拡大(同項2号)死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役又は禁錮にあたる罪の事件が対象となり、強盗罪、強制性交等罪及び建造物等以外放火罪などの事件が新たに対象となりました。
- イ 考慮要素に「犯行の結果」が追加(同項ただし書)今まで、いわゆる「原則逆送事件」は、故意の犯罪行為により、被害者を死亡させた罪の事件に限って対象とされていましたが、今回の改正により様々な事件が対象となるため、犯行の結果も考慮事情として含まれました。犯行の結果を重視するという趣旨ではありません。
- ウ 同項ただし書の解釈について同じ書きぶりの20条2項同様、保護不適推定説(特段の事情説:対象事件は、保護不適を推定したもので、ただし書を適用して刑事処分以外の措置を相当と判断するためには、原則を破るに足る「特段の事情」が必要)に立脚した上で、「特段の事情」の判断枠組みにつき、総合考慮説(狭義の犯情以外の要素も含めた総合考慮)によるのが実務上有力であろうと考えられます。
基準時は犯行時です(62条2項各号)。処分時に18歳であっても犯行時に17歳であれば対象となりません。また、令和4年3月までに起きた事件については、検察官送致の特例は適用されませんのでご注意ください(附則2条)。
4 推知報道禁止の公判請求後の解除
特定少年について、公判請求後に限って、推知報道の禁止が解除されます(68条)。基準時は犯行時です。公判提起時が18歳であっても、犯行時が17歳であれば解除の対象外になります。
5 ぐ犯の適用除外
特定少年は、民法上成年で親権から離脱すること等を考慮され、ぐ犯の適用が除外されます(65条1項)。基準時は手続時・処分時です。17歳の少年によるぐ犯事件であっても、処分時に18歳になれば、手続は終了します。
6 刑事事件の特例の一部不適用
特定少年には、検察官送致決定がされた後の少年法における刑事事件の特例が原則として適用されなくなりました。不適用となった規定の数が多く、紙面の都合上紹介できませんので67条を確認してください。
第3 事例を通して考える弁護人・付添人活動からみたポイント
1 事例
研修では、改正少年法下の仮想事例を2つ検討しました。紙面の都合上、1つを扱います。
令和5年2月15日。あなたは、少年事件の当番弁護士の出動要請を受けました。
被疑事実は、令和4年11月3日、友達と3人でコンビニエンスストアでカゴの中に商品をいっぱいにして、そのままレジ前を走って逃げ去るといういわゆる"かごダッシュ"をしたところ、店員が少年たちを追いかけてきて、捕まりそうになり、店員を振り払う際に強く突き飛ばして転ばせてしまったという事後強盗です。少年は、見張り役や外で待機して原付バイクで逃げる準備をする役ではなく、カゴを持って走って店から出る役でした。少年は、友達3人とゲーム感覚で犯行をしてしまい、自分たちが飲食したいお菓子や飲み物、パン等を3000円分ほどカゴに入れてやったと述べてます。
少年は、両親と同居している専門学校の学生で、令和4年12月1日に19歳になったそうです。
2 捜査段階
- 基本的に大事なことは変わらない
いわゆる「原則逆送」対象事件も、少年事件である限りまずは検察官から家裁送致されます。
非行事実だけでなく要保護性にも捜査段階から目を配り、要保護性消滅・低減のための活動を行いましょう。 - 62条2項対象事件の確認事後強盗罪(刑法238条・236条1項)は法定刑が「短期1年以上の懲役」にあたるため62条2項2号対象の罪であり、事例の少年は令和4年11月3日の犯行時18歳です。したがって、62条2項2号対象事件にあたります。なお、62条2項対象事件の基準時は犯行時、保護処分の基準時は処分時であることに注意してください。
- 送致罪名を検討し、検察官への申入れを家裁送致時の送致罪名は大きな意味を有します。事例では、窃盗罪と暴行罪の成立にとどまるとの主張もありうるところです。
成人事件なら起訴猶予となるような比較的軽微な事案も、少年事件で逆送決定後は45条5項により起訴強制となります。こうした不合理を回避するためにも、検察官に対し送致罪名の変更を積極的に申し入れましょう。 - 被害者対応の重要性
62条2項ただし書の調査の結果、刑事処分以外の措置が相当と認められた場合には検察官送致されません(※第2の3(2)ウも参照。)。また、法改正により被害弁償が重要となる強盗罪や強制性交等罪も62条2項2号対象事件となりました。
今まで以上に、被害弁償の有無が保護処分適否の判断や逆送後の刑事裁判の判断を左右する可能性があります。なお、示談するだけでなく少年自身が示談の意味を理解することが重要であることは一般の少年事件と変わりません。 - 勾留に代わる観護措置
東京では実務上、勾留に代わる観護措置がとられていません。もっとも、特定少年は勾留に代わる観護措置がとられにくいおそれがあり、東京以外の道府県では注意する必要があります。 - 逆送を見据えた弁護を逆送の可能性のある事件では、捜査・審判段階から一貫して逆送後の公判弁護活動を意識することが重要です。十分にケースセオリーを検討した上、供述や主張の方針を決定しましょう。
今回は改正法にかかる基礎的事項に留めますが、否認事件や逆送後に裁判員裁判が見込まれる事件はより慎重な活動が必要です。 - 保護者
民法の成年年齢引下げにより18歳以上の少年には「保護者」(2条2項)がいないとの見解と、少年を事実上監護する親は「保護者」にあたるとの見解があります。
かかる論点はさておいても、依然として親や家族が情報源や社会資源として重要であることは変わりません。
事例も両親と同居中の学生であり、親の事実上の監護下にあると予想され、環境調整や学校への連絡に際して親の協力は不可欠でしょう。 - 推知報道解禁に注意を
第2の4記載のとおり、特定少年が公訴提起された後は、推知報道が解禁されます。
しかし、実名報道は少年の更生に大きな支障を来しかねません。逆送後も55条移送により最終的に保護処分となることもあり、推知報道解禁には慎重であるべきです。報道機関に対して報道しないよう働きかけを行う必要があります。
3 家裁送致・審判段階
- 裁判官・調査官への働きかけ
送致罪名を確認の上、審判での活動方針を再構成しましょう。逆送が見込まれる事件でも、カンファレンスを行い、犯情に重きをおいた相場的な判断を防ぎ、丁寧な要保護性調査を求めることが大切です。審判段階の少年調査票が、逆送後の55条移送判断の重要な証拠となることもあります。 - 法律記録の謄写・社会記録のメモ
法律記録は逆送後の公判弁護のためにも、できる限り全部謄写しておきます。なお、全部謄写しても、法律記録以外の証拠や逆送決定後に作られる証拠もありますから、公判に向けた証拠開示の必要性は変わりません。
逆送後の公判で、社会記録の取調べに代えて弁護人・検察官が内容を要約・抜粋して作成した報告書を取り調べることもあります。社会記録も詳細にメモしておきましょう。
4 保護処分
- 少年院
特定少年であっても、付添人が的確な見通しや正確な知識を持ち、少年に説明する必要があります。
収容可能期間と、処遇期間として実際に在院する期間の違いや処遇勧告の意味等も事前に分かりやすく説明しましょう。社会復帰後の社会資源に対するフォローも必要です。 - 保護観察
2年の保護観察の場合に施設送致申請事件となるリスクについて、特に少年に対する遵守事項違反の不利益の説明が不可欠です。
5 検察官送致後
推知報道解禁は前述のとおりですが、公判で少年のプライバシーや情操保護のための措置がとられにくくなるおそれがあります。実名を出さない、着席位置を工夫するといった事実上の配慮を裁判所に求めましょう。
6 検察官送致決定後の手続
逆送決定後の付添人は、私選の場合は45条6項により弁護人に移行します。国選の場合は被疑者国選弁護人への切替手続が必要です。また、45条4項前段によるみなし勾留がつくため、勾留を争ったり留置場所の移送を阻止したりする活動が必要です。
なお、逆送決定はあくまで中間決定であるため、逆送決定自体に対する不服申立ては認められていません。
第4 18歳未満の付添人活動と具体的にどう変わるのか
1 おさらい ~少年事件の付添人活動は成人の公判弁護とどう違うのか~
最も基本的なことですが、少年事件の審判対象には、非行事実の存否以外に要保護性が含まれ、要保護性の判断基準時は、行為時ではなく審判時です。そのため、審判時までに変化しうる要保護性にどう向き合うかが、責任に応じた刑罰を言い渡す成人の公判における弁護との大きな違いです。
また、法律記録は家裁送致直後から閲覧が可能であり、社会記録も家裁係属歴があれば家裁送致時から前件までの家裁調査官の分析(少年調査票)を含め閲覧することができます。
そうすると、付添人としては、少年・保護者から聞いた話と、家裁係属後すぐに閲覧が可能になる記録に表れた事実・エピソード・分析を手がかりに、当該非行の原因(促進要因、機能しなかった阻害要因)を分析して要保護性を消滅・低減させる対策を考え、審判までに可能な対策を付添人主体で実行することで、要保護性に応じた処分のレベルを下げ、少年にとって不利益性の高い処分を可能な限り回避することが、要保護性に関する付添人活動の中身となるでしょう。
このような付添人活動の中身は、特定少年であるかや、犯情の軽重によって選択しうる処分によって変わることはありません。
まず、付添人自身が、この点を忘れずに活動することが何よりも重要です。
2 62条2項対象外事件の処分選択傾向は変わるのか
次に、62条2項の対象でない事件においても、犯罪行為に対する評価が今回の改正によって変えられたとみるべき、という主張が一部にあります。
しかし、法制審議会や国会の審議では、62条2項対象外の事件についてどのような処分選択がされるべきかという議論は一切されておらず、変えないのが立法者意思であるのは明らかであり、付添人には、かかる一部の主張に惑わされない活動が求められます。
3 まとめ
今回の改正によって、18歳、19歳については、特定少年として区分され、保護観察の種類が2種類になったり、推知報道が一部解禁されたり、とかく18歳未満の少年との違いに目がいきますが、少年法の健全育成・成長発達支援という目的規定の下、少年審判で要保護性が判断されるのですから、特に付添人活動においてするべき活動が変わることはなく、我々自身が付添人として、行為責任を過剰に意識しないことがより重要になるものと考えられます。
その上で、改正後の特定少年の事件を初めて担当される際には、本研修及び日弁連「少年法2021年改正に伴う付添人活動のQ&A」などを再度確認していただければと思います。