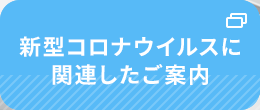労契法20条に関わる近時の裁判例の動向と分析及び今後の労契法20条の解釈論の方向性(後編)
後編 全2回(前編)

2 損害の認定
損害の認定に入ります。
(1)均等・均衡の考え方
均等・均衡の考え方については、ガイドラインとパートタイム・有期雇用労働法(パート有期法)の制度設計にややずれがあります。同一労働同一賃金というスローガンとの関係もありますが、実はガイドライン(案)と旧パート法で「均等・均衡」という概念が全く違っていました。
まず2016年12月に出されたガイドライン(案)は、もともと日本における「同一労働同一賃金」がヨーロッパの成功事例を基に作るということだったので、待遇ないし労働条件単位で職務の関連性を見る構造になっています。
そして、職務と関連のない待遇に関しては、同一の取扱いをすることを「均等」と位置付けています。このガイドライン(案)の考え方に基づくと、各種の手当は職務と関連がないことが多く、差をつけてはいけないという考え方になじみやすくなります。
また、職務と関連のある待遇に関しては、職務の違いに応じてバランスの取れた差はついていてもよい。このことを「均衡」と位置付けています。
これはこのガイドライン(案)の基となった東京大学社会科学研究所の水町先生の考え方であり、この学説では、均等と均衡を、まず待遇単位で検討し、次に職務との関連性を見ながら振り分けていきます。
他方、旧パート法は違う考え方をしていました。新パート有期法もそれを継承し、まず人単位で、職務内容や人材活用の仕組みなどの要件を見るのです。そして、職務等が同じ人を同じように扱うことを「均等」、職務等が違う人でもバランスよく扱うことを「均衡」と整理しました。人単位で均等待遇の対象者なのか均衡待遇の対象者なのかをまず振り分けて、同じであれば差別禁止で9条が適用され、全ての労働条件を同じにしなければならない。これに対し、職務が違う人に関しては8 条の均衡待遇でよいので、それぞれの労働条件がバランスの取れたものであるかという検討に入っていきます。均衡は必ずしも100%支払わなければならないことまでは意味していないと考えられます。
この点、ガイドライン的に考えると、職務など前提条件が同じ待遇は均等に100%という結論になりやすい。ガイドライン(案)が出されてからガイドラインになっていく過程でいくつかの地裁判決が出ていますが、複数の裁判例がガイドライン(案)を参考にしたとみられます。
ただし、違いに応じてバランスの取れた対応を求めるという不合理格差禁止の趣旨、すなわちパート有期法本来の考え方からすれば、割合的な損害賠償を認めることは、特に性質や支給目的が複雑で不明確な賃金項目については、望ましい場合もあります。
日本郵便の事件に関して東京地裁判決が手当を割合的に認めていますが、そういった考え方も、不合理格差禁止の趣旨からすれば決して間違いではありません。基となっている考え方が違うということです。
(2)割合的な認定がなされた例
割合的な損害の認定がなされた例を、いくつか挙げておきます。
日本郵便の東京地裁判決は、職務内容と関係の薄い、比較的支給目的のはっきりした手当であるにもかかわらず、100%ではない損害を認めた点で注目されます。例えば年末年始勤務手当や住居手当です。これを民訴法248条に基づき、損害がはっきりしない場合であると正直に認め、8割ないし6割を認めた事案です。少し異色で、この後は追随する判決は余り出ませんでした。
退職金や賞与については、もともとその趣旨がはっきりしていませんし、やはり額が大きいので割合的な損害賠償を認定する実務上の要求も大きいところだと思います。メトロコマースの高裁判決は退職金について正社員の4分の1、大阪医科薬科大学の高裁判決は賞与について正社員の60%を認めましたが、それぞれどこからそういう数字が出ているのかは、ある意味こじつけ的なところも否定できません。
メトロコマースの高裁判決はいろいろある退職金の趣旨のうちの1つに関して4分の1を認めるという、ある種のフィクションを明確に述べたものです。
これに対し、大阪医科薬科大学の高裁判決はなぜ60%なのか微妙です。これはアルバイトが訴えてきた事案ですが、アルバイト以外にももう1つ契約社員という非正規類型があります。支払われた賞与額を見ると、正社員が100だとすると契約社員は80でした。ところが、訴えてきたアルバイトは0でした。
恐らく、ここは60を認めれば、100、80、60 でちょうどバランスがよいと考えたのかもしれません。趣旨を細かく認定するというよりも、これぐらいは支払ってあげてもよいのではないかという認定だと思います。
大阪医科薬科大学の高裁判決では、症病欠勤中の賃金と休職給についても割合的な認定をしています。どのような割合で認定するか、あるいはもう認定できないから民訴法248条を使ってやるんだと正直に言ってしまうかは、最終的にはもう決めの問題だろうと思われます。
3 個別労働条件の性質認定
個別労働条件の性質認定に入ります。特に、労契法20条からパート有期法に変わっていくときに、性質認定が大変重要であるとされ、それが改正の条文上明記されました。
パート有期法8条は労契法20条から何が変わったかというと、待遇格差を見るときに職務内容、変更範囲、その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮し、不合理と認められる相違を設けてはならないとされました。
ここはガイドライン(案)の、待遇から見ていくという考え方にかなり寄った改正だと言えます。まず待遇の性質ないし目的に照らして何を考慮するかを決める点が、現在の労契法20条とは条文の構造上はっきりと違っているところです。
考慮する要素を何にするかも、その待遇の性質、目的を認定してから決めなければならないので、これまで以上に性質認定、目的認定が重要になってきます。
これまでの労契法20条は何をもって性質などを認定してきたかというと、特に手当に関してはその名称が大きく関係していました。ただ、それだけではなく支給基準や条件などを総合的に判断する傾向があります。賃金項目によってもかなり違うので4つに分けて説明します。
(1)基本給
まず基本給ですが、基本給の差が不合理だという原告の主張が認められたのは産業医科大学の高裁判決のみとなっています。これは基本給というか基本賃金ですけれども、30年以上臨時職員として雇用されてきたという「その他の事情」の部分が非常に大きく、かつ団体交渉などの労使自治による労働条件の改善も特になかったことが重視され、事案としては特殊であると言えます。
そもそも基本給に関しては、正規と非正規とで制度が異なることがほとんどです。正社員に関しては職能資格制度を使いますが、非正規は個別の時給制で決めるという場合が多く、それ自体どう決めると明記されておらず、性質認定が難しいという事情があります。
法的には正社員と非正規の制度、賃金の決め方を全て同じにしなければならないのかは、ずいぶん議論しました。2016年の検討会のときにも結構議論しましたし、ガイドライン(案)が出たときにも「注」が入り、あくまでもガイドライン(案)での言及は「同じ制度を適用している場合」とはっきりと書いてあります。
更に、「違う場合には必ずしもその限りではない」との記載は、現在のガイドライン中にも残っています。つまり、同じ制度であれば、同じ賃金にしなければならないとされていますが、違っている場合にも同じにしなければならないとは書いていません。
法律上、ガイドラインでも、制度の同一化までは求めていません。
違う制度のものをどう比べるかについて、厚労省で出している基本給に関するマニュアルでは、職務分析を用いて、違う決め方をしている正規、非正規の人に関しても、職務の価値を分析して確認する方法を勧めてはいますが、強制されているわけでもなく、このやり方でやらなければならないこともありません。そもそも比較は非常に難しいと思われます。それから定年後の賃金制度の変更は、事実上不合理性が否定される傾向にあると言えます。
【質問4:定年後再雇用者の相違】
質問4は、現行労契法20条、新法8条の解釈としては長澤運輸事件のように第1考慮要素と第2考慮要素に相違がない場合でも、定年後再雇用されたものであること及びそれにまつわる事情を考慮することによって、正社員との間に基本給、賞与、退職金の相違を設けること自体は否定されないと理解してよいでしょうかということです。新法9条の場合はどうなのかともあります。
新法9条の均等待遇に関しては、定年退職後再雇用では長期間雇用をすることは通常想定されていないので、この新法9条の要件である「当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において」との関連で、人材活用の仕組みが正社員とは異なるとされる可能性も否定できません。また、定年後再雇用であることを考慮して設けられた待遇の相違は、有期雇用労働者であることを理由とした差別的取扱いではないという説もあるところです。それらをどう考えますかというご質問でした。
新法9条では、「事業主は職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者であって、当該事業所における慣行、その他の事情から見て、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と、同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて差別的取り扱いをしてはならない」とあります。
これは人単位の均等待遇です。まず人単位で職務などの2要件を見ます。まさにこれは 2要件なので、大きな違いは「その他の事情」がないことです。新法9条の2要件を充足してしまうと、その他の事情は考慮されません。
この「人単位」で同一視される、通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に当たると、差別禁止の網が全部かかってしまうので、全部の労働条件を同じにしなければならないことになります。
他方、新法8条については労契法20条の最高裁判決の解釈を踏襲して、その他の事情として定年後再雇用という事情は重視されるだろうと思われます。新法9条については2つのパターンがあるでしょう。
大企業のように多種多様なポストがあって、配転や昇進に関してもいろいろな可能性があるというパターンにおいては、その雇用関係の存続する全期間において、人材活用の見込みが同じ再雇用者は極めて少ないと考えられます。他方で、小規模零細企業で状況が何も変わらないパターンでは、有期契約労働者などであることを理由とした差別かが問題となってきます。恐らく裁判所は結果の重大性を考慮するだろうと思われます。
新法9条は、いろいろな事情を考慮して労働条件に差をつけてよいという構造にはなっていませんので、何か考慮しようとすると、この「短時間・有期雇用労働者であることを理由として」というところしか手掛かりがないのです。
再雇用者が給付金や年金を受給しているという事情があって待遇にそれを考慮したい場合には、今後はその理由で争うことになるのではないかと思います。
【質問5:有為人材確保論】
それから質問5です。今後、将来的に有為な人材を確保するために高い労働条件を提示する、その差をつけてもよいという「有為人材確保論」という考え方は許されないということも言われていますが、本当でしょうか。基本給、手当、休暇、賞与、退職金の中で、有為人材確保論がなお相違の理由になり得るものはあるだろうかというご質問です。
有為人材確保論を強く敵視する考え方もありますが、その根底にはやはり原理的な同一労働同一賃金的な考え方があるのだろうと思います。同じ職場で同じ仕事をしているのだから同じように取り扱われるべきだ、その職場における平等を推進すべきだという考え方も非常に強いところです。
原理的な同一労働同一賃金の考え方に寄せていく立場や平等を重視する立場からすると、こういったことは当然許されないとなりますが、ただ法律上の賃金決定の大原則からするとやはり私的自治ないし労使自治は重要な価値です。最低賃金その他の賃金に関する強行規制を守っている限り、本来的には自分の採りたい人材を採るために、それに適する労働条件を提示する。それで結果的に、何らかのグループと差がついたとしても、そのこと自体が否定されるものではないと思います。企業として必要な人材確保のために労働条件に工夫を凝らす自由は否定されるべきではないと私は考えています。
ただし、正規、非正規の制度的分断が社会問題化して、均等・均衡待遇原則が法制度化されてしまった以上、使用者が事後的な自己正当化として、漫然と有為人材確保論を持ち出すことは厳しいでしょう。インセンティブ手当を付けるなどはよいとして、問題は基本給です。基本給は、有為な人材を得るために高い条件を提示していますということが、実は言いにくいのではないでしょうか。
というのは、結局、制度的に同じ賃金が支払われる正社員の中には、有為でない人材もいるわけです。しかし結果として、正社員として入社できさえすれば皆長期間にわたって高い労働条件を享受できるとするなら、それは本当に有為な人材を採るためだったと言えるのかどうか。その判断が難しいのではないかと考えています。
一方で今、様々な企業が、特に技術系で必要とされているビッグデータやAIを扱う人材に関して、新卒でも1,000万円以上の賃金を提示するなどしていますが、そうした工夫が否定されるようなことは望ましくありません。
そういう意味では、不合理かどうかを考えるときに、解釈論が出てきた初期の段階では、社会的に不公正な部分を切り取り、そこを不合理だと法的に評価するという立場があり、それに対する批判も多かったのですが、今はその原則に立ち戻りつつあるのではないかと思います。
合理か不合理かという問題に対して、最高裁は不合理か否かを判断するのだとはっきり述べました。それは、結局は裁判所における法的な評価は抑制的な判断にとどまるということではないかと考えています。
(2) 手当
それから、手当です。手当の性質認定ですが、通勤手当などは支給条件が客観的に明確なものが多く、そういった判断は、妥当かどうかはともかく、だいぶ収斂してきています。通勤手当に関しては同じ額を認めるのが大勢です。
しかし、本当にそれでよいのかと、個人的には差を付けてもよいのではないかと思っています。正社員は遠いところからでも、あるいは、転居しても支給すると。一方、パートや有期雇用の人に関してはごく近場で来てもらえる人を優先しているという考え方で、通勤手当を全く支給しないとなると問題だとしても、支給の条件に差を付けておくことが不合理ではないケースもあるのではないかと思います。しかし、裁判例としては100%同じく認める傾向です。
それはそうとして、多様な性質を持ち得る手当に関しては、その認定によって判断が変わってきます。法改正後は、待遇の性質や目的の認定がまず重要で、そこから考慮要素として適切なものを決めていくパターンになりますので、その認定がより問題となってきます。ガイドラインはいろいろな手当を挙げてい ますが、重要なものが載っていません。大きなものは家族手当、扶養手当、それから住宅手当、住居手当です。これらはどういうふうに性質認定するかで結論が違ってきています。長澤運輸事件の最高裁判決は、扶養手当は 扶養家族の生活費補助であると性質認定をしました。そして定年後は扶養家族の生活を補助する趣旨がそれほど該当しない。扶養家族も自立しているでしょうということでしょうか。これに対し、正社員はまだ若くて扶養家族が多い人もいるということを考慮して、不合理ではないと判断しています。
一方、日本郵便の大阪地裁判決は、扶養手当は生活保障給であると見ています。配偶者や扶養家族による生活費の増加に関して、正規と非正規で差を付けてよい理由はないので、不合理であると判断しました。
また、住宅手当、ないし、住居手当に関しても、趣旨をどう見るかで結論が違ってきています。これを批判されている有為人材の獲得・定着であると性質認定したメトロコマース東京地裁判決は、それも一定程度合理的であると、不合理ではないと判断しました。
しかし、正社員の配転に伴って見込まれる住宅コストの増大に対応したのだと、全く違う趣旨を読み込んだハマキョウレックス事件の高裁判決と最高裁判決は、確かに正社員には配転があることから、不合理ではないと判断をしています。
一方で、住宅手当、住居手当は生活費の補助であるという見方をするものもあります。メトロコマース事件の高裁判決などです。となると、生活費として家賃がかかるのは、正規であっても非正規であっても同じなので、これに差を付けることは不合理だという判断になりました。
更に、井関松山製造所事件の地裁判決も、住宅手当は住宅費用負担の補助であると認定しています。これも生活費の補助と解釈した場合と同様に不合理であると判断しています。つまり、結論は性質・目的の認定によって相当変わり得るということです。
【質問6:無期転換を選択しない労働者】
質問6は、有期契約労働者のある労働条件が、無期転換を選択すれば改善される制度を採っている場合、無期転換を選択できるのにしないで更新し続ける有期契約労働者との関係で、正社員との相違が不合理ではないと評価することはできるでしょうかというご質問でした。
流動性があり、しかも、無期転換ができるにもかかわらず、あえてしないという事情は、両者間の労働条件格差は不合理ではないと判断される方向に働くと考えられます。井関松山製造所、ないし、井関松山ファクトリーの同じような別の2つの事件について、流動性があることを不合理性を否定する方向に認定した裁判例があります。
(3) 賞与
それから、賞与に関しては、最高裁判決では多様な趣旨があるとざっくり言っていまして、その多様な趣旨に何が含まれているのかまで踏み込んだ分析はされていません。むしろ、年収で見たときに正社員の8割程度が保障されているといった事情を見て、不合理ではないと判断しています。つまり、長澤運輸事件の最高裁は賞与の趣旨を要因分解してはいないのです。
しかし、裁判所によって判断は分かれています。先述の30年以上臨時職員として雇用され続けていた、その他の事情を重視した産業医科大学の高裁判決は、賞与の差の不合理性を認めて正社員と同額を認めています。有期に関してはいわゆる新法9条の均等待遇がないなかで、この段階でかなり新法9条に近い判断をしたものと言えます。
賞与算定期間の在籍、就労それ自体に対する対価だと分析した大阪医科薬科大学の高裁判決は、一方で長期就労への誘引や経営判断の尊重などで、60%未満を不合理だと判断しています。在籍、就労それ自体に対する対価なのに、いろいろな経営判断などにより60% としたのは裁判所の謙抑的な姿勢の表れともみえます。
(4) 退職金
それから退職金です。これもガイドラインの中には取扱いが例示されていないタイプの賃金項目です。これまで認容されたのはメトロコマースの高裁判決のみです。これは割合的な認定でも、性格をある程度要因分解をしたパターンです。退職金にもいろいろな性格がありますが、そのうち、功労報償的な性格を持つ部分があると。その部分を4分の1と認定して、その部分について払っていない点は不合理だと認定しています。
同じように割合的な認定をしていても、賞与に関する大阪医科薬科大学の高裁判決と似たような判断に見えて、発想は全く違います。あくまでもメトロコマースの4分の1というのは、待遇の性格を切り分けて、4分の1の功労報償的な部分に関しては同じように扱わなければならないというガイドライン的な均等の考え方を採っています。
これに対して大阪医科薬科大学の60%という数字は、「せめてこれぐらいは」というような、まさにバランスを考慮した量的、割合的な判断といえ、実は両者は全く違う発想に立っているのです。
4 他の労働条件
それから、他の労働条件との関係です。不合理性は個別労働条件ごとに判断すると最高裁判決は言っていますが、他の労働条件を考慮することが否定されるわけではありません。ただ、経緯や実務上の取扱いをもって、容易に相関関係が認められるわけでもないという傾向にあります。
例えば、九水運輸商事事件の高裁判決は、通勤手当の額に差がありましたが、この争いが訴訟になったことで、使用者側が通勤手当の額を同じにそろえました。ところが、一方で正社員側の職能給にその部分を上乗せしました。すなわち、正社員側の通勤手当の差額を非正規側に合わせる形で削ったけれども、それを基本給に乗せてあげて、総額で不利にならないからいいよねと正社員側には言い訳をしつつ、有期雇用の人には通勤手当の額が同じになったからいいでしょうと言った事案です。
当然、争っていた有期雇用労働者は、結局同じ差額がずっと続いていると争うわけですが、裁判所は、直ちに職能給の増額された部分が通勤手当の差額であってその差額がずっと続いていると認めることはできない、と判断しました。
一方で、ハマキョウレックス事件の差戻し高裁判決では、非正規への皆勤手当の不支給につき昇給が代償措置と言えるかが判断され、結果的になっていないと認定しています。ハマキョウレックス事件はもともとハマキョウ(差戻し審)事件とかっこ付きで呼ばれていましたが、ここで言っている差戻し高裁判決は2018年6月1日の最高裁判決が出て皆勤手当と昇給との関係を見直すべく差し戻されたその後の高裁判決のことを指しています。
合理的な代償措置と評価できれば、不合理性の評価障害事実となると述べているので、その点が今後の決め手になっていくと思われます。
そうやって見ると九水運輸商事事件は微妙ですが、争っていた通勤手当の額が同じになった以上、基本給で争わなければ難しくなるということでしょう。基本給の違いを争うのは非常に難しいので、手当を揃えて基本給の差が拡大することが弊害として予想されてはいましたが、現象として起きています。
5 労使の関係
次に、労使の関与はどのように扱われているかです。団体交渉などの結果は不合理性判断に影響しているようには見えます。ただ、非正規の意見が反映されているか否かを実質的に加味して考える傾向も読み取れます。
一般論として、長澤運輸事件の最高裁判決などは、そもそも賃金決定は労使自治に委ねられるべき部分が大きいと原則を確認していますし、日本郵便の高裁判決なども賃金に関する労働条件の在り方については、基本的には労使自治に委ねられるべき部分が大きいとしています。
ただ、何でもそう言えるかというとそうではなくて、産業医科大学の高裁判決では、そもそも問題となっている臨時職員については団体交渉などによる労使自治で労働条件の改善が図られていたと言うことができない事情があるとして、労使自治と言えば何でも許されるわけではないと限定をかけています。 しかし、日本の企業別組合の多くは正社員主体の組合です。そういった労使交渉でも非正規労働者の利益を考えなければならないのか。ただ、職場の公正代表として組合があるわけではなくて、本来的には労働組合はその構成員である組合員のために動くものですから、正社員組合だったら、正社員の利益を代表して何が悪いという話になるわけです。
ですから、これは使用者側がリスクマネジメントとして、本来的な団体交渉でもし汲めないのであれば、別に非正規労働者の意見を反映させるシステムを構築する必要性を示しているのです。
6 説明義務
最後に説明義務についてです。今後は新法14条の説明義務が入ってきますし、その説明義務を果たさない場合には不合理性判断における、その他の事情として考慮されることになります。これまで見てきたように、どの無期フルタイム労働者との待遇格差も不合理であってはならず、比較対象はパート、有期労働者が選択できることになっています。ただし、説明を果たすべき対象は、使用者が一番職務内容が近いと考える労働者の労働条件でよいことになっていて、求められる情報が必ずしも得られるとは限らないという状況にあります。
その齟齬について、政府は都道府県の労働局が任意で、本当はこの人との労働条件の格差を問題にしたいと言われたときに、当該労働条件の説明を使用者側に指導するということが想定されているようです。しかし、それもあくまでも任意でやりなさいという指導にすぎませんので、それらは今後の課題になると考えています。