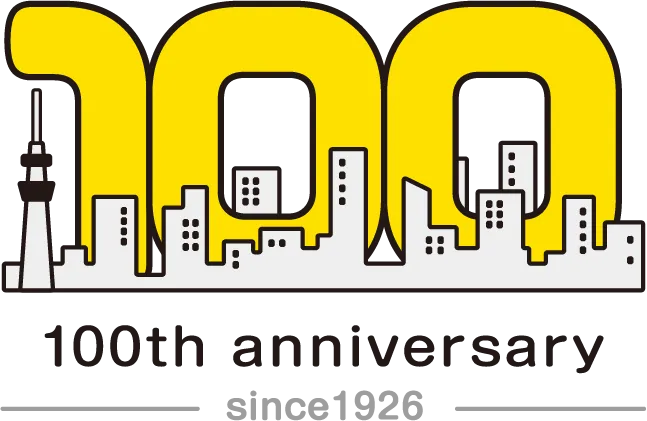刑事裁判のQ&A
「無罪推定の原則」とは、 犯罪を行ったと疑われて捜査の対象となった人(被疑者)や、刑事裁判を受ける人(被告人)について、刑事裁判で有罪が確定するまでは、罪を犯していない人として扱わなければならない、という原則です。
これは、日本だけでなく、世界の刑事裁判制度に共通する原理です(世界人権宣言11条1項、市民的及び政治的権利に関する国際規約14条2項)。
「無罪推定の原則」を受けて、刑事裁判においては、検察官が被告人の犯罪を証明できなければ、有罪とすることができません。被告人の側から見れば、被告人が無実を証明する必要はなく、裁判で自ら無罪であるという説明をする義務もない、ということになります。
犯罪事実が、法廷に提出された証拠だけでは、あったともなかったとも確信できないときは、被告人に有利な方向で判断しなければなりません。これを、「疑わしきは被告人の利益に」の原則といいます。
刑事裁判で有罪となれば、罰金刑、懲役刑、死刑などの刑罰が与えられ、市民の財産、自由、そして場合によっては生命までをも奪うことがあります。
それだけに、被告人が有罪であるというはっきりとした証拠がなければ、このような結論を出してはなりません。
過去の歴史をみると、きちんとした証拠がないまま、「疑い」だけで市民の皆さまの財産、自由、生命が奪われることがありました。このように、人類が大きな犠牲を払った歴史から学んで、市民の権利、人間の尊厳を守るための知恵として、「無罪推定」、「疑わしきは被告人の利益に」などの原則が導かれたのです。
刑事裁判における主張と立証は、原則として、検察官と被告人・弁護人の論争によって進められます。裁判所は、自ら進んで有罪・無罪を調査するのではなく、両者の主張と証拠をもとに、第三者として判断をすることになります。
裁判員は、「検察官から提出された証拠によって被告人の無罪推定がくつがえったかどうか」を、まず判断することになります。
このとき、「無罪推定をくつがえす証明」のハードルは、とても高いものが要求されています。
刑事裁判では、「確からしい」という程度の証明では足りません。検察官は、常識に照らして合理的な疑問が残らない程度にまで被告人が有罪であるという証明ができないと、無罪推定をくつがえすことはできません。
これを「合理的な疑問を残さない程度の証明」と呼んでいます。
裁判員には、裁判官と一緒に、このような刑事裁判のルールに従って、判断していただきます。
つまり、検察官の提出した有罪の証拠に、常識に照らして合理的な疑問がないかどうかを検討し、疑問が残らなければ有罪、少しでも疑問が残れば無罪と判断することになります。
この点において、裁判員のみなさんの、それぞれの「常識」を踏まえた判断が期待されているのです。
そのうえで、被告人が有罪であると判断した場合には、さらにどのような刑が妥当かを判断することになります。これを量刑判断といいます。(実際の刑事裁判では、被告人が自ら罪を認めている事件が多いのが実情です。そのような事件においては、量刑判断の比重が大きくなります。)
この量刑判断においても、「常識」を踏まえることが期待されています。
「弁護士はどうして悪い人の味方をするの?」
― そのような素朴な疑問をお持ちの人もいるかもしれません。
まず知って頂きたいのは、逮捕されたり起訴されたりした人が「悪い人」つまり本当に罪を犯した人ではない場合があるということです。
マスコミなどでは、逮捕されたり起訴されたりすると、その人が罪を犯した「悪い人」であると決めつけるような報道がされるかもしれません。しかし、それだけでは、その人が本当に罪を犯した「悪い人」であるとは限りません。
そこで、本当にその人が罪を犯した人であるかどうかを、証拠に基づいて第三者が冷静に判断する手続が必要になります。罪を犯していない人、つまり「悪くない人」が間違って処罰されてしまうことがないようにするのが刑事裁判の第一の役割です。
捜査に携わる人たちも神ならぬ人間です。間違った思い込みから、罪を犯していない人に疑いを向けてしまうというケースも、どうしても出てきます。疑いを向けられる人の中に無実の人が紛れ込む可能性を完全にゼロにすることはできません。
ひとたび犯罪者としての疑いを向けられた一市民が自分の力で無実を証明することは非常に困難です。身体の拘束を受けている場合はなおさら困難です。捜査機関である検察や警察は、捜索や差押などさまざまな強制力をもって、しかも組織的に、証拠を収集することができます。これに対して、被疑者や被告人は、そのような力を持っていません。主張立証の技術や法律知識の面でも大きな差があります。そのため、被疑者・被告人の側をサポートする法律のプロが必要になるのです。それが弁護人です。
また、被告人が実際に罪を犯した場合、つまり「悪い人」だった場合であっても、不当に重く処罰されることがあってはなりません。犯罪者の処罰が正義の要請であるのと同じように、罪と罰の正しい均衡もまた正義の要請だからです。
罪を犯した人、つまり「悪い人」であっても、その事情をも最大限考慮した上で、あらかじめ定められた法律に従って、犯した罪との均衡を失しない刑罰を科すことが刑事裁判の第二の役割です。
刑の種類や重さは、その事件を取り巻くもろもろの事情を踏まえて決定されます。このとき、被告人にとって不利な事情は検察官が主張しますが、被告人にとって有利な事情を、被告人が自分で主張していくことはなかなか困難です。そこで、弁護人のサポートが必要になります。弁護人がその事件に別の方向から光を当て、被告人に酌むべき事情があることを主張することで、有利不利すべての事情を踏まえた適正な刑の判断ができるようになるのです。
以上のように、今日の刑事裁判は、無実の者が処罰されることを防ぎ、罪を犯した者に対しては適正な刑罰を科すために、弁護人という役割を含めて、長い歴史を経て作り上げられたシステムなのです。
弁護人の役割は、この刑事裁判というシステムが正しく機能しているかどうかをチェックすることです。捜査機関が違法な捜査をしていないか、裁判所が憲法や法律の定める手続をきちんと守って裁判をしているか、そういったことを、被告人の弁護を通じてチェックするのです。これは、刑事裁判という制度を守るため、ひいては、いつ犯罪者の疑いを向けられるかもしれないすべての市民の生活の安全のために、必要不可欠な役割なのです。
ですから、被告人が「自分は罪を犯していない」と争っている場合でも、罪を認めている場合でも、弁護人のサポートが必要になるのです。弁護人は、「悪い人」の味方をしているのではなく、裁判官や裁判員の公平な判断を引き出すために、とても重要な役割を担っているのだということを理解していただければと思います。